川越 宣明 院長の独自取材記事
川越内科クリニック
(三鷹市/三鷹駅)
最終更新日:2025/09/29

三鷹駅もしくは吉祥寺駅からバスで15分ほどの場所に、「川越内科クリニック」はある。患者がくつろいで診察を受けられるよう、書斎を意識した診察室にしてあるという同院。川越宣明(よしあき)院長は、「より身近で、わかりやすく、専門性が高い医療」を理念に、糖尿病や甲状腺の病気など内分泌代謝内科を専門に診療。糖尿病にかかってしまうと、食事の楽しみを奪われたと落ち込む患者が多いが、川越先生は患者の食の好み、好きなお酒の種類や量を聞き出しながら、患者が実践しようと思えるような生活習慣の改善に尽力する。診察までの待ち時間や検査時間の軽減、精度にこだわった検査機器をそろえるなど、理想のクリニックづくりをめざす川越先生に話を聞いた。
(取材日2025年3月11日)
高水準の検査と治療を受けられる理想のクリニックを
糖尿病と甲状腺疾患を専門にしているそうですね。

当院が診療している内分泌代謝内科という領域では、甲状腺や副腎の病気などの内分泌疾患と、糖尿病や痛風、脂質異常症などの代謝に関する病気を診ています。食生活の欧米化や自動車社会による運動不足で、昔の日本には少なかった代謝疾患が急速に増えています。甲状腺の病気で有名なのは、バセドウ病と橋本病。バセドウ病は再発率が約30%とされていますが、うまくコントロールすれば投薬の中止や、寛解した状態を維持することが望める場合もあります。甲状腺機能が低下する橋本病は、もともと人体にある不足した甲状腺ホルモンを補い、ホルモンバランスを整える目的の治療を行っていきます。糖尿病や甲状腺疾患は、病院の受診を勧められるケースも多いですが、専門のクリニックで管理できることも少なくありません。当院は、専門的な診療が受けられ、気軽に相談できるような、大きな病院に行く前のワンクッションになるクリニックをめざしています。
糖尿病治療について教えてください。
糖尿病は生涯付き合っていく病気です。そのため治療では、合併症を出さずに平均寿命をめざして元気に楽しく生きていくことを目標にしています。治療せずに放置すると、5年ほどで手足のしびれなど神経障害を、10年ほどで眼底出血や失明を、10年以上経過すると腎不全や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こす恐れがあります。しかし、適切な治療を行うことで、深刻な状態になるリスクを減らすことが期待できます。そして、血糖値が高いから治療しなさいと話すだけでは患者さんにとって説明不足ですので「なぜ血糖値が高いとよくないのか?」についてきちんとお話しして治療の必要性や目標も理解していただけるよう心がけています。また、栄養相談にも力を入れており、糖尿病療養指導を専門に学んだ看護師や管理栄養士なども複数在籍しています。
栄養指導ではなく、栄養相談ですか?

糖尿病をはじめとする生活習慣病の治療では、「栄養指導」という言葉が日常的に使われています。しかし、私は「栄養相談」が正しいと考えています。「指導」という表現には、医療者が上の立場で患者さんが下という関係性を暗に含んでいると感じるからです。糖尿病の治療において大切なのは、医療者が患者さんを「指導」する立場であるという意識ではなく、ともに歩む「伴走者」であるという姿勢です。患者さんの生活に寄り添い、その人がより健やかに、前向きに人生を送ることができるようサポートするのが本来の医療の役割です。治療方針の決定や生活改善の提案も、一方的な命令口調ではなく、患者さんとともに考え、納得のいく形で進めていくべきだと考えています。
人生を楽しみながら生活習慣を見直し、病気と付き合う
患者の気持ちに寄り添う姿勢が大切なのですね。

糖尿病治療において大切なのは、「ペイシェント・センタード・ケア」。すなわち患者さん中心の医療です。医療者はあくまでサポート役であり、患者さんが糖尿病を抱えながらも、充実した人生を送れるよう支えることが使命です。糖尿病は何もせず放置してしまうと、失明や腎不全による透析、足の切断といった深刻な事態に発展することもあり、寿命にも影響を与えます。だからこそ合併症を予防し、「糖尿病はあるけれど元気です」と言える状態を維持していくことが重要です。そのためには、患者さんと医療者が対等な立場で協力し合う関係づくりが欠かせないのです。先ほども話したように、看護師や管理栄養士も含め私たちは、患者さんの伴走者のような存在となり、一方的な「指導」をするのではなく、患者さんの状況を丁寧に把握し、ともに最適な選択を考えていく。そのスタンスこそが、糖尿病治療の成功の鍵なのだと考えています。
患者は、糖尿病治療にどのように向き合えばいいでしょうか?
食事療法と運動療法は、糖尿病治療の基本です。しかし、糖尿病になると「食事制限ばかりで、人生の楽しみがなくなった」と感じる方も少なくありません。私もお酒や食べることが好きなので、その気持ちはよく理解できます。だからこそ、糖尿病の患者さんにも、できるだけ食事療法や運動療法を楽しんで取り組んでもらいたいのです。診察では、患者さんの食の好みや飲酒量などを把握した上で、改善のポイントを一緒に考えるよう心がけます。また、診察室や栄養相談室が「叱られる空間」になってはいけません。医師、看護師、管理栄養士との面談が、患者さんにとって楽しみであり、新しい知識や気づきを得られる前向きな場であるべきです。「体重が増えた」「血糖値が悪化した」といった事実に対して叱るのではなく、「これからどうしていくか、一緒に考えましょう」と提案する。その姿勢を大切にしています。
子どもでも糖尿病になるそうですね。

日本では成人の2型糖尿病が圧倒的に多いのですが、2型や1型糖尿病の子どもいます。1型糖尿病というのは、最終的には膵臓からインスリンが出なくなるタイプで、特に10代など若いうちに発症するケースが多いです。ある日突然、「今日から一生、朝昼晩インスリン注射が必要です」と言われたら、自分だったらショックを受けると思います。実際、口もきかずにずっと暗い顔をしている子もいます。それはそうだろうなと思うんです。糖尿病の治療は、ただ「これを食べましょう」とか「インスリンを打ちましょう」と言えば済む話ではない。特に1型の子たちには、まず気持ちに寄り添って、信頼関係をじっくり築いていくのが大事です。本人だって、頭では必要なことはわかってるんですよ。でも、心が追いつかないんです。だから私は、上から指導するのではなくて、マラソンの伴走者みたいに、横で一緒に走る存在でいたいと思っているのです。
身近で専門性が高く、わかりやすい医療の提供をめざす
検査にも力を入れているとか。

HbA1cや血糖値の測定器、血球分析装置、動脈硬化を測定する装置、超音波診断装置などを導入しています。超音波検査専門の臨床検査技師も在籍しています。なぜ、超音波診断にこだわるのかというと、糖尿病が動脈硬化とがんに関連性がある病気だからです。中でも、糖尿病の人のがんの見逃しは命にかかわります。血液検査をしているから大丈夫だろうという医師の油断で発見が遅れることはあってはならないことです。がんは、進行しないと血液検査で異常値が発見できない場合もあります。当院では、糖尿病患者さんに年に1回は必ず肝臓や胆嚢、膵臓などを超音波で検査をし、臓器のがんなどの早期発見に努めています。また、頸動脈の動脈硬化や甲状腺がんの発見にも、超音波検査は非常に有用です。
医師になったきっかけは?
祖父と父が歯科医師で、他にも身内に医師や歯科医師が多い家庭環境で育ちました。小さな頃から遊び場が自宅兼歯科医院で、医療の道に進むことは自然の流れでした。人と関わるのも好きで、両親からは「世の中に還元できる人間になりなさい」と言われて育ちました。微力ながらも人に還元し、貢献する医師という仕事は大げさかもしれませんが天職と感じています。
今後の展望をお聞かせください。
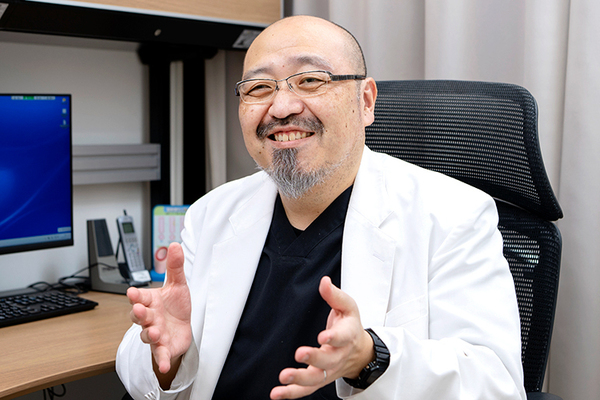
研修医の頃、「最先端の医療も必要だが、最前線の医療も必要」だと教えられました。医学の進歩に向けた最先端医療の研究と、実際の臨床現場で患者さんとじっくり向き合う最前線の医療のどちらも重要です。診療では、「より身近で、専門性が高く、わかりやすい医療」を理念に「受診した患者さんは全員笑顔で帰宅していただく」ことをモットーにしていますから、「医療機関=暗いイメージ」というふうには捉えないでほしいですね。そして最前線の医療として、糖尿病や甲状腺疾患はもちろんですが、かかりつけ医として気軽に相談してもらえればうれしいです。






