歯を抜く必要があるケースとは?
抜歯の外科処置について知る
永福町駅前歯科・矯正歯科・小児歯科
(杉並区/永福町駅)
最終更新日:2025/11/27


- 保険診療
親知らずが起こす炎症や、虫歯が進行してつらい痛みがあるときに、治療の選択肢となる抜歯。とはいえ、歯を抜く処置への恐怖心は、多くの人が感じているはず。本当に抜歯しなければならない歯と、抜かずに済ませられる歯とを判断する基準はどこにあるのだろうか。また、歯を抜きたくない場合、どのような対処やケアが必要なのだろうか。「永福町駅徒歩1分の歯医者」として親しまれ、杉並区や渋谷区、三鷹市、武蔵野市などから多くの患者が訪れる「永福町駅前歯科・矯正歯科・小児歯科」の森田剛大院長は、「来院されて、いきなり抜歯をすることはありません。検査をして、患者さんのご意向、同意のもと、治療の方針を決定しますのでご安心ください」と話す。抜歯の判断基準や、抜かない場合の治療方法などについて、森田院長に話を聞いた。
(取材日2025年11月20日)
目次
腫れや隣の歯への悪影響の有無などが判断基準。患者自身の意向を尊重して抜歯の可否を判断
- Q抜歯は怖いというイメージがあります。
-
A
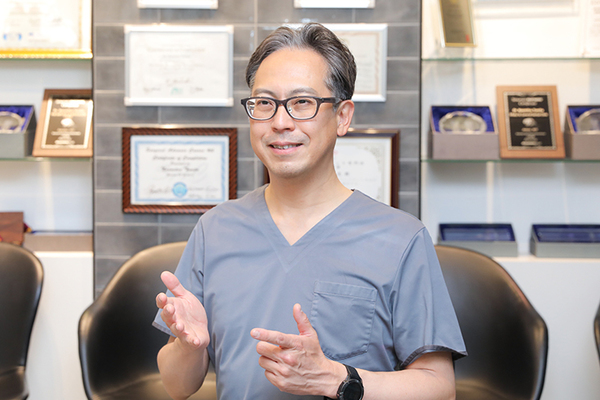
▲患者に寄り添い丁寧なカウンセリングを心がける
正直に言えば、私が患者さんの立場だったとしても抜歯への恐怖心はあると思いますし、怖いと思う気持ちそのものを無理に取り去ろうとしなくても良いと思います。大切なのは、なぜその歯を抜いたほうが良いのか、放置しておくとどのようなリスクがあるのか、メリットとデメリットをお伝えして、患者さん自身によくご理解いただくことです。その上で、ご本人が抜歯に同意されて、「怖い」から「頑張ろう」という気持ちになれるよう、丁寧な説明を心がけています。もちろん、患者さんの症状によって、抜かずに経過観察してもいいと思われる場合や、高次医療機関で抜歯の処置を行うべき場合などさまざまですので、そうした説明も適切に行います。
- Q歯の痛みはなぜ生じるのでしょうか?
-
A

▲納得して治療を受け入れてもらえるような診療を行う
原因はさまざまです。親知らずの周辺が汚れて歯肉が腫れてしまっている場合もあれば、大きく虫歯ができて神経を取ることを考えるレベルに悪化していたり、根管治療をしている歯の根の中に膿がたまっていたりすることもあります。少し腫れているくらいであれば、清潔に保って抗生物質を処方することで様子を見るという選択肢もありますが、歯が割れてしまっていて痛い場合などは、抜歯をしたほうが良いでしょう。親知らずが気になるという方は、ぜひ一度お口の中を見せていただければ思います。当院には杉並区、渋谷区、三鷹市、武蔵野市など京王井の頭線沿線地域から多くの方が来られます。土日診療もしていますので、お気軽にご来院ください。
- Q親知らずは、やはり抜かなくてはいけないのでしょうか?
-
A

▲半個室と個室タイプの診察室を完備
親知らずが生えてくるとき、顎に十分なスペースがないと、斜めに生えてきたり、歯茎の中に半分から全部が埋まったままになったりと、正常に機能しない状態で歯が存在することになります。その結果として、腫れて歯肉炎になってしまったり、隣の歯が虫歯になる原因になってしまったりしている場合には、抜歯をしたほうが良いでしょう。他方で、親知らずが骨の中に完全に埋まっている場合はリスクも小さいですし、清潔に管理できていて大きな腫れがない場合は、緊急性はありませんから、すぐに抜歯をする必要はないと考えられます。
- Q抜歯以外の選択肢について教えてください。
-
A

▲十分な問診と診断を行う当院
親知らずの場合は、よく洗浄して清潔に保つことに尽きます。重要なのは、腫れたり他の歯に悪影響を及ぼしたりするリスクをコントロールするということですね。親知らずでない歯の場合は、割れているものは抜くしかないのですが、それ以外でどうしても抜きたくないというときには、虫歯の状況によって、根管治療をして歯を残すことをめざすか、あるいは、歯肉よりも上に出ている歯であれば処置の選択肢も増えるため、ケース次第で歯肉の位置を下げる外科処置を行うこともあります。抜歯をするにせよ、他の選択肢を考えるにせよ、患者さんのご意向を尊重し、また処置後の予後の予測やリスクをきちんとお伝えして治療します。
- Q抜歯の外科処置を行うまでの流れを教えてください。
-
A

▲短時間で痛みの少ない治療をめざす
まずエックス線撮影をして歯の状況を確認し、抜歯のメリット・デメリットなどまで含めて、患者さんにしっかり説明をします。また、抜歯をするかしないかに関わらず、患者さんに疾患などがあれば医科の先生の対診書を作った上で、実際に抜歯をするかどうかを患者さんに選択していただきます。その後、抜歯をすると決まったら、必要に応じてCT検査も行った後、口腔内の汚れを取って清潔にした状態で、麻酔をかけて痛みに配慮しながら抜歯の処置をします。抜歯処置後は、処方されるお薬についてなどの説明をして終了となります。抜歯処置の際に糸で縫った箇所がある場合は、1~2週間後に抜糸を行って、一連の処置が終わりになります。
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。






