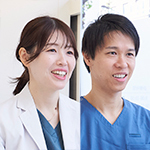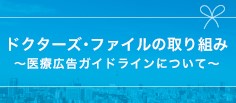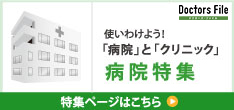- TOP >
- ドクターズ・ファイル特集一覧 >
- 足立区の医療情報
足立区
つくばエクスプレスや日暮里・舎人ライナーの開通、大学の誘致、駅前の再開発などを経て、雰囲気が大きく変わりつつあるまち。独自の施策による治安向上や子どもの学力向上なども相まって、若い世代からも注目されている。
足立区長インタビュー
一点突破型のユニーク施策を展開
子どもたちの居場所があるまちへ

- 近藤 やよい
- 区長
1959年足立区生まれ。青山学院大学大学院経済学博士前期課程修了。警視庁警察官、税理士を経て、1997年に東京都議会議員当選し、3期務める。2007年に足立区長選挙で初当選。現在4期目。「ビューティフル・ウインドウズ運動」「おいしい給食」など独自の施策を次々と展開している。
ここ数年、区内外から「足立区は変わった」と評判ですね。
足立区長として13年間、さまざまな施策を展開してきましたが、それぞれに成果が見えてきてうれしく思っています。中でも、治安を改善するために平成20年から始めた「ビューティフル・ウインドウズ運動」は、区民の皆さんが中心となってパトロールや清掃活動を行ってくださった結果、令和元年は犯罪認知件数が戦後最少となりました。減少に伴い、令和元年度の区の調査では「治安が良いと思う」区民の割合が50%を超えています。大学誘致も進んでおり、令和3年開設予定の文教大学を含めると区内6校となります。また、平成25年には、区民の健康寿命が都の平均より約2歳も短いという実情をオープンにし、区民1人あたりの国民健康保険の医療費が23区で最も高い糖尿病に着目した健康対策を開始。「あだちベジタベライフ〜そうだ、野菜を食べよう〜」を展開し、健康寿命が男女とも1歳以上延伸しました。
足立区では「透明性」を大事にしています。区にとってマイナスな情報でも隠さない。そして、区からの情報は、取りに来てもらうのではなく、届けに行く。「オープン」かつ「おせっかい」なサービスをモットーとしています。
子どもの貧困対策を進めていらっしゃいます。
どんな子どもにも、親や家庭の事情に左右されず、自分の力で未来を選択できるようになってほしいと思っています。足立区では親から子への「貧困の連鎖」を断ち切るための取り組みを推進。例えば、「子ども食堂」には子どもの第三の居場所となってほしいという思いで支援しています。子ども食堂で出会った大人が、その子のライフモデルになる。そこから未来が広がる、と考えています。また、家での学習が困難な中学生を対象とした「居場所を兼ねた学習支援」もそうした取り組みの一環です。このほか、区内には不登校の子どもが通える特例課程教室「あすテップ」もあります。今後は、外国にルーツを持つ子どもや、若年層に目を向けた居場所も用意していきます。
居場所づくりに力を入れている理由を教えてください。

大学生が中学生の学習をサポートするだけでなく、地域の高齢者など多世代の交流にもなっている学習支援
自分自身の苦しさが原点かもしれません。高校時代、学校になじめなかった時期があるのですが、そのときの居場所が保健室でした。保健室の先生が私をつき離さずにそっと見守ってくださった。その気持ちに助けられました。今、苦しんでいる子どもたちが、居場所を通して前向きに成長してくれたらいいなと思います。
足立区は、本当に困っている人、一歩踏み出せない人の背中をそっと押してあげられるような役所でありたいと思っています。
(2020年5月時点の情報です)