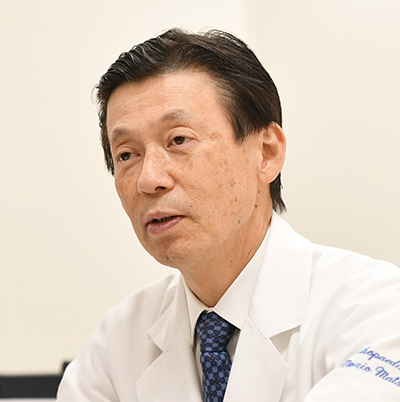
こちらの記事の監修医師
慶應義塾大学医学部整形外科学教室
松本 守雄 先生
ようついすべりしょう 腰椎すべり症
最終更新日:2022/01/04
概要
腰椎すべり症は、何らかの原因に腰の骨がずれてしまう病気です。その結果、腰痛や脚の痛みやしびれなどのさまざまな症状を引き起こします。また、腰椎すべり症は主に「分離すべり症」と「変性すべり症」の2種類に分けることができます。「分離すべり症」は、背骨の本体である椎体と関節を支えている椎弓が分離してしまう状態、「変性すべり症」は、加齢に伴い骨と骨の間にある椎間板や靭帯など、腰椎を安定化している組織が変性したことでずれてしまった状態を指します。主な症状は腰痛であり、エックス線検査などで偶然見つかることも多く、症状が軽度の場合は保存療法、症状が重度もしくは保存療法でも改善されなければ手術療法が検討されます。
原因
腰椎すべり症を発症する明らかな原因はわかっていません。「変性すべり症」は「分離すべり症」に比べて発生の頻度が高く、中年以降の女性に多く見られることから女性ホルモンの影響を受けているのではないかとも言われています。「分離すべり症」は、思春期のスポーツ活動などによる腰の骨の疲労骨折である「腰椎分離症」に引き続いて生じ、第5腰椎に多いのが特徴です。
症状
主な症状としては腰痛と坐骨神経痛があります。すべりが重度になるにつれ、腰椎後方の脊柱管という神経の通り道が細くなり、脊髄神経が圧迫されることが要因となり、下肢に痛みやしびれが症状として表れることがあります。また、少しの距離を歩くだけで臀部や太ももに痛みやしびれを感じ、少し休息を取ることで痛みは緩和するが、再び歩き始めると痛みやしびれが出るという間欠跛行と言う症状が見られることも特徴です。症状が軽度の場合には自分でも気づかないことが多いため、エックス線検査を行った時に偶然に腰椎すべり症が発見されることもあります。
検査・診断
問診、医師の診察、エックス線検査、必要であればMRI検査を行った上で診断します。腰椎の「ずれ」に関しては、エックス線検査を用いて腰椎を前後に曲げた状態(前屈位)での撮影を行うことで不安定性の程度を診断します。しかし、下肢の痛みやしびれ、歩行障害を来すといった腰椎すべり症と似たような症状の病気としては、椎間板ヘルニアや脊髄腫瘍なども考えられるため、これらの病気との鑑別も重要となります。
治療
腰椎すべり症の治療は、まず薬物療法や理学療法などの保存療法が行われます。消炎鎮痛剤、神経障害性疼痛治療薬の処方、腰への負担を軽減するためのコルセットの使用や、神経ブロック注射などを行います。間欠跛行が見られる方には神経の血流を良くするプロスタグランジン製剤の内服が有効なこともあります。これらの治療と並行し、腰椎のけん引や温熱療法、ストレッチや筋力トレーニングなどのリハビリテーションを実施することで、痛みやしびれなどの症状の軽減を図ります。しかし、これらの保存的療法を行っても症状が軽減されなかった場合や、痛みやしびれ、下肢の麻痺、排尿障害などの重度の症状により、日常生活に支障を来している場合には、手術療法を検討します。手術療法では、骨がずれて神経が圧迫されている状態を改善するために、まずは椎弓切除術あるいは形成術と呼ばれる除圧術、さらに必要に応じて脊椎固定術を行うこともあります。
予防/治療後の注意
腰痛すべり症に対する効果的な予防法はありません。しかし、腰回りやおなかの筋肉を鍛えておくこと、腰を動かして日常的にストレッチをするなど、腰への負担軽減につながる一般的な「腰痛」予防を継続的に行うことが大切です。肥満がある場合には適度な運動や食事療法により減量も図ります。また、保存療法や手術療法を終えた後も、日常生活の中で常に腰に負担をかけないように注意したりして生活を送る必要があります。
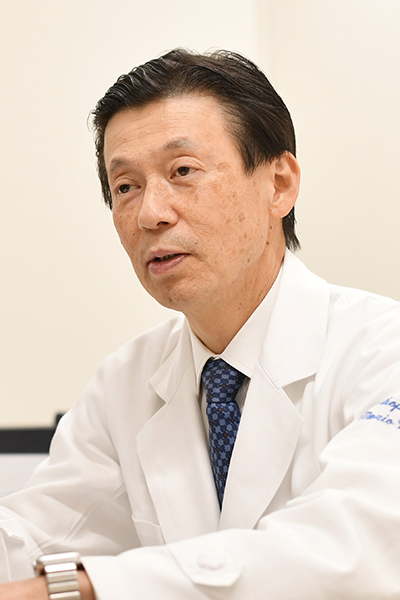
こちらの記事の監修医師
慶應義塾大学医学部整形外科学教室
松本 守雄 先生
1986年慶應義塾大学医学部卒業。同大学医学部にて研修の後、1988年同大学医学部整形外科学教室へ入局。米国ALBANY医科大学への留学などを経て、2008年慶應義塾大学医学部整形外科学教室の准教授に就任。2017年より現職。日本整形外科学会、日本側弯症学会にて理事長を務める。
初診に適した診療科目
都道府県からクリニック・病院を探す
| 関東 | |
|---|---|
| 関西 | |
| 東海 | |
| 北海道 | |
| 東北 | |
| 甲信越・北陸 | |
| 中国・四国 | |
| 九州・沖縄 |




