丁寧な問診と的確な検査が肝心
気になる咳は呼吸器内科の受診を
たけだクリニック
(豊川市/豊川駅)
最終更新日:2025/12/04


- 保険診療
子どもから高齢者まで幅広い年齢層を診療する「たけだクリニック」。武田正志院長は病院勤務医時代、内科系全般を診療、中でも気管支や肺などに起こる呼吸器疾患、アレルギー系疾患、感染症の診療を得意としてきた。同院では、呼吸器感染症や喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などを調べる検査機器を充実させ、早期の治療開始につなげている。病気は生活環境やライフスタイルも大きく関わってくるため、問診票や診察で細部にわたり聞き取りを行うことも重要だ。呼吸器疾患には禁煙が望ましいが、「その方に合わせてやんわりと伝えます」と配慮する武田院長。一方通行ではない対話を通した診療を大切にする同院の検査体制について話を聞いた。
(取材日2025年7月24日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Qこちらではどのような検査が受けられますか?
-
A
咳や痰がある場合の検査としてはまず胸部レントゲン検査、呼吸機能検査、呼吸抵抗検査、呼気NO(一酸化窒素)検査が挙げられます。それぞれ、肺の機能、気道の通りやすさ、気道の炎症などについて調べるものです。COPDの場合は呼吸機能検査ですぐわかります。喘息の場合はさらにピークフロー検査といって1回思いきり息を吐き、それによって動いた針が差した目盛りで息の強さを測る検査もあります。また、血液検査の好酸球数を調べ、アレルギー検査も行います。ほかに、呼吸器感染症の場合は、抗原検査や15種類の感染症を調べられる多項目同時PCR検査、また睡眠時無呼吸症候群の簡易検査にも対応しています。
- Qクリニックならではの特徴はありますか?
-
A
1つ目に、多くの検査がその日のうちに結果が出ることです。2つ目に、吸入方法を私が喘息の専門家として正しい知識、技能でもって患者さんに指導していることです。特に吸入薬が初めての方には私が実演してお見せしたり、練習用の吸入器を使ったり、自宅でも正しく吸入できるように日本喘息学会が作製した5分程度の動画をご紹介したりしています。看護師も私と同等のスキルを持っているので患者さんに繰り返し説明することができます。3つ目に、問診票を重視していることです。呼吸器疾患は症状もさまざまで生活環境も大きく関わってきます。そのためできるだけ細かく聞き取り、その方に適した治療法を選択したいと考えています。
- Q問診票について教えてください。
-
A
問診票は数種類用意しており、患者さんの症状や、初診か再診かによってお渡しするものが異なります。症状、基礎疾患、内服薬についてはもちろん、「感染症」の問診票では時系列の症状、職場とご家族の状況もお聞きしますし、「咳、痰」については、夜中に目が覚めるかどうか、鼻水、鼻詰まりはあるか、痰の色や量はどうかなど27の質問項目があります。「COPD」に関しては喫煙や息切れの程度について細かくお聞きします。逆流性食道炎が咳に関連することもあるので胸焼けについてお聞きする問診票もあります。ペットや枕、整髪料、さらに気温や天候の変化などについてのチェックリストも。人によっては問診票が何枚にもなりますね。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1問診票を記入する
-

同院では「感染症」「喘息」「咳・痰」「逆流性食道炎」「COPD」などいくつかの問診票が用意されている。人によっては複数枚の記入が必要になるが、的確な検査と治療に結びつけるため、思いあたる項目をチェックしよう。同院のホームページにはウェブ問診票があり、受診前の記入もできる。
- 2問診票をもとに医師の診察を受ける
-

喘息を例に挙げると、風邪が長引いたり、アレルギーが原因など、複合して発症することが多いため、医師からより細部にわたる質問を受ける。「例えば、日中は軽いのに、夜間咳が苦しくて眠れない場合は喘息の可能性があります」と武田院長。聴診では肺に雑音があるかどうかをしっかり診察。
- 3呼吸能力や肺機能の検査
-

症状に応じて、呼吸機能、呼吸抵抗、呼気NOなどの検査を受ける。呼吸機能の程度や気道の炎症、アレルギー反応が調べられ、喘息やCOPDかどうか、または合併の有無が評価される。いずれの検査も時間は5~15分程度。マウスピースをくわえて息を吸ったり吐いたり、深呼吸したりするだけなので、高齢者も、子どもも6歳以上なら大きな負担もなく受けられる。
- 4必要に応じてほかの検査も受ける
-

咳・痰が3週間ほど長引いている場合や、感染症、肺炎、肺がんが疑われる場合などはレントゲン検査も合わせて受ける。アレルギー性の喘息が疑われる場合、指先採血によるアレルギー検査も受けられる。ほかに、腕から採血する血液検査、尿検査が必要なこともある。これらの検査結果と生活環境、症状を照らし合わせ、医師が総合的に診断していく。肺がんや間質性肺炎の疑いがあり、CTでの精密検査が必要な場合は病院に紹介する。
- 5診察室で検査結果を聞き、治療を始める
-
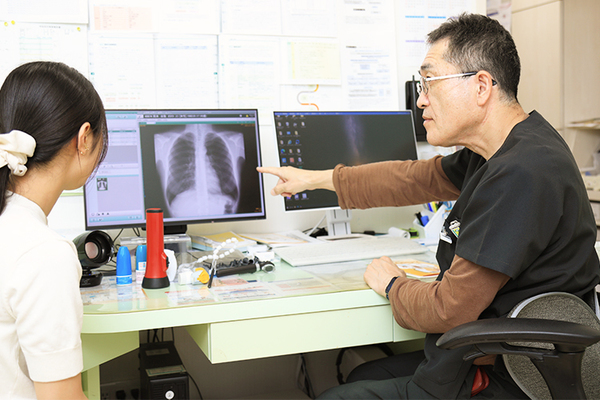
検査結果の説明と治療方法について話を聞く。例えば気道炎症があれば「トンネルの中で火事が起こっている状態なので毎日消火していきましょう」というように、現状の問題と薬がなぜ必要か、それによってどういう変化が見込めるか、資料を用いて説明され、炎症を鎮める吸入薬や飲み薬などが処方される。吸入法については医師、看護師から丁寧に指導がある。指示があれば自宅で日記をつけて自身の症状を把握しよう。







