丹羽 明 院長の独自取材記事
にわ医院
(文京区/西日暮里駅)
最終更新日:2024/12/10

文京区千駄木の静かな住宅街にある「にわ医院」は、内科と小児科に加え、眼科も診療するクリニック。田端駅や西日暮里駅、千駄木駅などから徒歩圏にあり、近くの動坂下停留所からは豊富なバス便も利用できる。同院の歴史は長く、丹羽院長の父が20年余り続けていた産婦人科を、消化器内科を専門とする丹羽院長が引き継いだのが1977年のこと。それから50年近く、地域に住む人々の健康を見守り続けてきた。「患者さんが一体何を求めて来院されたのかを大切に、お一人お一人と丁寧に向き合うようにしています」と柔和な表情で語る丹羽明院長。検査の数値を改善することより、患者が元気になることが重要と話し、データに表れない、目に見えない要素も大切にしているという。そんな丹羽院長に、同院の特徴やめざす医療を聞いた。
(取材日2024年7月2日)
歴史ある医院を守りながら、内科・小児科と眼科を診療
長い歴史を持つクリニックなのですね。

約45年前に父が亡くなってからは、昼間は日本医科大学病院に勤務しながら、夜間と土日のみこの場所で私の専門である内科の診療を行ってきました。その後、尊敬する先輩に誘われ、当時設立されたばかりの防衛医科大学校病院第三内科で経験を積み、母校で博士号を取得した1985年から当院での診療に本腰を入れるようになりました。これまで、無理がたたって体を壊したこともありましたが、地域の患者さんやスタッフ、友人などに恵まれ、助けていただきました。内科と小児科を軸に診療してきましたが、近年は眼科診療も提供しています。
眼科を開設されたのはなぜですか?
日比谷で眼科を開業していた義兄が、閉院後も気になる患者さんだけ継続的に診療したいと、当院の診察室で週に2回診療を始めたのがきっかけです。その後、義兄は高齢で引退し、現在は2人の医師に週に2回の診療を交代で担当していただいています。高血圧や糖尿病といった生活習慣病と眼科疾患の関わりは深く、薬によっては眼圧に影響が出てしまうものもあります。また、眼科症状からこうした内科疾患が見つかるケースも少なくありません。眼底変化をきちんと追うことで、糖尿病などの早期発見にもつながります。目の病気はある一定期間を過ぎると治らなくなることもあるので、早めに症状を発見して進行の抑制が見込めるものに対応して差し上げたいと考えています。
どのような患者さんを多く診られていますか。

感染症の諸症状や、生活習慣病の管理で通院される方などさまざまです。土地柄か、受験シーズンになるとお子さんの受診で混み合います。今は夏でもインフルエンザの流行が見られるなど、従来の考え方では感染予防が成り立たなくなるケースも。小児の発熱は検査を基本とし、大人の方もできる限り検査を受けていただくようお勧めしています。新型コロナウイルス感染もまた増えてきていますが、5類感染症移行後は軽く考えていらっしゃる方が多いのは少し気がかりです。ほかには、高齢者の不安に対する相談なども多く受けています。
単に病気を治すだけでない、「人生のお手伝い」が役割
高齢者の不安にはどのように対応されるのですか。

精神や心理の専門家ではありませんから、治療が必要と思われるケースでは何科を受診すべきかの判断をお手伝いする程度です。多くの場合、薬を処方すれば良いという問題ではなく、どうすれば解決できるのかを一緒に考えることが大切。中には話すだけでほとんど解決できるようなこともあるでしょう。近所付き合いや家族の対話の機会が減り、身近に愚痴を言ったり、相談したりできる相手が見つからないという方も多いのです。私はあまり話が上手なほうではなく、時間がかかることもあると思いますが、井戸端会議の延長のようにさまざまなお話を聞くようにしています。実際、長く生きてこられた高齢者なりの人生の知恵は、私たちの生活や仕事に役立つことも多く、いろいろと活用もさせていただいてもいます。
消化器内科のほか、認知症分野でも活躍されているそうですね。
専門は消化器内科で、当院では上部消化管検査や胃のエックス線検査などを行っています。痛みをきっかけに来院する方を検査することが多いですね。今では内視鏡検査は当たり前ですが、私が診察に導入した当時は、文京区では内視鏡検査ができる医院はまだごくわずかで、その当時が懐かしいです(笑)。また、認知症サポート医でもありますので、普段から患者さんと話をする中で認知症の早期発見につなげていければと考えています。すでに発症している方に対しては、神経内科の先生と相談しながらいくつかのメニューを用意し、ご家族と一緒に選んでもらえるようにしています。そのほか地元の幼稚園、保育園の園医も担当しています。
診療の際に心がけていることは何ですか。

その方が一体何をしにここにいらしたのかを大切に、患者さんの話を傾聴するよう心がけています。患者さんの普段の生活を知ることが診断や指導への第一歩です。若い頃は検査の数値にこだわった時期もありましたが、今は検査の数値を良くすることだけではなく、患者さんご自身が良くなることを大切にしているのです。人の健康はすべて数値で測れるものではなく、数値が健康をつくるものでもありません。医師の仕事とは単に病気を治すことではなく、その人なりの「人生のお手伝い」をすることかもしれないと、最近つくづく思うようになったんです。
医師としての勘も大切に、幅広い年齢層に柔軟に対応
小児から高齢者まで幅広い年齢層に接していらっしゃるのですね。

お子さんや子育て世代の親御さんに接する際には、自分の時代とはまったく違うのだということを心して対応しています。子どもたちや子育て家庭を取り巻く環境は随分と変化しており、価値観も大きく変わっていますから。また、ご高齢の方に対しては、それまで歩んで来られた人生を尊重した上で、現在と今後を一緒に考えるように心がけています。何より、世代を問わず患者さんに接する上で最も大切にしているのは、顔色や表情、動きなどから類推される状態。「何かがおかしい!」という内科医としての第六感のようなものは、軽んじることなく大切に診療しています。
プライベートはどのようにお過ごしですか?
もともと中学時代に吹奏楽部でトランペットを吹いていたのですが、医師会でも私が提案して音楽同好会をつくりました。メンバーは当初の6〜7人だったのが今や30人ほどに増え、毎年定期演奏会を開いています。また、医師会の写真部にも属し、年に1〜2回は旅行に出かけて風景写真を撮影しています。待合室に飾った写真は千葉の養老渓谷で撮ったものです。音楽も写真も、一人で好きな時に楽しめるところが良いですね。人に見せるため、聴かせるためではなく、純粋に自分自身が楽しむために続けています。
今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。
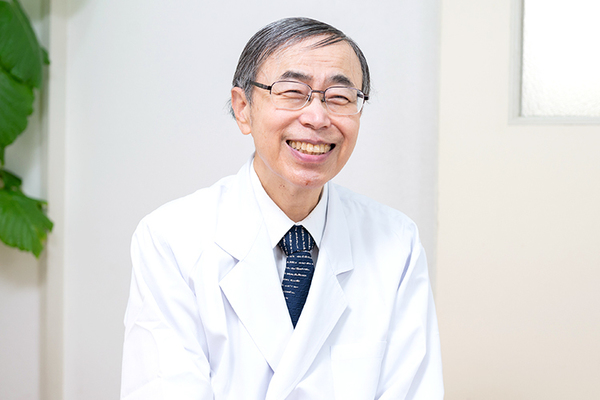
今やっていることを今後も続けて、そこから得られた経験をさらにより良い診療へと還元していければと思っています。皆さんにお伝えしたいのは、家族間など人と人とのつながりの大切さを、今一度考えてほしいということです。若年世代は忙しく、家族との時間を取ることが難しいというのも理解できますが、いざという時に「知らなかった」「わからない」では困ります。短時間でも時間をとって、面倒でも顔を合わせて言葉を交わすことを意識していただくと良いのではないでしょうか。私個人の考えではありますが、面倒から生まれる価値もあると思うのです。






