木本 高志 院長の独自取材記事
きもと眼科
(西宮市/甲子園駅)
最終更新日:2026/01/21
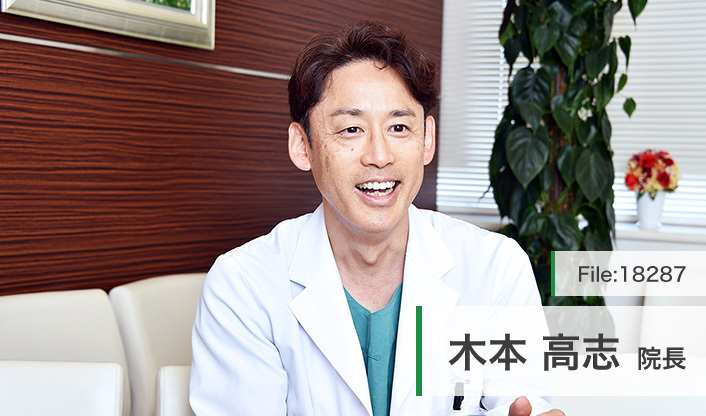
阪神本線甲子園駅から徒歩約6分、阪神甲子園球場近くのビル3階に「医療法人社団 きもと眼科」がある。木本高志院長は関西医科大学を卒業後、関西医科大学眼科学教室に入局。同大学大学院で博士号を取得後、南カリフォルニア大学の研究所において、失明に至ることもある難治療疾患で目の中に炎症を起こす“ぶどう膜炎”の研究に2年間従事。帰国後は関西医科大学附属病院および大阪府済生会野江病院に勤務の後、2014年に同院を開院。専門の網膜硝子体疾患、ぶどう膜炎、黄斑疾患をはじめ、白内障、緑内障、近視、斜視、眼鏡やコンタクトレンズの処方まで、患者の健康を最優先に考え、心に優しく寄り添う診療を心がける。外来診療だけでなく現在も大学で後進指導を行い、多忙な日々を送る木本院長に話を聞いた。
(取材日2019年9月5日)
大学病院と同等の医療をクリニックで可能に
まず、こちらで開院した経緯からお聞かせください。

関西医科大学を卒業後、大学病院や基幹病院で臨床と基礎研究を行い、忙しい毎日を送っていましたが、50歳を迎えた頃、将来、親の介護が必要になった状況を考えると、ずっと勤務医を続けていくのは難しいのではないかと考えるようになりました。そんな時に、研修医時代から親交のあった医師から、既存のクリニックを紹介されました。西宮は住みやすく、人気が高いエリアですし、せっかくのご縁を大切にしたいと私が改めて院長として開設しました。
診療の内容や方針、患者さんの層などに特徴があれば教えてください。
大学病院や基幹病院と同等の医療をクリニックで受けられるように取り組んでいる点が当院の特徴ではないでしょうか。大学病院の外来は1日がかりになってしまうことが多いのですが、当院はそこまでお待ちいただくことはないと思います。一般的に眼科はご高齢の患者さんが多いのですが、西宮という土地柄のせいか、ファミリー層も増えているように感じます。また、当院近くの小学校や中学校の学校医も担当しているので、学生の患者さんも少なくありません。全体的に各年代層の方がバランス良くいらっしゃいますね。近くにお住まいの方が中心ですが、セカンドオピニオンや日帰り手術のために他府県から来られる方もいらっしゃいます。
専門的な外来にも特徴があるように感じました。

そうですね。網膜硝子体、ぶどう膜炎、加齢黄斑変性の外来は私の専門です。中でもぶどう膜炎を専門にしている開業医の先生は少ないですね。網膜硝子体疾患の日帰り手術を行っているクリニックは白内障手術に比べて少ないと思います。当院では硝子体手術に対応するため、常に新しい機器を導入するようにしています。また、硝子体手術を修得するには、その適応となる症例が多い病院で指導を受け、ある程度の経験が必要になります。私は関西医科大学で病棟医長などを、大阪府済生会野江病院では眼科部長を務め、後進の指導も行いながら多くの経験を得ることができたので、その経験を生かしたく当院で行っています。入院施設はないので、あくまで日帰りで可能なケースに限られます。入院が必要な場合は、患者さんの希望をお聞きしながら、適切と思われる病院を紹介していますのでご安心ください。
患者の意思に寄り添うことが診療のモットー
医療機器などにもこだわりがおありなのですね。

技術があっても、設備や機械がなければ治療はできませんから、可能な限りそろえるようにしています。直近では、硝子体手術の新しい機械を導入しました。眼科の治療機器は道具はどんどん進化しています。新しい機械は目の中に挿入する器具が針のように細いのに安定した操作が可能となりました。そのため、より傷口の小さい、低侵襲な手術が図れるようになっています。高価な機器であり、クリニックでは導入に躊躇するレベルかもしれませんが、私としてはそこで諦めたくはありませんでした。もちろん経済的な負担もありますが、大学病院での経験から、先進的な設備機器の重要性はわかっているつもりです。手術に限らず、検査機器の画像にしても鮮明さが診断に影響することもあります。そのため基幹病院で実施しているような精密検査を、ここでも行いたいと思っているのです。
患者さんと接する上で心がけていることなどはありますか?
例えば網膜剥離の手術をしても、再剥離してまた手術をしなければいけない場合もあります。それでも諦めず頑張って治そうと努力されている患者さんと接すると、自分ももっと精進して、しっかりレベルを上げた治療をしなければいけないなと、改めて思わされます。また、患者さんとの信頼関係も不可欠なので、納得していただけるような、丁寧な説明を心がけています。失明を防ぎ生活の質を向上させる目的で行う手術は、われわれ眼科医師にとって重要な仕事です。とはいえ、何が何でもすぐ手術しましょう、と強引にお勧めすることはありません。最初から手術ありきで進めるのではなく、あくまで患者さんの意思に寄り添うことをモットーにしています。ただし緊急性が高い症例の場合は別です。早期の発見と治療が重要な場合もあるので、常に小さな異変でも見逃さないように気をつけています。
スタッフさんがたくさんいらっしゃる印象を受けました。
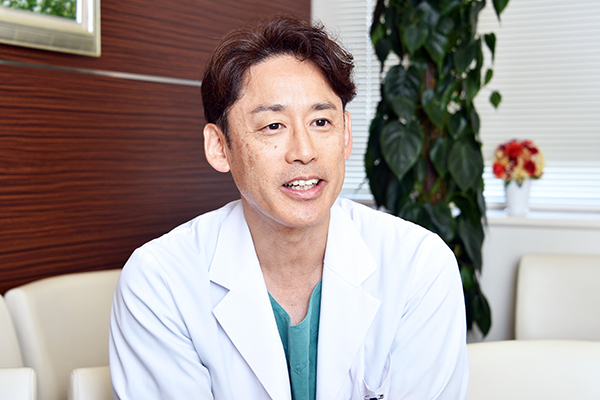
現在は私の他に非常勤のドクターが4人と、看護師2人、視能訓練士1人、事務員、検査補助スタッフが4人います。非常勤のドクターは関西医科大学眼科医局から派遣してもらっています。スタッフには、常に患者さんに寄り添うように伝えていますね。目がよく見えないという患者さんが多いわけですから、院内を移動する際にも注意を払うなど、きめ細かな対応をするよう伝えています。また、「だらだらせずに時間内に仕事を終わらそう」ということはよく言っていますね。ですから、おそらく自分が一番遅く来て一番早く帰っています(笑)。
医学の基礎を学ぶことで臨床の奥が深まる
医師をめざしたきっかけと眼科を選んだ理由をお聞かせください。

祖父が小児科の開業医、父は病理学の教授でがんの基礎研究をしていました。そういった環境のもとで、私も自然に医師をめざすようになりました。眼科を選んだ理由は、恩師である故・宇山昌延教授の影響に尽きます。宇山教授は、網膜疾患の分野において世界で活躍されている方でした。また、欧米では失明原因の第1位である加齢黄斑変性という病気に精通しておられました。宇山教授と出会えたことは、私の人生において最も幸運な出来事だったといえるでしょう。
米国の研究所に行かれたときの経緯を教えてください。
宇山教授は、海外でも多くの先生方と親交を持っていました。その中に、ロサンゼルスにある南カリフォルニア大学ドヘニー眼研究所で眼病理学の研究を行い世界で活躍されている、Narsing.A Rao(ラオ)教授がいらっしゃいました。その研究所で、ぶどう膜炎という免疫に関した目の病気を勉強してこいと言われまして。この病気のエキスパートである、ラオ教授の指導のもと、研究医員として2年間研究してきました。結果がすべての実力主義社会で、教授もなかなか厳しい方だったこともあり、仕事は大変でしたが、そのおかげで根性も鍛えられ、良い体験ができましたね。
休日は何をして過ごしていますか?

日曜日はゴルフですね。といっても毎週行けるわけでもなく、なかなかなうまくならないので悩んでいるのですが(笑)。普段ずっと暗い部屋で診察している反動から、思いきり日光を浴びたくなるんです。また顕微鏡をずっとのぞいていると肩が凝ってくるので、体を動かしたくなります。そういった面でゴルフは、気分転換にもなるし、体にも良いんです。ときには昼の休憩に打ちっ放しに行くこともあります。肩を回すだけでも体がほぐれてリフレッシュできますね。
最後に、今後の展望と読者へのメッセージをお聞かせください。
大学病院の眼科がそのまま地域のクリニックになったというイメージで、現在の医療の質を保ちながら、地域に貢献を続けていきたいですね。20年以上大学と基幹病院に在籍し、臨床と基礎研究の両方を並行して続けてきたことは、自分にとって大きな強みです。もちろん臨床は大事ですが、基礎を学ぶことで臨床の奥が深まります。読者の方へのメッセージとしては、とにかく「見え方がおかしいな?」と感じたら、気軽にいらしてほしいですね。異常があっても両目では気がつきにくいので、片目ずつ見て、ものがゆがんでいるとか視野がかすむとか、気になる症状が続くときは、ぜひ一度ご相談ください。






