三輪田 俊介 院長、三輪田 博介 先生の独自取材記事
Family Clinic みわた小児科
(名古屋市西区/浅間町駅)
最終更新日:2025/09/16

名古屋城から西、下町情緒が漂う住宅街にある「Family Clinic みわた小児科」は、半世紀以上にわたり地域の健康を支えてきた小児科クリニックだ。2020年の改築で装いも新たとなった同院で診療を行うのは、2024年10月から3代目院長を務める三輪田俊介先生と、父親の三輪田博介(ひろゆき)先生。俊介院長は名古屋大学大学院にて小児の白血病の研究で医学博士号を取得、博介先生は救急医療や小児科全般の研鑽を積み、ウイルス感染症の研究で医学博士号を取得している。地域の子どもたちの成長を見守る2人の気さくな人柄が印象的なクリニックだ。親子二人三脚で励む2人に、小児医療への思いを語ってもらった。
(取材日2025年6月19日)
結果が早く出せる早期の検査で、診断の質を上げたい
博介先生は2代目、俊介先生は3代目の院長だそうですね。

【博介先生】僕が小児科医師になったのは、亡くなった父のような医師になりたいと思ったからです。ここは父が1964年に開業した小児科の医院で、幼い頃は父が子どもたちと仲良くする姿をよく目にしていたこともあり、僕はずっと父を目標にしてきました。今でも困った時は「親父ならどうするだろう」と考えるんです。父の患者さんが親になって子どもを連れて来てくれることもありますよ。すごく慕われていたんですね。
【俊介院長】父が祖父を目標としたように、僕も父の姿に憧れて小児科の医師になるのを決めました。2025年の10月に父から院長職を継承し、現在は親子で診療にあたっています。父は小児科医、そして町医者としての大先輩。診療を通じてたくさん学ばせてもらっています。
2020年にクリニックを改築されましたが、院内づくりでこだわった点を教えてください。
【俊介院長】当院に集うすべての人にとっての「居心地の良さ」と感染対策を追求しました。1階中央には大型の空気清浄機を設置し、徹底した除菌・加湿を心がけています。待合スペースには、絵本をたくさん用意したり吸入時におもちゃで遊べるようにしたりと、お子さんが退屈しないよう工夫しました。また、3つの待合室と3つの診察室、7つの隔離室で、感染者や新生児をしっかり分けて診療できるようにしています。感染症が疑われる患者さんとそうではない患者さんが別エリアで待機でき、1階の仕切りのあるベンチではお隣同士で顔を見合わせることもありません。予防接種や健診で来院した患者さんは2階でお待ちいただけます。
俊介院長が院長に就任されてから、検査体制も充実させたそうですね。
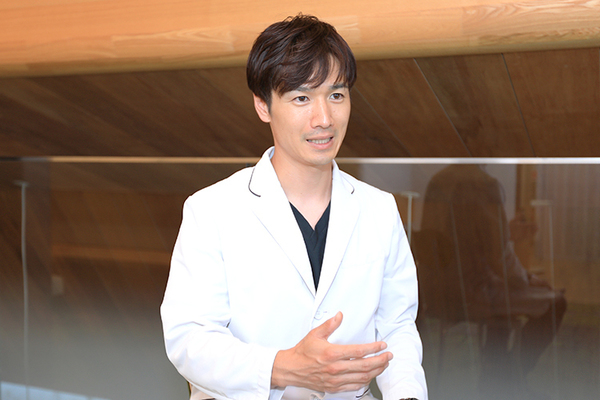
【俊介院長】患者さんが知りたいことを積極的に検査することで、ステップアップした治療に進めるので、検査は積極的に行うようにしています。親御さんへの安心のためにも、そして診断の質を高めるためにも、早い段階での検査はお勧め。現代医学は情報戦ですから、病気との戦いという意味では、得られる情報は得て診察や問診以外の情報を固めながら診ていきたいと考えています。PCR検査や抗原検査に関しては発熱2日目以内、血液検査に関しては発熱3日目には検査を行うようにしています。15種類の感染症の判別が可能なPCR検査、41項目のアレルギー検査も導入しました。エコー検査もおなかの病気をその場で検査できますし、体への負担もないので、積極的に行っています。また、ウェブ問診も導入しました。診察時に慌てることなく、ご自宅でゆっくりと聞きたいことや伝えたいことを記入できます。
子どもとその家族が安心できる医療を提供
医院名の「ファミリークリニック」に込めた思いをお聞かせください。

【博介先生】2つの意味を込めています。1つは、子どもが風邪をひけば親にもうつる可能性があるので、お母さんやお父さんも一緒に診ますよということ。もう1つは、その家族に合った治療を考えるということ。病気と闘う子どもがいて、家族も一緒に闘っている。そこに僕らが投薬やアドバイスなどのちょっとした武器を携えて加わって一緒に闘う。医院名はそんな当院の診療の在り方も示しています。子育ての悩みもよく聞いています。特に心配なければそのことをお伝えするようにしていますし、医師の返事を聞いて、気が楽になってもらえたらと。反対に子どもの状態に気づいていなさそうなら、一声かけることも忘れません。スタッフに「先生、よろず相談所になっていますね」と言われます。
ご家族に真剣に向き合っていらっしゃるのですね。
【博介先生】頑張り屋の親御さんは、自分のことは後回しにして我慢してしまうんですよね。ですので、例えばお子さんの診療時に親御さんが診察を希望されたら、いつも以上に診療に気合いを入れます。よくよく我慢された上での相談でしょうからね。それと、僕は24時間365日、いつでも患者さんからの連絡に応じています。その場ですぐの診察は難しくても、アドバイスぐらいはできるので。実は僕自身、家族の大病から患者の家族という立場を経験したことがあり、患者さんの不安、心配な気持ちが本当に身にしみました。だから、相談があれば「大丈夫」「任せてください」と、臆せず言います。
病児・病後児童保育室についても教えてください。

【博介先生】保育室は、名古屋市病児・病後児デイケア事業の委託を受け、2015年から取り組み始めました。実は病児保育を始めるか迷っていた時、背中を押してくれたのが俊介先生でした。病児保育をスタートしてから、皆さんから思ってもみなかった感謝をされて、その時初めて「ああ、父を超えられたかな」と思えましたね。
2人の医師が力を合わせ、地域に貢献していく
小児科の診療において、何が大切とお考えですか?

【俊介院長】お子さんの普段の様子は医師にとって大事な情報源ですので、親御さんにも「クリニックは必ずしもすごく体調が悪くなったときに受診する場所ではない」とお伝えしたいですね。気になる様子があるとか、些細なケガでも気軽に足を運んでください。目の前のお子さんと親御さんだけでなく、家族みんなが安心できる医療をめざしていますから、わかりやすい説明は常に意識しています。
【博介先生】お子さんの病気のほとんどは自然と快方に向かいます。だからこそ重症を見逃さないのが重要で、100%見逃してはいけないという思いでいます。重篤な病気が隠れていないか、死の危険性はないか、細心の注意を払う。それが役目だと思っていますし、僕は危険感知のアンテナが抜群に働くんです。普段のその子やお母さんを知っているからこそ、異変に気づけるんでしょうね。
吃音症の相談や治療もされているそうですね。
【俊介院長】名古屋市内には吃音に対応しているクリニックが少なく、私も以前から患者さんの紹介先に困っていました。幸い、当院の2階にはスペースも空いていたので、落ち着いた空間でゆっくりと吃音トレーニングができたらいいなと思い、4月から専門の外来を開設しています。2、3歳のお子さんで100人中、8人くらいは吃音を経験しますが、中には小学校になっても吃音が残ってしまうお子さんが100人中3人ぐらいだといわれています。少しでも気になる方は気軽にご相談ください。きちんと診断し、治療が必要なお子さんには言語聴覚士と一緒にトレーニングをしていただきます。
赤ちゃんの頭の形を矯正するためのヘルメット治療も行う予定だそうですね。

【俊介院長】以前、小児脳外科医と協力して赤ちゃんの頭を専門とする外来での診療とヘルメット治療を行った経験を生かして、自院でもエックス線画像や3Dスキャンなどの検査体制を整え、今年の夏からスタートします。発達がのんびりだったり、向き癖が強かったりする赤ちゃんは、同じ方向を向いて寝ている時間が長く、頭の形が絶壁になったり斜めに変形したりします。それがある程度のレベルを超えると、頭の形のゆがみとして残ってしまうため、早期に見つけて対処することが大事。また、骨同士がくっついてしまう病気によって変形していることもあります。ゆがみが残ったまま進行していないか、病気が隠れていないかを判断し、治療が必要な赤ちゃんには専用のヘルメットを使った矯正治療を行う予定です。今後も世の中で不足している医療を提供していきたいですね。






