気づかれにくい心房細動は
早期発見が予後改善の鍵
虎溪医院
(草加市/獨協大学前〈草加松原〉駅)
最終更新日:2025/08/27


- 保険診療
心房細動とは、心房に流れる電気信号が乱れる不整脈の一つで、加齢や生活習慣などが原因となる。心房細動が起こると脈拍が不規則になり、進行すると心不全を引き起こすほか、心房内に血栓ができると脳梗塞の原因にもなる。そのため早期発見が大切なのだが、心房に異常が起こっていても、心室が拍動するので、約半数の人は無症状のまま気づかないともいわれる。「虎溪医院」の虎溪則孝(とらたに・のりたか)院長は、循環器疾患の専門家として大学病院で不整脈治療の研鑽を積んできた。現在も大学病院で週1回ペースメーカーの外来を担当し、病診連携を意識した精密な医療を提供している。そんな虎溪院長に、心房細動の種類や検査・治療法などについて詳しく聞いた。
(取材日2025年8月5日)
目次
循環器疾患の専門家による、一人ひとりに合った適切な検査と治療で、予後の改善をめざす
- Q心房細動には、どのような種類がありますか?
-
A
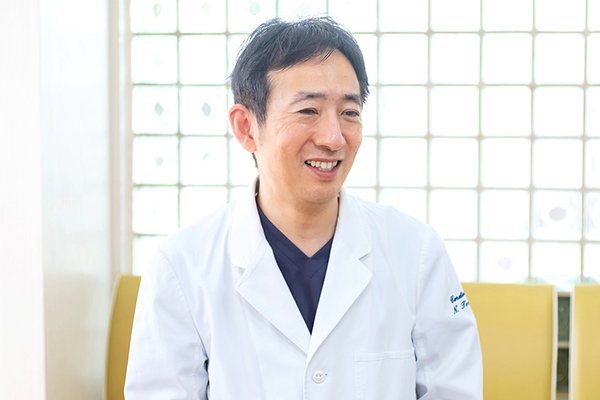
▲日本循環器学会循環器専門医の資格を持つ虎溪院長
心房細動には3つの種類があります。7日以内に自然に止まる発作性心房細動、それ以上持続する持続性心房細動、1年以上持続する長期持続性心房細動です。長くなるほど自然には止まりづらく、洞調律、つまり正常な心拍に戻すために薬や電気的除細動が必要です。また、治療をしても洞調律に戻せない状態を永続性心房細動といいます。発作性心房細動が何年も続いて持続性へと進行するものもあれば、初めて起こった心房細動が自然に止まらず持続性になってしまうものもあります。さらに、手術した時にはすでに永続性心房細動になっている場合もあります。
- Q心房細動の自覚症状について教えてください。
-
A

▲自己判断せず、専門的な知識を持つ医師に相談することが大切
心房細動になると、脈と脈の間隔がバラバラになります。特に発作性心房細動では、正常な心拍と比較して、急に脈拍が速くなることが多く、心臓がドキドキしたり、息切れしたり、胸に違和感を覚えたりするケースがあります。発作性心房細動でも症状がないことがありますが、心房細動の持続期間が長くなると症状はますます感じづらくなり、長期持続性や永続性心房細動では症状を感じることがほとんどありません。しかし、心房細動が長時間持続することで心臓全体の機能が落ち、慢性心不全の状態になると、息切れや体のむくみなどの症状が出やすくなります。
- Q心房細動には、どのような検査がありますか?
-
A

▲エコー検査をはじめ、さまざまな検査に対応する
心房細動の診断は、異常があるときの心電図を記録して行います。持続性や永続性の場合、健診の際の心電図検査で見つかりますが、発作性の場合、受診時には心房細動が止まっていることが多いため、24時間装着するホルター心電図検査や、日常生活で異常が起きたときに素早く計測する携帯型心電計(イベントレコーダー)を用います。心房細動と診断されたら、心エコー検査を実施します。心房細動に起因する心臓の病気がないか調べ、心臓の機能や左心房の大きさを測定します。また、脳梗塞の原因になりそうな血栓が心臓内に付着していないかも検査します。
- Q心房細動の治療法を教えてください。
-
A

▲患者一人ひとりに合わせた治療法を提案
まず脳梗塞を予防するため、75歳以上・高血圧症・糖尿病・心不全がある人・脳梗塞の既往歴のある人は、抗凝固薬の服用を検討します。心房細動を正常な心拍に戻すことをリズムコントロールといい、カテーテルアブレーション、抗不整脈薬、電気ショックなどを組み合わせて治療します。ただし、すべての人に推奨されるわけではなく、「心房のダメージが進行し正常の心拍を維持できそうにない」「予後にあまり影響を与えない」「症状がない」場合などは無理にリズムコントロールを行わない選択をすることもあります。心房細動は、発症してからなるべく早めに治療することが重要で、カテーテルアブレーションは4〜5日の入院で行うことができます。
- Qこちらで受けられる治療について教えてください。
-
A

▲簡単に自宅や外出先で計測できる携帯型心電計とホルター型心電計
当院では心房細動の早期診断のため、通常の心電図検査に加え、24時間計測または7日間連続計測のホルター型心電計や、不整脈の有無を長時間にわたって記録する携帯型心電計による検査、脳梗塞や失神の原因を調べる植え込み型心電計の手術に対応しています。心エコー検査によって心臓の機能を評価し、持続期間、年齢、症状、患者さんの希望などを考慮し、治療方針を決めます。必要に応じて連携先の医療機関に紹介するとともに、手術後のフォローアップや再発の評価、薬の調整・中止の検討にもこまやかに対応しています。私は現在も大学病院で週1回ペースメーカの外来を担当しており、地域の中核病院との病診連携に力を入れているんです。






