石戸谷 淳一 院長の独自取材記事
石戸谷耳鼻咽喉科
(世田谷区/千歳烏山駅)
最終更新日:2025/09/29
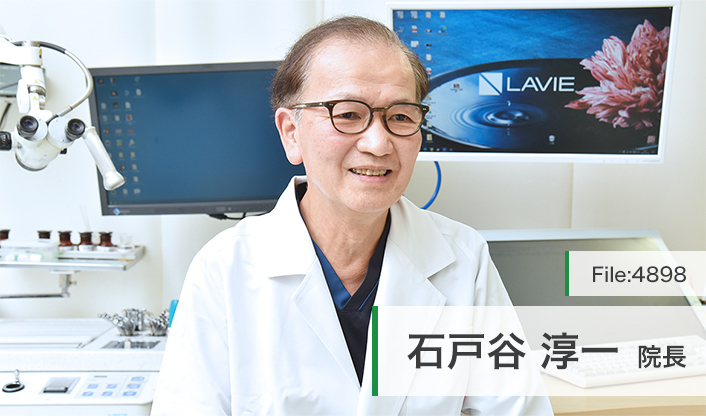
京王線千歳烏山駅前北口から徒歩1分。駅前から続く商店街の中にあるビルの3階が「石戸谷耳鼻咽喉科」だ。1階からエレベーターで上がれる院内はバリアフリーで、広い待合室にテレビやキッズスペースも用意されるなど、誰でも温かく迎え入れる体制が整えられている。院長である石戸谷淳一先生は、国立病院の医長(診療科長)や大学病院の教授を歴任してきた実力派のベテラン医師。これまで培ってきた豊富な知識と経験を生かした診療を行い、局所麻酔による日帰り手術にも取り組んでいる。「当院で最初から最後まで責任を持って治療を行い、患者さんの満足が得られるようにしたい」と話す石戸谷院長に、これまでの経験や同院のことについて話を聞いた。
(取材日2018年8月30日/情報更新日2024年12月19日)
専門性の高い治療と手術の経験を生かした診療
患者さんの主訴や、患者層について教えてください。

副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、中耳炎、咽頭炎、風邪をひいた後に咳が続くなど、子どもから高齢者までの耳、鼻、喉のことなら何でも診察しています。中でも、私は鼻・副鼻腔疾患の研究を長らくしていたので、特に副鼻腔炎のご相談が多く、インターネットで探して遠方からおいでになる方も数多くいらっしゃいます。当院では、副鼻腔炎や鼻中隔弯曲症、鼓膜の穴を閉鎖する手術などを局所麻酔の日帰り手術を行っているので、それらを希望して来る患者さんも少なくなく、これまで約1200例(2015年5月~2024年9月)の手術をしています。年齢層は幅広く、20歳代~50歳代の方が多いですね。病状が長く続きなかなか改善しないという方や、何か気になる症状がある場合には、まずはご相談いただければと思います。
手術は数多くされているのですか?
耳鼻咽喉科は頭頸部外科と言われ手術で治療をする診療科ですから、当院でも可能な範囲で手術治療を取り入れています。今は週に2日の午前中を手術枠にして、1日2例ずつの手術をしていますが、数ヵ月ほどお待ちいただいている状況で申し訳なく思っています。長年の鼻詰まりや匂いがわからない、鼻水が喉に垂れて咳や痰がいつも出ている、鼻詰まりで夜も眠れなかったというような症状で悩んでいた方が鼻・副鼻腔の手術で喜んでくださったらうれしいですね。また、数多くの患者さんを診ていると、いろいろな発見がありますし、患者さんからも多くを教えられます。自分としても成長するし、とても興味深いですね。
手術に力を入れているのはどのような理由からでしょうか?

大学病院などであれば全身麻酔で1週間の入院で行うような副鼻腔炎や鼻中隔弯曲症などの手術を、当院では局所麻酔で行っています。局所麻酔なので入院は不要ですが、全身麻酔の手術と同じことをするために手術当日は痛みや出血がありますが、翌日にはガーゼを抜くので圧迫感や痛みは大分楽になります。局所麻酔による手術のメリットは、日帰りで手術ができることではないでしょうか。例えば、小さいお子さんがいて保育園の送り迎えをしなければならないお母さん、リモートで仕事をしている方などにニーズが高いです。また、局所麻酔なのでリラックスして手術を受けていただけるように、手術中には患者さんと雑談もしています。手術を治療の一つの手段として、今後も患者さんにとって適切な治療を提供していければと思っています。
患者への説明を重視し、一度の診察で最善を尽くしたい
診療で心がけていることを教えてください。

慢性副鼻腔炎といっても症状はさまざまなため、患者さんによって治療法が異なります。咽頭炎も重症度と腫れている部位によって、適した薬は異なります。つまり、同じ病名でもさまざまな病態があるため、個々の患者さんの病態をしっかりと診断し、一人ひとりに合った治療をすることが大切です。また、ネブライザーのためだけに通院してもらう、毎週のように何度も通院をして治療をするといったことは基本的に行っていません。今は良い薬がありますから、薬を少し多めに処方して、それで治らなければまた来てくださいというスタンスです。患者さんも何度も通院するのは大変ですし、できるだけ1回の診察で治したいという気持ちで行っています。
「通院回数を少なくする」ということを大切にされているんですね。
この方針のためか頻回に通院する患者さんは多くなく、開院して10年以上が経過していますが、今でも初めて受診される方が少なくありません。当院の診療は予約制にしていますが、予約開始後すぐに予約が埋まってしまう日もあり、初めて受診する方は予約が取りにくくなっています。そこで、ホームページ上で予約の取り方のコツをまとめているので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。現在、外来診療を1日40人までと制限したり、手術の予約も数ヵ月先になってしまったりと申し訳ない気持ちですが、ご理解いただけるとうれしいです。病院勤務から開業して、自分の医師人生の中で患者さんとの距離が一番近くて、患者さんのつらさを具体的に聞けるし、笑顔もいっぱいもらえているように感じます。これからも患者さんの笑顔をたくさん見られるような診療を続けていきたいですね。
先生が医師をめざしたきっかけについて教えてください。

私は台東区上野で生まれ育ち、子どもの頃は上野公園を自分の庭で遊ぶかのように駆け回っていました。小学生の頃は理科が好きで、「記憶のメカニズムはどのようになっているのか」や「なぜ手が動くのか」といったことに興味を持っていました。また、病院へ連れて行かれた時などは、母親がお医者さんを尊敬している姿をいつも見ていました。そんなことも影響したのか、中学生の頃には、将来は医師になりたいと思っていました。大学の医学部に入って解剖学や生理学を学んだ時、自分が子どもの頃に疑問に思っていた答えを知ることができたのはうれしかったですね。
患者に満足してもらえる質の高い医療の提供をめざす
その後は、どのような道を歩んだのですか?

医学部卒業後は、国立国際医療センター(現・国立国際医療研究センター)耳鼻咽喉科の研修医になり、3年目には3ヵ月間をカンボジア難民医療に関わりました。その後は、東京大学医学部の生化学研究室で基礎医学の研究をして博士号をいただいたり、アメリカの国立衛生研究所(NIH)に2年半留学して発がんのメカニズムを研究したりしました。帰国してからは国立国際医療センターで臨床や研究に取り組み、40歳で耳鼻咽喉科医長(診療科長)になりました。そして、横浜市立大学からお誘いをいただき、同大学附属市民総合医療センターの耳鼻咽喉科教授になり、副病院長も4年間務めました。しかし、いつかは地元で地域医療に貢献したいという思いがあり、10年ほど前に自宅から近い千歳烏山で開業しました。難民医療やアメリカ留学、分子生物学の研究など、普通ではなかなかできないことを経験できたことが私の財産になっています。
お休みの日など、どのようにリフレッシュしていますか?
休日はよくウォーキングをしています。多摩地域のほうにハイキングに行ったり都内で暗渠(あんきょ)めぐりをしたりしています。暗渠とは昔の川や水路の名残りです。そこを歩くことで江戸時代の頃の生活に思いを馳せたり、すてきなお店を見つけたりするのが楽しいです。20kmくらい歩くこともあります。音楽を聴いたり絵を見たりするのも好きで、オペラ鑑賞をしたり、美術館巡りもしています。同じ時代に生きた作曲家と画家のそれぞれの作品を照らし合わせて、見たり聴いたりするのも面白いですね。
今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

とにかく「鼻詰まりは治療できる」ということをお伝えしたいですね。鼻の内部構造や体質は人によって違いますから、その人に合わせた適切な治療をすることで鼻詰まりは必ず改善が見込めると考えています。例えば、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎や鼻中隔弯曲症による鼻詰まりは薬や手術による治療が可能です。当院はCT検査とファイバースコープを用いて、初診の時点で患者さんそれぞれの鼻・副鼻腔の状態を把握し、適切な治療や対応についてお話しできると思います。何度も通う必要がありませんので、悩む前にまず受診していただければと思います。患者さんに満足していただけるよう、質の高い医療の提供をめざしていきますので、耳や鼻、喉の悩みであれば、小さなお子さんから高齢者まで、どなたでも気軽にご相談ください。






