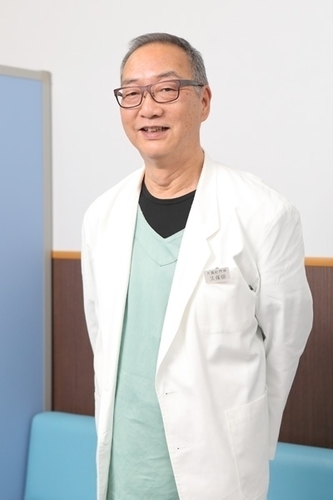炭酸ガスで負担減、迅速に終了
大腸内視鏡検査でがんの早期発見を
西新井大腸肛門科
(足立区/西新井駅)
最終更新日:2026/01/21


- 保険診療
「お尻にまつわる症状は話しづらい。ましてや、お尻から内視鏡カメラを挿入するなんて……」と思う人は多いだろう。そのため症状が出ても、「痔や便秘くらいは大丈夫」と思い込もうとしたり、受診を後回しにしたりしてしまう。しかし、大腸がんは男女ともにがん死亡原因の上位で、とりわけ女性ではトップの病気。今回は、大腸がんの早期発見に役立つ大腸内視鏡検査を年間3800件受け入れ可能な「西新井大腸肛門科」を取材した。大腸内視鏡検査にかかる時間は約20分ほどで、炭酸ガスを用いて患者の負担がなるべく少なくなるように検査を行っているという。イメージと違う検査の中身が見える実際の流れをレポートする。
(取材日2015年3月3日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Q大腸内視鏡検査では、どんな病気がわかりますか?
-
A
大腸内視鏡検査の最大の目的は、がんの発見です。早期の発見により内視鏡にて切除が可能です。小さいポリープが見つかった場合は検査中に切除も可能です。そのほか憩室症や急性腸炎などがあります。最近増加傾向にある炎症性腸疾患の潰瘍性大腸炎やクローン病は18歳前後で発症しますので若い人でも下痢が続いたり、出血があった場合は要注意です。
- Qおなかの張りを軽減するために、炭酸ガスを使うと聞きました。
-
A
腸内を観察しやすくするため、通常は空気を送り込みますが、当院では「炭酸ガス」を使います。炭酸ガスは、空気の1000倍以上の速さで吸収・排出されるといわれており、検査後の患者さんへの負担が少ないのです。
- Q検査にかかる時間や費用の目安を教えてください。
-
A
内視鏡カメラを入れている時間は10〜20分くらいです。麻酔薬を使用しているのでうとうとしている間に終わります。その後、体を回復させるために20〜30分ほど休んでから、結果を説明します。検査前の排便の時間を含めても、半日ほどです。検査には保険が適用されます。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1事前に検査の説明を受ける
-

検査前に服用する下剤、検査中に使用する鎮静剤や鎮痛剤、検査中のまれなリスクなどに関する話を聞く。また、検査中にポリープを切除した場合、大きさや数によっては入院が必要。よく確認し、疑問や不安を解消しておく。先生がわかりやすく、ユーモアを交えて説明してくれるので緊張もほどけるだろう。
- 2自宅、または当日に院内で下剤を服用し、腸内を空に
-

正確に観察するため、下剤で腸内をきれいにする。基本は自宅で服用するが、検査の数時間前に来院し、院内で服用することもできる。また、前日は食事制限が必要で自費となるが、希望者には検査食を用意している。
- 3いよいよ内視鏡検査を開始
-

専用の紙パンツには必要な部分に切り込みが入っているので、着用したまま検査が可能。リラックスと痛み軽減、脱水症状などへの対応を目的に、鎮静剤と鎮痛剤を打ちながら進める。検査中は医師が説明や話をしてくれる。空気の1000倍以上の速さで吸収・排出されるといわれる炭酸ガスを使用するため、検査後の患者への負担が少ないという。
- 4検査後はリカバリースペースでゆっくり休息
-

検査は10〜20分と短く、負担軽減の工夫がされているとはいえ、最長で130cmほどの内視鏡スコープを入れることもある。検査直後にはリカバリースペースで休息を取る。20〜30分ほど横になる人が多いという。ナースコールもあり、看護師も気にかけてくれるので安心だろう。
- 5画像を見ながら、詳しく検査結果を聞く
-

検査結果は、撮影した画像と同院オリジナルの腸内図を使って説明してくれるので、自分の体に照らし合わせて具体的にイメージしながら話を聞くことができる。万が一入院が必要な場合も症例によっては同院で入院も可能だ。