突然の胸の痛みから高血圧の管理まで
循環器疾患の専門家に相談を
江渕クリニック
(練馬区/大泉学園駅)
最終更新日:2025/09/12
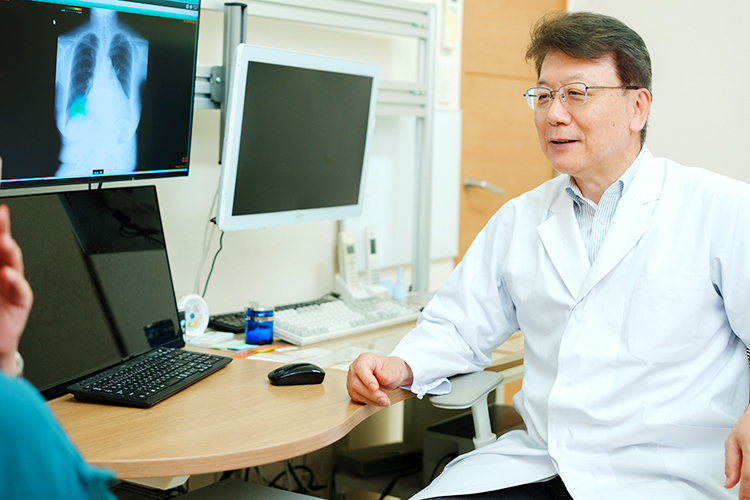
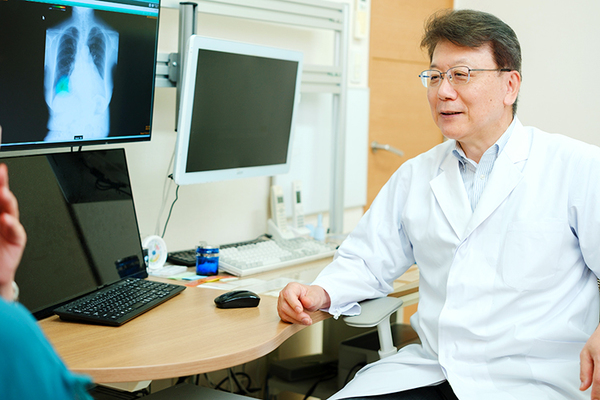
- 保険診療
急に発症し、適切な治療を受けられなければ命に関わることもある心臓病。しかし、必要な時に検査と治療につながれると、その後はこれまでどおりの生活を送ることが望めるのもこの病気の特徴だ。それには違和感があった時すぐに受診し、健康診断で高血圧や糖尿病などを指摘されたら放置しないことが大事だという。「例えば高血圧症は、将来的に心臓の病気を発症するリスクが高いですから、循環器内科であれば、それらを見据えて治療や管理が行えます」と教えてくれたのは、一般内科・循環器内科を診療する「江渕クリニック」の江渕知命院長。日本循環器学会循環器専門医の豊富な知識と経験に加え、地域に根差し、幅広い診療に携わってきた経験を生かして包括的な診療に取り組む。そんな江渕院長に、循環器疾患について詳しく教えてもらった。
(取材日2025年7月10日)
目次
健康診断で高血圧や血糖値の高さなどを指摘されたら循環器内科へ。将来を見据えた治療を提案
- Q胸の痛み、動悸、息切れは循環器疾患と関わりがありますか?
-
A

▲バリアフリー設計で、診療室まで車いすで移動可能
不整脈、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、心不全といった循環器疾患の症状として、胸の痛み、動悸、息切れが現れることがあります。大動脈瘤など血管の病気も、それらの症状が共通しています。他に、手足のむくみの原因に循環器疾患が関わっている場合もあります。心臓の病気はその方によって感じ方が違うことも特徴で、同じ不整脈でも運動ができる方もいれば、つらくて仕方ないという方も。胸のモヤモヤや圧迫感などを感じる方もいます。また、息切れは呼吸器疾患の可能性も考えられますので、検査を行い、適切な治療へとつなげていきます。
- Qどんなときに循環器内科を受診すれば良いのでしょうか。
-
A

▲検査機器も充実している
循環器疾患は自覚症状なく進行して突然発症する場合が多く、その時に適切な治療を受けることが予後に大きく関わってきます。ですので、胸の痛みなどの違和感に気づいたら放置せずに受診することがとても大切です。もう一つ、健康診断で心電図やコレステロール値で引っかかったり、血糖値の高さや高血圧を指摘されたら循環器内科を訪ねてみてください。そういった指摘から考えられる高血圧症や糖尿病、高脂血症は、将来的に不整脈や心筋梗塞、心不全などをはじめとする循環器疾患を発症するリスクが高い病気です。循環器内科であれば、それらの病気も専門としていますので、今後を見据えながら治療・管理することができます。
- Q検査を後回しにすると、どのようなリスクがありますか。
-
A
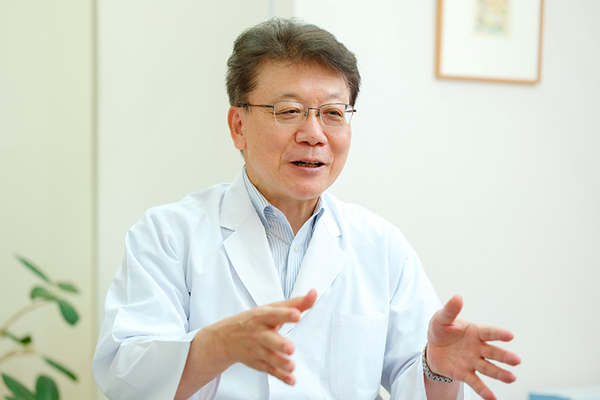
▲長年循環器疾患に向き合ってきた日本循環器学会循環器専門医
循環器疾患の中には必要な時に検査や治療を受けないと後遺症が残ったり、命に関わる病気があります。しかし、検査を受けて適切な治療が行われれば、これまでと変わらない健康な生活を送れることも期待できます。よく早期発見が大切だといわれますが、例えばがんの場合は徐々に進行していくので、早いうちに見つけて対処することで治療予後にも期待が持てます。対して循環器疾患は突然発症した際に、1日2日、1時間2時間といった短時間を乗りきることが重要で、そのために、違和感がある際は早期に検査を受けていただきたいのです。また健康診断で指摘されたときも再検査を受け、治療介入が必要なのかを専門家に判断してもらうことが大切です。
- Q循環器疾患の検査について教えてください。
-
A

▲患者の負担が少なくなるように検査機器も工夫している
心電図や胸部のエックス線検査、心臓のエコー検査を行い、場合によっては血液検査で、心臓や腎臓、肝臓の状況を確認します。頸動脈エコー検査で動脈硬化の進行具合を把握し、脈波で動脈硬化の程度を評価することもあります。ホルター心電図といって、日常生活の中での心臓の動きを確認する検査もあり、こちらは専用装置を24時間胸に貼って検査をするものですが、当院では患者さんの負担が少なくなるよう特に小型のものを用いています。また、胸部エックス線検査機器は、精度の高い診断をめざし、AI機能を搭載したものを導入しました。専門的な検査も組み合わせながら、必要に応じてより専門性の高い医療機関への紹介もしています。
- Qこちらではどのような治療を行っていますか。
-
A

▲専門性の高い循環器診療の提供に努めている
循環器内科を専門としていますが、その1点だけに集中するのではなく、地域に根差すクリニックとして包括的に診ていくことを大事にしています。例えば高血圧の方の血圧の数値を下げることは大事ですが、数値の変化を目的にはせず、あくまで「健康寿命を延ばす」ことを目的とした治療を行っています。同時に日進月歩で進化する薬を正しくご提案できるよう、勉強も欠かせません。それぞれの薬の長所と短所を理解して、適切な処方に努めています。専門性の高い新しい治療における知識も常に更新しながら、地域の方へ還元していきます。






