伊沢 英知 院長の独自取材記事
伊沢眼科
(武蔵野市/吉祥寺駅)
最終更新日:2025/11/06
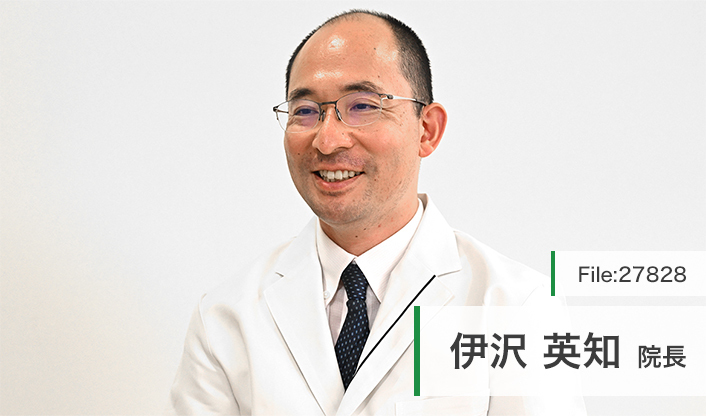
吉祥寺駅から徒歩3分の「伊沢眼科」。伊沢英知(いざわ・ひでとも)先生は前院長であった父から同院を引き継ぎ、2024年7月に院長に就任。大学病院やがんセンターでの勤務経験があり、専門であるぶどう膜炎の外来診療をはじめ、眼科疾患全般に対応してきた。「当院は、コンタクトレンズ会社と提携した眼科ですが、コンタクトレンズに限らず幅広く診療しています」と、わかりやすい説明に加え、患者の年齢や知識の幅に即した接遇を心がけながら診療にあたっているという。そんな伊沢院長に、診療の特徴や今後の展望などについて話を聞いた。
(取材日2024年7月19日/再取材日2025年8月20日)
父から継承、駅からアクセス至便なクリニック
2024年7月に院長に就任されたそうですね。これまでのご経歴と就任の経緯を教えてください。

当院は、父の伊沢保穂前院長が、2010年にこの場所で開業しました。私は父の後を継ぎ、2024年7月に院長に就任しました。それまでは東京大学医学部附属病院や国立がん研究センター中央病院、国際医療福祉大学病院の眼科に勤務していました。勤務医時代は、目の中に炎症を起こす病気の総称であり、比較的希少疾患として知られる、ぶどう膜炎を専門とする診療で経験を積みました。現在も休診日には東京大学医学部附属病院で、ぶどう膜炎の診療を行っています。また国立がん研究センター中央病院では、眼腫瘍そのものや目以外の悪性腫瘍に伴い出現する目の症状、腫瘍に対する治療によって眼部に出現する副作用、移植によるドライアイや網膜症などの治療を行ってきました。血液腫瘍科など他の診療科の先生と連携しながら治療を行うことも多かったですね。国際医療福祉大学病院では一般的な治療が多く、対応できる疾患の幅が広がったと思います。
クリニックを継承され、変わった点や変わらない点についてお聞かせください。
当院はコンタクトレンズ会社と提携する眼科で、コンタクトレンズの処方を目的とする患者さんが多かったのですが、コンタクトレンズの処方に加え、一般診療についてもできるだけ幅広く診療していきたいと考えています。新たに、緑内障治療のSLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)や網膜裂孔に対する網膜光凝固術のためのレーザー機器や、緑内障検査・種々の網膜疾患診断に用いるOCT(光干渉断層計)なども導入し、これまで以上に検査や治療の選択肢も広がりました。今までの経験を生かしていくとともに、患者さんの利便性を向上させ、ご負担を減らし、より多くの方々の助けになれればと思っています。父が担当してきた患者さんはもちろんのこと、新規の患者さんや眼科検診の患者さん、学校健診の患者さんなども広く受け入れています。父が行っていた、第二種運転免許や大型免許の取得に必要不可欠な深視力検査にも引き続き対応します。
お父さんはどのような存在でいらしたのでしょうか?
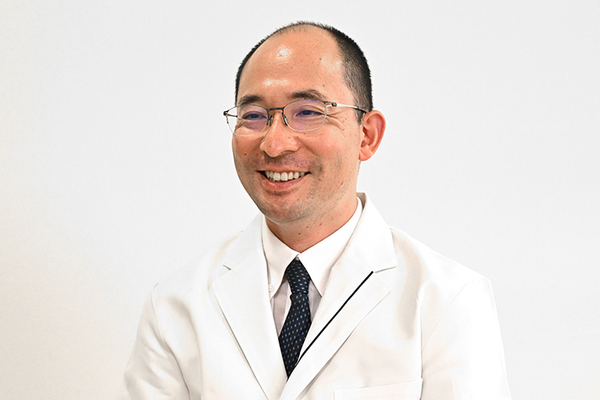
父は、当院を開く前に三鷹市で開業し、地域に根差した眼科診療を38年間行ってきました。幼い頃、父が患者さんを診療している姿を見て憧れのような気持ちを抱き、自分も将来は医師になりたいと思いました。家では厳しかった父ですが、患者さんやクリニックで働くスタッフに対しては親身で優しく、当院の患者さんの中には父が三鷹で開業していた頃から通ってくださっている方もいらっしゃいます。当院の院長になり、父がどのように患者さんとの信頼関係を築いてきたのかを改めて感じることができ、父の偉大さを感じています。ちなみに父の専門もぶどう膜炎でした。国立がん研究センター中央病院に勤務していた頃、父も入局していた東京大学医学部附属病院に非常勤でお手伝いに行っていたのですが、その時に勧められたのが、ぶどう膜炎だったのです。その時の経験はとても勉強になりましたし、運命的なものを感じますね。
患者の年齢や知識の幅に即した対応を
診療の際に心がけていることを教えてください。

患者さんは目のことで不安があっていらっしゃっているので、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。また、患者さんの年齢もさまざまですし、インターネットでいろいろ下調べをしてくる方もいれば、そうでない方もいて、知識の幅もさまざまです。ご高齢で耳が遠い方には目で見える資料をお渡しして説明したり、その方が知りたいことや不安に思っていることに即したアドバイスをしたりするなど、一人ひとりの患者さんに適した対応を心がけています。当院ではさまざまな検査に対応していますが、例えば眼圧検査をする時、患者さんが緊張してしまうと眼圧が上がってしまって適切な計測ができないこともあります。患者さんにリラックスして検査を受けていただくような雰囲気づくりも心がけています。
深視力検査以外には、どのような検査を行っているのですか?
一般的な視力検査はもちろんのこと、緑内障の診断に広く使われているハンフリー視野検査、検査技師が手動で行い広い視野の範囲を確認することができ、多様な疾患に対応したゴールドマン視野検査、視神経の異常の有無を調べるフリッカー検査などに対応しています。これらの検査により、緑内障以外にも、脳腫瘍などによる視野欠損や視神経炎、網膜色素変性など、さまざまな疾患の可能性を調べることができます。また、新たに導入したOCTにより、これまで以上に緑内障や加齢黄斑変性など網膜疾患の早期発見や精密な診断を行えるようになりました。当院には常勤の検査技師が1人在籍していますので、これらの検査にも随時対応しています。検査の結果、緊急性が高い場合や手術が必要と判断した場合は、連携している武蔵野赤十字病院や杏林大学医学部付属病院などに適宜紹介いたします。
自治体の眼科検診や学校健診にも取り組まれるのでしょうか?
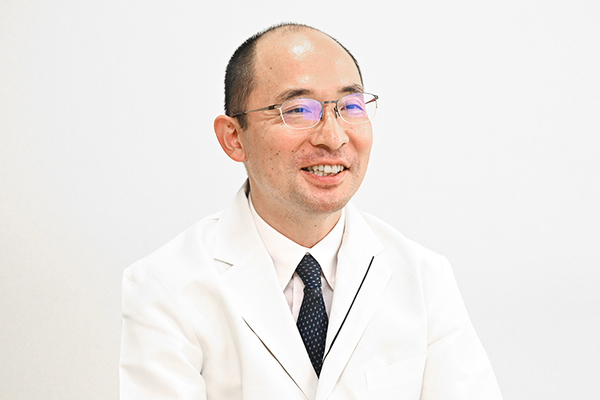
そうですね。地域の眼科クリニックとして、地域に根差した医療に取り組んでいきたいと思います。職場などで受ける健康診断で行う目の検査は、視力検査のみの場合がほとんどです。しかし、加齢に伴って増えてくる目の病気を早期発見するには、視力検査だけでは十分とはいえません。自覚症状に乏しい初期の段階で病気を見つけるには、定期的に眼科での検査・診察を受けることが大切です。40歳を過ぎたら、自治体の眼科検診は積極的に受けてほしいと思います。
地域に根差した眼科診療を継続
眼底検査ではどのようなことがわかるのですか?

眼底の血管や視神経、網膜などの状態を調べることにより、緑内障や黄斑変性などの病気の発見につなげられますし、ご自身は糖尿病、高血圧の自覚がないのに眼底検査で糖尿病網膜症、高血圧性網膜症の所見が見つかり、内科を受診して糖尿病や高血圧と診断される場合もあります。さらに、眼底の血管を観察することで高血圧症を推測できる可能性もあります。
お忙しい日々だと思いますが、休日はどのようにお過ごしですか?
5歳になる子どもがいるので、子どもと過ごす時間を大切にしています。公園や児童館に遊びに行ったり、妻が親子向けのイベントをいろいろ見つけてくれるので、それらに参加したりしています。個人的な趣味では、体を動かすことが好きで、トライアスロンや登山、テニスなどを楽しんでいます。新型コロナウイルス感染症がはやっていた時期はなかなか行けなかったので、ようやくぼちぼち再開したという感じですね。登山やテニスは、子どもが大きくなったら親子でチャレンジしてみたいですね。
最後に、今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

前院長から引き継ぎ、地域に根差した眼科医療を心がけてまいりいたいと思います。商業施設の8階にある当院は、吉祥寺駅からのアクセスも良く、待合室からは大きな窓越しに見晴らしの良い風景を味わうこともできます。目がかすんだり、よく見えないことがあるなど、目のトラブルは加齢に伴うことが多いですが、ドライアイや眼精疲労は年齢に関わらずかかる可能性のある疾患です。コンタクトレンズのご相談はもちろん、何か気になることがあれば、気軽に当院にお越しください。






