高野 学美 院長の独自取材記事
貝坂クリニック
(千代田区/麹町駅)
最終更新日:2025/08/04

麹町駅近くのビル10階にある「貝坂クリニック」は、千代田区を中心に通院困難な患者に対して在宅医療を提供し続けてきた。大学病院の麻酔科で研鑽を積んだ院長の高野学美先生は、2006年の開業以来、がん手術後の疼痛ケアや在宅酸素療法など幅広いケースに対応。介護施設や専門病院と連携を取りながら、合併症を起こしやすい認知症患者のケアにも力を入れている。新型コロナウイルス感染症の流行に際しては、千代田区医師会において重篤な患者をスムーズに診療する体制をつくることに尽力。「誰もがいずれは看取られる立場になるのですから、早くから在宅医療に関心を寄せてほしいですね」と語る高野院長に、日々の診療についてや医師としてのポリシーなどを聞いた。
(取材日2024年5月29日)
疼痛緩和や胃ろう、人工肛門など幅広い領域をカバー
在宅医療に特化された背景を教えてください。
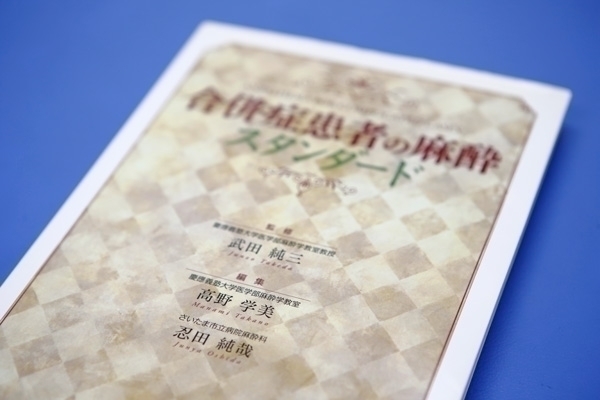
もともと私は麻酔科の医師として大学病院に務め、緊急性の高い手術の全身麻酔や、さまざまな痛みの緩和や解消をめざすペインクリニックの外来診療などに携わっていました。終末期の患者さんを看取ることも多く、最期まで“その人らしく生きる”ために何ができるのかを模索する日々の中で、自分が進むべき道として選んだのが在宅医療です。やがて超高齢社会に突入する日本では、患者さんが安心して療養できるご自宅できめ細かな医療を提供できる医師が必要になる。その確信を同じ医師である主人とも共有できたことで、2006年に土地勘のあった千代田区平河町で貝坂クリニックを開業しました。
具体的にはどんな医療を提供しているのでしょうか?
訪問先は保険適用のエリアであるクリニックから16キロ圏内のご自宅や高齢者介護施設が中心です。私の麻酔科での経験を生かし、在宅緩和ケア、がん疼痛ケア、在宅酸素療法も提供していることが特徴です。その他、自発的に食事摂取ができない患者さんには中心静脈栄養法や胃ろうの管理、点滴などを行いますし、硬膜外ポートや人工呼吸器の管理など専門性の高い領域もカバーしています。難病の患者さんに対しても専門の先生に相談しながら療養をサポートしますし、状態が急変してしまった際にも都内の急性期病院と連携して24時間体制で早急に対応できるよう体制を整えています。
がん疼痛などの緩和ケアで心がけていることはありますか?

患者さんの生命力を最大限に引き出し、できる限り長生きしてほしいと願いながら緩和ケアを行っています。がんの末期だからと諦めて併発疾患を治療しない場合もあるようですが、私は治るように努力します。また、身体的な痛みについては、鎮静薬や医療用麻薬で軽減を図るだけでなく、メンタル面のケアも欠かさず行うようにしています。好きな場所で好きなものに囲まれて過ごすことを許容して前向きになっていただくことで、免疫力の向上につなげ少しでも長く幸せに残された時間を生きてほしいのです。そういった面からも、在宅医療の役割は大きいと思いながら診療しています。
緩和ケアは患者さんの気持ちに寄り添うことも大切なんですね。
私の役割は、患者さんのご要望を最大限くみながら、医師として容体を的確に見極めつつ麻酔や医療用麻薬を駆使して痛みの緩和をめざすことだと考えています。患者さんやご家族が少しでも後悔を残さず旅立つお手伝いができたのであれば、在宅医療の道を選んだ者としてこんなにうれしいことはありません。一概に再入院や再手術を押しつけるのではなく、今後も患者さんやご家族の考え方に寄り添った医療を続けていきたいですね。
認知症の早期対応、患者の心のケアにも力を入れる
患者さんとのコミュニケーションで大切にしていることを教えてください。
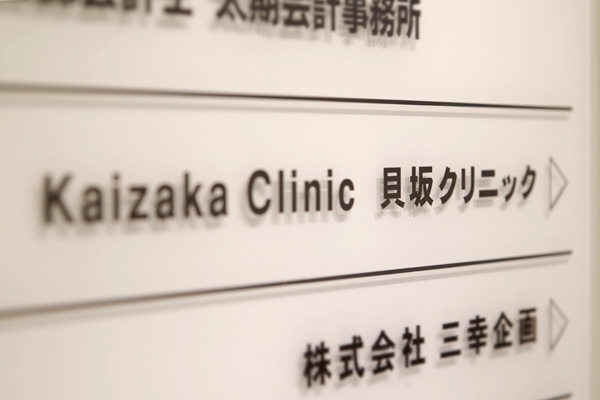
大きな手術を経験したり、重い症状を抱える患者さんは、医師の目をよく見て真意を読み取ろうとするものです。「ごまかしていないか? 信じていいのか?」と。だからこそ、やみくもに希望を抱かせるような展望は語らず、伝えるべきことは包み隠さずお話しすることで信頼関係を築くことをめざしています。真実を伝えることで患者さんを絶望させてしまう可能性がある場合は伝え方を加減して、できる限りポジティブな言葉を探します。例えば症状が進行していないのであれば、「今週もお変わりなくて良かったですね」と伝える。患者さんに安心していただいて、次の訪問まで快適に過ごしていただくことを重視しています。
先生は認知症サポート医として、認知症の早期発見や改善を促す取り組みにも力を入れているそうですね。
ここ数年の認知症患者の増加が著しく、危機感を抱いております。2025年には患者数が700万人になるともいわれておりますが、ご本人も身近なご家族も初期症状に気づきにくいんですよ。「最近、物忘れが多いけれど、高齢だから仕方がないか」と、対処を遅らせているうちに、どんどん症状が進んでしまう。それを避けるために、千代田区は認知症が軽度でも相談できる窓口を設けており、当院のような認知症サポート医や専門病院を紹介する体制を整えています。軽度認知障害(MCI)に対するアプローチは、早期であればあるほど良いとされていますので、心配な方はお早めに行動することをお勧めします。
認知症についてはどんなスタンスで診療していますか?

認知症が進行すると、脳が萎縮して全身のいろんな機能が衰え、歩けなくなってしまったり、自力での食事が困難になったりすることもあります。そういった合併症状を最小限にとどめられるように、骨折が疑われる場合はすぐに病院への紹介状を書くなど、やはり早めの対応をすることが大事です。今後のさらなる高齢化に向けて、当院も専門病院との連携を強化していきたいと考えています。また、千代田区は区民を集めてコーヒーを飲みながら認知症の情報を伝える、認知症カフェの活動もしているので、お役に立てる局面があれば私も参加していきたいですね。
緊急事態に備えた医療連携の体制構築にも尽力
先生は千代田区医師会の活動にも尽力されてきたそうですね。

新型コロナウイルス感染症の流行に際しては、区内の病院や保健所、薬局と連携して重篤な患者さんに対応する体制をつくることに力を入れました。医師会に所属する医師が曜日ごとに当番制で深夜の診察にも対応できるスケジュールを整え、保健所から要請を受けたら防護服を着て往診に向かう。その場で解熱剤や酸素療法が必要な場合は薬局や業者に連絡して届けてもらう。入院するべきなら救急車で病院に向かってもらう。私は日頃から訪問診療を行う上で関係部署とコミュニケーションしているからこそ、スムーズな連携システムをつくることができたのではないかと思います。その経験を生かして、今後また同じようなパンデミックが起きてしまった場合も、構築した医療体制をもとに対応していきたいと考えています。
日々の診療で患者さんの命に向き合いながら、地域貢献にも尽力する情熱の源はどこにあるのでしょうか?
当時、千代田区の医師会で在宅医療に特化している先生はおられませんでした。未知のウイルスに直面して、慣れないステイホーム生活を強いられてたくさんの人々が混乱している中で、「自分が率先して体制を整えるしかない」という使命感を抱いていました。医師として、困っている人の助けになりたい、役に立ちたいという気持ちは常に持ち続けています。ちなみに最近はプライベートで気象情報をベースに地震を独自予測することにも力を入れています。病気だけでなく天災とも戦えるようになれたら良いのですが、さすがに責任が大きすぎますので個人的な趣味にとどめておきたいと思っています(笑)。
読者に伝えたいことはありますか?
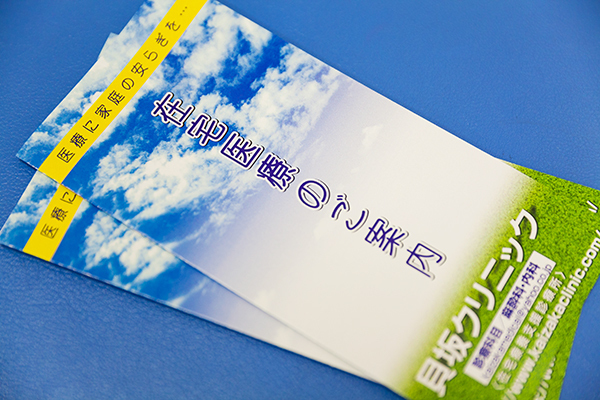
高齢の方々は、いつ病気を発症してもおかしくありません。急にケガをしたり、事故に遭ったりする可能性もあります。そんな緊急事態に直面しても慌てないように、転ばぬ先のつえとしてかかりつけ医を見つけ、良い関係を保っておくべきではないでしょうか。そして、コロナ禍のような危機が再び訪れる可能性もありますし、今後は在宅医療に詳しい先生を選ぶメリットが大きくなるはずです。私は千代田区医師会の介護保険の取り組みにも携わっていますので、これからも地域に密着した在宅医療を提供していき、ご高齢の方々にとって近しい存在の医師でありたいと思っています。






