所 為然 院長、次田 正 先生の独自取材記事
鼠径ヘルニア日帰り手術 広島アルプスクリニック
(広島市東区/広島駅)
最終更新日:2025/06/06

広島駅から徒歩5分の商業施設内にある「鼠径ヘルニア日帰り手術 広島アルプスクリニック」は、鼠径ヘルニアに対する日帰り手術に特化したクリニックとして2024年5月に開業。広島県内では少ない日帰り手術のクリニックだけに、開業当初から多くの患者が訪れている。勤務医時代から腹腔鏡下手術の研鑽を重ねてきた所為然(ところ・ゆきなり)院長と、日本外科学会外科専門医・日本消化器外科学会消化器外科専門医として数多くの外科手術に携わってきた外科統括部長の次田正(つぎた・まさし)先生がタッグを組み、負担の少ない腹腔鏡手術を提供する。クリニックの柱である鼠径ヘルニアの日帰り手術についてや同院の特徴、めざすクリニックのあり方まで話を聞いた。
(取材日2024年12月12日)
専門性の高い鼠径ヘルニアの日帰り手術に特化
クリニックの特徴について教えてください。

【所院長】当院は鼠径ヘルニアの日帰り手術に特化したクリニックです。2022年に私が開業した「大阪うめだ鼠径ヘルニアMIDSクリニック」で積み重ねた日帰り手術の実績を生かした鼠径ヘルニアの専門性の高さが当院の診療の強みです。鼠径ヘルニアは体の筋肉の隙間から主に腸やその他の臓器、脂肪などが皮膚の下まで出てくる病気で、脱腸と呼ばれるゆえんです。3人に1人が罹患するともいわれている病気ですが治療方法は手術しかなく、開腹手術と腹腔鏡手術が適応になります。患者さんの視点からどちらの手術が良いかと言えば、低侵襲の腹腔鏡手術が推奨されます。腹腔鏡手術は技術が必要ですが、当院では鼠径ヘルニアに対する専門性の高い医師が多くの経験に基づいた日帰り手術に取り組んでいます。
次田先生のご経歴について教えてください。
【次田先生】私は1981年に筑波大学医学部を卒業し、東京女子医科大学病院の消化器医療部門に入局しました。その後、消化器外科医として研鑽を積み、65歳まで東京都内の公立病院に勤務しました。その後、山口県に転居し、所院長と巡り合うチャンスがあり、当院に入職したという経緯です。これまでに、鼠径ヘルニアをはじめ胆嚢摘出、虫垂炎の手術に数多く携わってきましたが、当時は入院を伴う手術が主でした。しかし、実際にはきちんと手術をすれば入院中は治療の必要がない外科疾患です。日本ではまだ普及していないというだけで、欧米では効率的に日帰り手術が行われているという実態があります。
所院長のご経歴と広島で開業された経緯を教えてください。

【所院長】2010年に広島大学を卒業後、関東をはじめ複数の病院で6年間勤務しました。その後、中国への留学を経験し、帰国後、大阪赤十字病院に4年間勤務し、2022年12月に大阪で開業しました。私が外科の医師になった頃は、まだ腹腔鏡下手術よりも開腹手術がメインでしたが、今後は患者さんの身体的負担が少ない腹腔鏡下手術のニーズが高まるだろうと考え、大阪赤十字病院で専門的に取り組みました。開業後も鼠径ヘルニアの日帰り手術を中心に多くの症例を積み重ね、広島での開業に至りました。広島院を開業した理由は、自分が広島大学の出身であり、そして、これまで広島には鼠径ヘルニアの日帰り手術に特化したクリニックが見当たらなかったからです。開業した月から多くの患者さんに来ていただき、手術件数も月を追うごとに増えています。
手術計画表の提示などの工夫で安心を提供
患者さんが気軽に脱腸の相談をできるような取り組みをされているそうですね。

【所院長】患者さんが脱腸を疑って受診し、いきなり手術と言われると怖いし、話を聞くのがおっくうに感じる方もいらっしゃると思います。臨床医という立場上、これまでに手遅れのケースも診てきました。受診を怖がり口の中の歯肉がんをマスクで隠して生活してきた人、乳がんを疑っているけれど診断されると怖いという人など、悪性疾患では手遅れになって命に関わります。鼠径ヘルニアのような良性疾患も同じで、手術をためらって放置していたら命に影響するような病態です。膨らみが大きくなれば手術の難易度が上がりますし、術後の合併症の発生リスクも上がります。当院ではそのような事態を招かないよう、患者さんの心のハードルを下げる目的で、まず看護師に健康相談ができる会を実施しています。
手術を受ける方に独自の手術計画表を渡されていると伺っています。
【所院長】手術計画表は標準的な経過を説明するスケジュール表ですが、当院ではオリジナルで「患者さま用診療計画表」という冊子を作成し、手術を受けられる方にお渡ししています。検査内容や結果、麻酔の説明のほか、手術前日の食事時間、当日の持ち物など、患者さんが行う準備についても記載。手術後は、状態を確認するチェックシートに患者さん自身で記入していただき、電話確認しています。「患者さま用診療計画書」は手術の記録であり備忘録のようなものです。私たちと患者さんが一緒に治療を進めていけることを念頭に置いて作成し、安心して日帰り手術に臨んでいただくためのツールとして活用しています。
スタッフの皆さんについても教えてください。
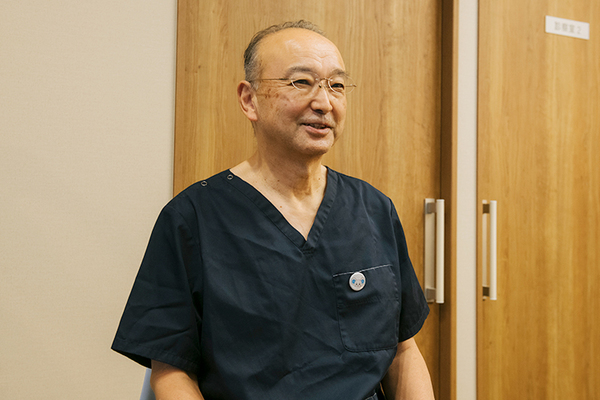
【所院長】当院では、医師・スタッフの垣根を超えてコミュニケーションを取るようにしています。開業時より患者さんが質問しやすい・話しやすい環境をつくることを心がけており、そのためには、医師とスタッフがお互いに親しみを持ってコミュニケーションを取ることが大事だと思ってます。また、患者さんから親近感を持ってもらえるよう、スタッフがクリニックのキャラクターを作ってくれました。「脱腸」と、「鼠径の1文字目がネズミ」ということから「だっちゅう」というネズミのキャラクターです。シンボルキャラクターとしてクリニックのPRに活躍してもらいたいと思ってます。
【次田先生】医師、看護師、受付などを含め8人の多職種が連携してチームで診療にあたっています。きちんとコミュニケーションを取るため、それぞれの人間性や技能に対して尊敬を持って接する姿勢を大切にしています。
細部までイメージできる丁寧な説明で患者の不安を払拭
院名の由来を教えてください。

【所院長】アルプスを「RLPS」とアルファベットで表記しており、「Robot」のR、腹腔鏡を意味する「Laparoscopy」のL、手術を意味する「Surgery」のSを合わせた造語です。つまり、ロボットと腹腔鏡で日帰り手術を提供するということですね。この15年以内にロボット手術が腹腔鏡手術に取って代わるといわれています。当院においても、そういった世間のニーズの変化に応え、長く医療を提供できるようにという意味も込めました。長く社会貢献するためには、心意気だけでなく、先のニーズを読むことも必要です。クリニックだからこそ、将来を見据えた医療を提供するフットワークの軽さはあると思いますね。
診療で大事にしていることは何でしょう?
【次田先生】今は、医療従事者が正しい情報提供を行って、十分理解していただいた上で患者さんに治療の選択をしていただく時代です。ですから、わかりやすい言葉で説明するということを心がけていますし、患者さんの疑問に対してはきちんと対応して、かみ砕いて説明するようにしています。手術に関しては何よりも安全が大事です。これまで、目的を達成するために積み重ねてきた外科の手技を駆使して、精密に安全に完結できるように心がけています。
【所院長】患者さんの手術に対する怖さは、細部までイメージできることで軽減されると思います。当院は鼠径ヘルニアの患者さんを多く診ており、さらに多くの日帰り手術を診ているからこそ、手術前から手術後までイメージしていただける説明ができます。かゆいところに手が届く診療を心がけたいですね。
今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

【所院長】当院では、鼠径ヘルニア手術に関する独自のデータベースを作成しています。例えば、合併症の発生数やその原因などをしっかり振り返るための記録です。数多くの手術を行うことでまれなケースもたくさん診ることになりますし、データを集めることでどういう方にどのようなことが起こり得るかを分析し、それらを未然に防ぐための方法を検討することができます。そのデータを生かし、患者さんに安心と安全をご提供できるクリニックをめざしています。
【次田先生】開業以来、広島県内においても日帰り手術のニーズが増えていることを実感しています。さまざまな患者さんの医療情報を十分に活用して、患者さんの疑問や不安に応えられるよう、所院長と協力して取り組んでいきたいと思います。






