アトピー性皮膚炎や花粉症などは
アレルギーの専門家に相談を
山と空こどもアレルギークリニック
(八王子市/八王子駅)
最終更新日:2024/07/29


- 保険診療
子どもに湿疹を見つけた時「アレルギーだったらどうしよう」と心配になった経験がある人もいるだろう。国民病ともいわれる花粉症は0歳児でもかかることもあり、子育てとアレルギーの不安は今や切っても切り離せない。小児科とアレルギー科を掲げる「山と空こどもアレルギークリニック」の鈴木俊輔院長のもとにも、アレルギーに関するさまざまな心談事が日々寄せられている。そんな患者一人ひとりに、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医として高度な診療を提供している鈴木院長。そもそもアレルギーとは何なのか、なぜ専門的な治療が大事なのか。また、アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎とはどのような病気であるのかなど、詳しく教えてもらった。
(取材日2024年1月4日)
目次
花粉症などのアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎はアレルギーを専門とする医師に相談を
- Qまずは「アレルギー」について教えてください。
-
A

▲日本アレルギー学会認定アレルギー専門医の鈴木院長
人体には免疫システムが備わっているので、体にいらないものが入ってきたら追い出そうとするのは自然なことです。この免疫の働きが暴走して過剰に反応してしまうことをアレルギーといいます。お子さんがアレルギーだと「育て方に問題があったのでは」と悩む親御さんもいますが、それは違います。その子が生まれ持ったアレルギーになりやすい体質というものがあり、誰のせいでもありません。ただ、遺伝や環境も無関係ではなく、特に治療の仕方によってはアレルギーを悪化させてしまうこともあるので注意が必要です。このため、当院では初診の患者さんには生活習慣だけでなく、これまでどんな薬をどのように使用してきたのかも詳しく聞いています。
- Qアレルギーは市販薬も入手しやすいですよね。
-
A

▲小児科とアレルギー科の専門クリニックとして2023年に開業
市販薬は眠くなりやすい成分が入っているタイプも多いので、車の運転をする方などにはお勧めできません。明らかな居眠りだけではなく、自覚できない眠気もまたやっかいです。知らずしらずのうちに勉強のパフォーマンスを落としていることもあるので、特に受験生は使用を控えたほうが無難ではないでしょうか。また、鼻詰まりの即時解消が期待できるとうたった市販薬もありますが、ぶり返しのリスクが強く、常用しているうちに薬剤性鼻炎に陥ってしまうケースもあります。アトピー性皮膚炎でもアレルギー性鼻炎でも、まずはアレルギーを専門とするクリニックを受診することをお勧めしたいです。
- Qアトピー性皮膚炎の特徴や治療法について教えてください。
-
A
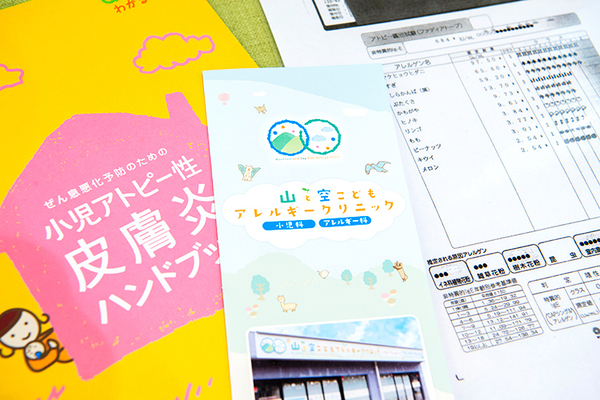
▲スタッフ一同、日々進歩する医療に対して学ぶことを怠らない
アトピー性皮膚炎は、繰り返し現れるかゆみのある湿疹が特徴です。乳児期は顔、幼児期から学童期は肘の内側、膝の裏側、首の周りなどに出やすい傾向があります。お肌のバリア機能が弱く、外から汚れ・ほこりのようないろいろな刺激が入ってきて炎症が起きてしまいます。さらにほこりが入り続けることによりハウスダストのアレルギーになってしまいます。お肌荒れがあるとよりいろいろな刺激が入りやすくなることにより、新たなアレルゲンができてしまったり、アレルギー体質が強くなってしまうことから適切な治療が必要になります。
- Q花粉症などのアレルギー性鼻炎のお子さんもとても多いようです。
-
A

▲わかりやすい丁寧な説明を心がけて診察している
アレルギー性鼻炎とは鼻の中に侵入してきたアレルゲンを追い出そうと過剰な鼻水、鼻詰まり、鼻のかゆみなどが起きる病気です。花粉が原因の場合は花粉症と呼んでいますが、ダニ由来のアレルギー性鼻炎もあります。アレルギー性鼻炎は副鼻腔炎(蓄膿症)や中耳炎を引き起こしやすく、眠りの質も落ちるので発育や学習への影響も心配です。また、常に鼻の粘膜が傷んでいるので鼻血を出しやすくなっています。鼻の穴がふさがりそうになっているため鼻くそが詰まっているような感覚があり、鼻をほじる癖がついているお子さんもいます。「やめなさい」と叱るだけではなく、アレルギーを専門とするクリニックで鼻を診てもらうようにしてください。
- Qアレルギー症状にはどのような検査や治療を行いますか?
-
A

▲大人のアレルギー疾患に対する診療も提供している
血液検査やごく少量のアレルゲンを皮膚に置いて反応を見るプリックテストなどは広く行われていますが、数値が高い人が発症するとも限らず、あくまでも目安にすぎません。数値よりも、問診と診察で実際にどのようなアレルギー症状が起きているのか確認することが大事ですし、これを得意としているのがアレルギーを専門とする医師です。結果をもとに一人ひとりに合った投薬治療をしていきますが、基本的に塗り薬も飲み薬も長期的に使うことになります。どの薬を、どれくらい、どのように使うのかが非常に重要です。また、自己判断で薬をやめると悪化する恐れがありますので、必ず医師の指示どおり続けるようにしてください。






