医療現場への第一歩を支える
病院実習前の抗体検査・ワクチン接種
東山かわぐちクリニック
(京都市東山区/清水五条駅)
最終更新日:2025/09/22


- 保険診療
医学部や薬学部などの学生が病院実習に臨む前に求められるのが、抗体検査とワクチン接種だ。感染症から自身を守るために不可欠な手続きだが、「どこで受ければいいのか、費用はいくらか、結果はいつ出るのか」と戸惑う学生は少なくない。「東山かわぐちクリニック」では京都女子大学との連携をきっかけに、8年前から医学生向けの抗体検査・ワクチン接種を行っている。さらに、他の分野の学生への各種診断書の発行や、外国人留学生への英語対応などの幅広いサービスも提供。通常の診療はもちろん、入学前から実習、国家試験に必要な証明書に至るまでトータルで支援する。地域に根差したクリニックとして、プラスアルファの医療サービスでも貢献する同院。川口道也院長に、抗体検査の流れや対応する診断書など学生へのサポート体制について話を聞いた。
(取材日2025年4月7日)
目次
抗体検査から診断書発行まで。英語対応も可能な一貫サポートで、京都の医学生の成長を支援
- Q医学部生の抗体検査・ワクチン接種を始めた経緯は?
-
A

▲医学部生向けの抗体検査やワクチン接種を行っている
医学部・薬学部などの学生さんは、病院や施設での実習を前に、麻疹、風疹、水痘、おたふく風邪であるムンプス、B型肝炎などの感染症予防として、抗体検査やワクチン接種が求められます。当院では開業当初の8年前に、京都女子大学からご紹介いただいたことで、学生さんへの対応を行うようになりました。年々需要が増え、今では他の学校の学生さんも多く来られています。学校から抗体検査の指示を受けても、「どこで受ければ良いのか」「費用はどのくらいかかるか」「結果はいつ出るのか」など、わからないことが多いんです。そういった学生さんの不安や疑問に応えたいという思いから、こうした医療サービスの提供を続けています。
- Qワクチン接種が期限ギリギリになる学生さんもいらっしゃるとか。
-
A

▲「どんなことでも相談してほしい」と話す院長
一定数いらっしゃいますね。特にB型肝炎のワクチンは3回接種が必要で、それぞれに一定の期間を空ける必要があるんです。また、来院されてもすぐに接種できるわけではありません。学生さんの体調やワクチンの状態によっても、接種できるかどうかが変わってきますので、少しでも早めにご連絡いただければ、迅速に応じます。また、医学部の学生が受けるタイミングとして、病院実習の前という大学もあれば、最近は入学前から準備するよう指示する大学も増えています。どんな状況でも、できるだけ臨機応変に対応いたしますので、まずはご相談ください。
- Q病院実習前の抗体検査・ワクチン接種の流れを教えてください。
-
A

▲病院実習前の抗体検査やワクチン接種を行っている
お電話で予約をいただくのが一般的です。ご来院いただいたら、まず抗体検査を行います。約1週間後に結果をお伝えしますが、もし抗体価が低い場合、つまり免疫力が十分でない場合には、ワクチン接種が必要となります。その際は、改めて予約を取っていただいてから、後日にワクチンを接種します。B型肝炎のワクチンのように1回で完了しない場合もありますので、実習までの期間から逆算して、早めにご相談いただくことをお勧めしています。接種後は、一般的な予防接種と同様に、アレルギー反応が出ないか20〜30分ほど院内で様子を確認します。
- Q各種診断書の発行についても対応されているそうですね。
-
A
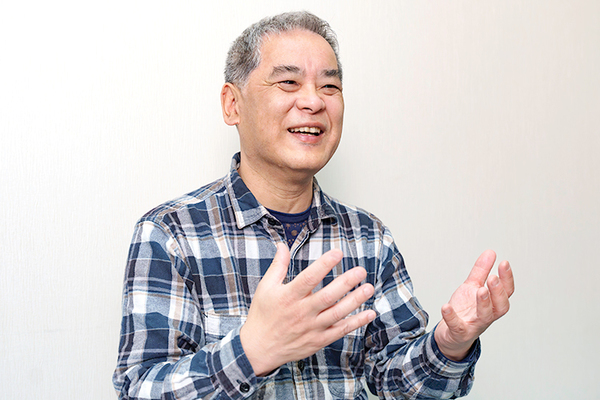
▲患者の悩みに寄り添い、幅広い対応を心がけている
はい。医学部・薬学部をはじめ、多様な分野の学生さんが国家試験を受ける際に必要な診断書を発行しています。国家試験ではさまざまな健康証明書が求められるので、対応範囲は広いです。調理師の国家試験用の証明書や、小型船舶免許に必要な診断書なども出していますね。またこの辺りは外資系ホテルが多く、そこで働く方々の健康診断も受けていますので、英語対応も可能です。若い方はかかりつけのクリニックがなく、診断書をどこで発行してもらえばいいかわからないケースが多いです。当院では当日出せる診断書であればその場で発行しますし、血液検査が必要な場合も通常2〜3日で結果が出ます。学生さんでも安心してご利用していただけますよ。
- Q外国人の患者さんも多く、英語でも対応するとお聞きしました。
-
A

▲地域に根差し、プラスアルファの医療サービスでも貢献する同院
アメリカ留学の経験もあり、ネイティブレベルの英語でコミュニケーションができるので、外国籍の方も積極的に受け入れています。風邪などの軽症から、予定より滞在が長くなってお薬が足りなくなった場合の処方まで、広く対応しています。日本語がある程度できる外国籍の方でも、医療の話となると専門用語が出てくるため、日常会話とは勝手が違いますよね。英語圏からの方であれば、母国語で体調の変化や不安なことを詳しく説明できるので、患者さんに安心感を提供できていると感じています。英語での対応について、皆さんとても喜んでくださっているのではないでしょうか。






