0歳から始める
小児歯科の活用法
豊橋キッズデンタルクリニック
(豊橋市/豊橋駅)
最終更新日:2025/10/23


- 保険診療
わが子に初めて歯が生えた時、それは親にとっても感動の瞬間だ。近年は、「このかわいい歯を守りたい」という愛情から、子どもの歯磨きや食育に熱心な保護者も増えているが、虫歯がない場合はいつから歯科医院へ通ったらいいのかに悩む人も多いだろう。日本小児歯科学会小児歯科専門医である「豊橋キッズデンタルクリニック」の中野崇院長は、「0歳から歯科医院へ通うことで、生涯にわたる健康につながります」と話す。「まだ歯もないのに歯科医院へ通うのは必要?」と感じる親も多いと思うが、小児歯科だからこそできる指導や親が気づいていない面へのアドバイスがあるのだという。0歳から小児歯科へ通うことには、どんなメリットがあるのかを詳しく聞いた。
(取材日2025年1月15日/情報更新日2025年10月17日)
目次
0歳から歯科医院へ通って健康な大人へ。口腔機能が発達する大事な時期だからこそ、得ておきたい知識や経験
- Q0歳からかかりつけの小児歯科を持つメリットを教えてください。
-
A
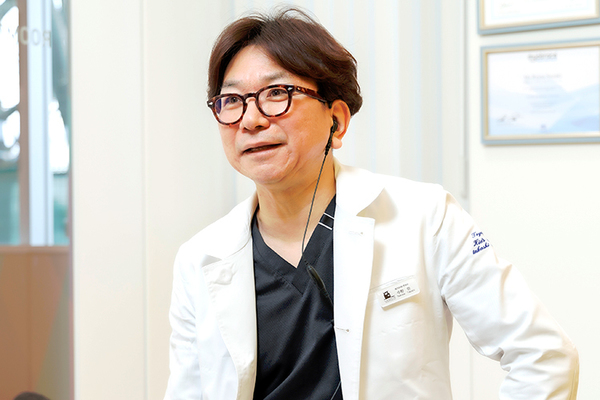
▲0歳から歯科医院へ通うことで、生涯にわたる健康につながる
まず一つは、不安があってから歯科医院に行くよりも、0歳の頃から正しい情報を得て安心して子育てができるメリットがあります。食べたり飲んだりの悩みやいびきや指しゃぶりなど、歯が生えていなくても心配事はたくさんありますよね。小児歯科では、そういった生活上の心配事も相談できます。もう一つは、歯並びが悪くなった場合の要因をお伝えできる点です。歯が生えそろう年齢になると歯並びの悩みが多く、お母さん方は遺伝や歯の大きさが問題ではないかと心配されるのですが、そこに至る生活習慣や癖には気づいていないものです。0歳から通っていることで、生活習慣などを指摘することでき、ひいては矯正の予防にもつながります。
- Qかかりつけの小児歯科を選ぶ際のポイントを教えてください。
-
A

▲子どもが通いたいと思える雰囲気づくりを行う
子どもの虫歯を治療するだけではなく、お口の機能発達を診ることが、ひと昔前にはなかった小児歯科診療で、大きなポイントになると思います。2018年から新しく「口腔機能発達不全症」という病名が認められ、小児歯科医療で注目されています。これは、18歳未満の小児で、食べる、飲み込む、話す、鼻で呼吸するという口腔機能が十分に発達していない病気。背景にある生活習慣を見極めた上で、口腔機能発達不全症の評価をして診断をつけることも小児歯科に必要なスキルだと思います。お口の中だけにフォーカスするのではなく、全身の成長とお口の機能の発達の関連性をお話ししてもらえるかどうかという観点で選ぶと良いでしょう。
- Q0歳から1歳の時期に注意することは?
-
A

▲家族で通いやすい工夫も施されている
食事と睡眠が大切な時期ですから、環境づくりの点で、正しく食べる、飲むことについてを親御さんが理解することが大切です。通常生後6ヵ月から離乳食が始まりますが、その前から「食べる飲む」が全身の発達に影響することを理解した上で育児をすることが、健やかな成長につながります。当院では、離乳食について、月齢で始めるのではなく、始めるタイミングの見極め方や、離乳食の初期、中期、後期に移行する時のポイントをお伝えしています。単純に口に入れるという行為もその後の発達に大きく関わってくる時期ですから、どういう食材をどういう方法で調理するのが良いのかを考え、お口の機能の発達を意識して離乳食を始めてください。
- Q2歳から3歳の時期に注意することは?
-
A

▲院内のスペースも広くトレーニングを実施できるスペースも確保
乳歯が生えそろ2歳から3歳の時期は、その乳歯が正しく機能しているかどうかはもちろん重要ですが、小児歯科では、乳歯をうまく使うための経験があるか、またその経験をどう生かせるかを見ています。自我が芽生え何でもやってみたい時期なので、自立を促す遊びや体験を大切にしてください。例えば、食べる時にすぐに「箸を使いなさい」と言うのではなく、まずは自分の意志でやらせてみて手づかみから経験させてあげることも必要です。手づかみができて、箸が使える、フォークも使えるという段階を見守り、お子さんの食べ方を通して、手づかみも必要であることを親御さんにも理解していただきたいですね。
- Qこちらのクリニックならではの取り組みを教えてください。
-
A

▲教室など積極的に開催し情報提供に努める
週に2回、0歳から3歳児の親子参加型の教室を開いています。教育と健康増進を目的に、口腔機能発達不全症のお子さんに対する口腔筋機能トレーニングや食べること・飲むことのセミナー、体験学習などを行っています。この教室には、まず診察で個別に悩みや状態を確認した上で、参加していただきます。仕上げ磨き、生活習慣、栄養、口呼吸、舌、歯並びなどの項目についてサポートするのは歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、保育士。各専門分野からアプローチしています。ご飯を握ったり、さまざまな切り方で提供したきゅうりの味の違いなどを体験したり、お口の感覚を育てる口のマッサージ法を親御さんが学んだりと、内容は多岐にわたります。






