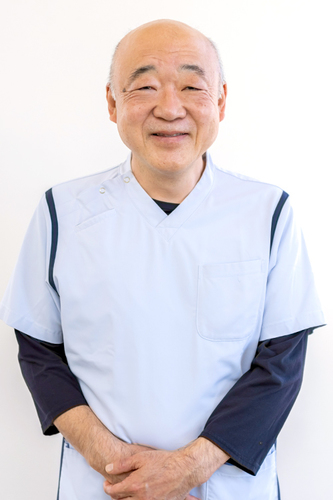患者をワンチームでサポート
関節リウマチのトータルケア
あずまリウマチ・内科クリニック
(狭山市/狭山市駅)
最終更新日:2025/10/23


- 保険診療
関節リウマチと膠原病の専門的な治療を行う「あずまリウマチ・内科クリニック」。東孝典院長は「今では早期に診断を受けて治療を始められれば、ほとんど元と同じように生活することも期待ができる疾患」と話す。同院では医師だけでなく適切な診断に必要な検査を行うスタッフをはじめ、患者の性格や生活背景なども把握した上で治療へのモチベーションをサポートする看護師や、関節の機能を維持し続けるためのリハビリテーションを提供するスタッフなど、クリニックがワンチームとなって患者をサポートする体制だ。この体制が具体的にどのように稼働しているのか、東院長に聞いた。
(取材日2021年12月1日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Qこちらのクリニックの診療体制の特徴は何ですか?
-
A
関節リウマチ・膠原病は免疫機能の異常で発症する病気ですから、関節の痛みや腫れだけでなく、合併症などの全身疾患にも対応する診療体制を取っています。例えば、合併症である間質性肺炎を引き起こしたら呼吸器の診察、手術が必要ならば対応できる病院にスムーズに引き継ぐといったことです。当院では関節リウマチが専門の先生や関連する診療科を専門とする先生に診療してもらっています。また看護部・検査部・リハビリテーション部が一つのチームとなり、患者さまそれぞれに合った診療を提供します。病状や処方された薬に対する不安や疑問などがあれば電話で24時間いつでも相談できる「リウマチコール」も開設し、ご相談をお受けしています。
- Qリハビリテーションの内容を教えてください。
-
A
関節リウマチの治療では薬物療法が主体ですが、理学療法を併用することで、日常生活に必要な機能の維持をめざせると考え、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを行っています。現在の痛みがリウマチ主体によるものなのか、日常生活動作による関節への負荷によるものなのかをしっかり判別しながら、一人ひとりの身体に合った運動療法や徒手療法を提供しています。また、院内ではエコー機器を各検査室のみならず、リハビリテーション室にも設置しています。リハビリテーションで通院している方が痛みを訴えた際に、すぐに確認し、必要と判断すれば医師と連携できるように備えているのです。
- Q薬物療法で使用する生物学的製剤とはどんな薬なのでしょうか?
-
A
バイオテクノロジー技術により作り出されたたんぱく質を用いた薬で、リウマチの関節炎を引き起こす炎症を抑えるのに有用です。近年にはさらなる効果を期待しての新薬の開発も進んでいます。生物学的製剤以外には価格が抑えられた後続薬であるバイオシミラーも登場し、治療薬の選択の幅が広がり、より寛解に導きやすくなってきたと考えています。診察室での一度の説明で理解していただくのは難しいので、治療の際に患者さまに必要なことを、図解パンフレット等を使って看護師からご説明しています。その際に大切にしているのは患者ファーストの姿勢です。患者さまに自ら「治そう」という明確な意識を持ってもらえるように取り組んでいます。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1医師による診察
-

診察では、触診に加え、痛みや腫れがいつから起こったかや、箸の使い方など日常生活で困っていることはないかなどを聞いている。院長が診察する際は看護師も診察に入り、難しい医学用語もわかりやすい言葉に言い換えて説明を行う。他の医師の診察でも必ず看護師が1人つくようにしているそうだ。
- 2看護師によるヒアリングや採血
-

看護師がフレンドリーに語りかけながらヒアリングや血液検査を行う。院内至急指示の血液検査では測定結果が20分以内に出るため、当日に結果を聞くことができる。看護部は情報共有センターの役割も担っており、診察室、検査部、リハビリテーション部等、各部署への情報共有を行い、患者それぞれに合わせた治療の実践に生かしているという。患者自身が不安に思っていることや診察の際に聞き漏れていたことなども気軽に相談できる。
- 3エックス線・CT・エコー検査
-

必要に応じて、エックス線やCT、エコー検査等を行う。エックス線・エコー検査では関節や骨を観察し、炎症や変形の有無、程度を判断する。エコー検査では関節内部は通常黒く映るが、炎症が起きている関節では血液の通り道ができ、赤く映るという。CT検査は、関節リウマチの合併症である間質性肺炎や骨折の疑いがある時などに実施するという。必要時には撮影したCT画像を、放射線科を専門とする医師が画像読影も行う。
- 4患者に合わせたリハビリテーションを実施
-

理学療法士や作業療法士が、日常動作を痛みなく行えるように姿勢や動作を改善する。炎症や痛みなどにより可動域が狭まった関節に対し運動療法や徒手療法などのリハビリテーションを行う。また、必要に応じて装具の作製も行い、日常生活動作での負担の軽減を図っている。
- 5定期的な通院
-

その後、病状によって定期的に通院。患者一人ひとりの状態を把握しながら、その時の病状に合った治療や検査、リハビリテーションなどを行っていく。医師、看護師、理学療法士が連携して、患者が無理なく通えるように支えていく。