石村 大輔 院長の独自取材記事
おかざきいしむら整形外科
(岡崎市/大門駅)
最終更新日:2025/08/06

大門駅から徒歩10分の所にある「おかざきいしむら整形外科」。前身の中西整形外科で勤務経験がある石村大輔院長が、クリニックを承継するかたちで2024年7月、リニューアル開業した。今までのクリニックの良さを引き継ぎながら、新たなクリニックをつくる決意、また、骨軟部腫瘍の治療を重ねてきた経験の中で培われた「患者とともに生きる姿勢」や、スポーツ整形外科に精通する医師としての真摯な思い、また患者とのコミュニケーションに対する信念など、石村院長の医療にかける熱い思いを聞いた。
(取材日2024年6月14日/情報更新日2025年7月28日)
患者とともに生きていく姿勢を大切に
院長は骨軟部腫瘍を専門とされているとお聞きしました。
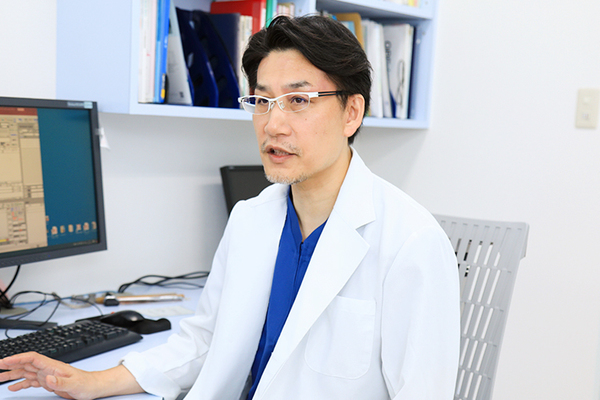
もともとスポーツとがん治療に興味があって、さらに尊敬できる先生たちとの出会いもあり、スポーツと関連の深い整形外科の中でもがん治療もできる骨軟部腫瘍を専門としました。骨や筋肉など軟部にできる腫瘍のことを骨軟部腫瘍といい、その悪性腫瘍はがん全体に対して発症割合は少なく、希少がんに分類されます。子どもから高齢者まで広い年齢層に見られる病気ですが、確立された治療法も少ないのが現状です。一人でも多くの患者さんの力になれればと思い、これらの疾患を専門的に診られる大学病院で長く研鑽を積んできました。
長年のシビアな診療経験を経た先生の診療姿勢について伺います。
例えば、子どもの頃に発症した患者さんとは、長く深く付き合うことになります。だから常に見て触れて、患者さんの心を推し量りながら寄り添う姿勢を貫いてきました。子どもの患者さんであっても自分の病気を理解してもらうために納得してくれるまで説明することも大切にしてきました。なぜ自分が治療をしなければならないのか、なぜ入院するのか、どんな治療を受けるのか、誠意を尽くして説明します。時には厳しいことを伝えなければならないこともありましたが、ご家族を含めて理解してもらえるよう何度でも説明を行い、どんな状況でも常に患者さんの側に寄り添うことが自分の基本的な姿勢になっています。
開業のきっかけを教えてください。

大学病院で骨軟部腫瘍の治療に長く携わってきて、厳しい医療現場であるだけでなく、そもそも治療や術後のフォローができる病院やクリニックが少ないことに問題意識を感じていました。受け皿があれば患者さんも通いやすくなり、大学病院の負担も軽減できると思い、開業を考え始めたんです。その頃、もう一つのライフワークであるスポーツ医学に関して、バスケットボールチームのドクターとして働ける話が来て、思い切って大学を退職しました。その勤務先に偶然、私が若い頃に非常勤医師として働いたことのあった「中西整形外科」の中西啓介先生の知人が入職されたんです。その人を介して中西先生と再会でき、開業の話をしたら「だったら、うちはどう?」とおっしゃっていただいて……。同じ骨軟部腫瘍を専門とする中西先生にこのタイミングで再会できて運命を感じましたし、以前一緒に働いていたスタッフが残っていたこともあり、すぐに承継を決めました。
スポーツをする人を医療の力で支えたい
スポーツ傷害の予防にも力を入れていきたいとお聞きしました。

私は自分もケガをした経験があるので、スポーツ傷害の治療やリハビリテーションに加えて、その予防にも関心があります。4~6月はちょうど、子どもたちが学校に入って初めて部活動を始め、初めてスポーツにふれる時期です。技術だけでなく、体力なども未熟なまま無理をすることで、疲労骨折や捻挫などのスポーツ傷害で受診される患者さんが多くなります。また、強いチームほど、痛みがあっても言えなかったり、病院に行きにくくなったりする傾向があり、悪化してから受診されることもあります。大人でも運動会でお父さんが急に体を動かすとケガをすることがありますよね。どちらも、本人や周囲の人にケガをするという認識や予防の知識がないことから起こります。楽しくスポーツをしてもらうためにも子どもたちだけでなく周囲の人や環境も含めてスポーツ傷害の認識と知識を広め、予防を促していきたいです。
指導者や保護者など競技者の周りの人の役割も重要なんですね。
コーチや保護者は、試合に勝ってほしいという願いから、つい子どもたちに期待しすぎることがあり、子どもたちはそれに応えようと頑張りすぎてケガをしたり、ケガを繰り返したりすることがありますが、それは本末転倒です。特に若年者であるほど、体力、柔軟性、さらに技術の差が大きくなるため、体力に見合った練習の強度やメニュー、休息の取り方などケガをしない工夫をしてほしいですね。逆説的ではありますが、ケガをしないことで練習時間が確保され、体の使い方もうまくなり、結果的に強いプレーヤーになれるのだと思います。
どのようにスポーツ傷害の治療や予防に取り組んでいくのですか?
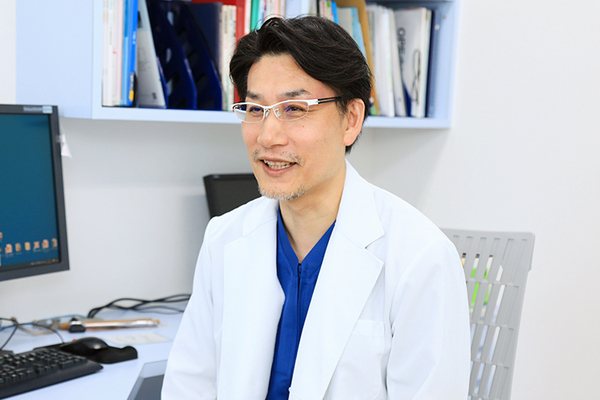
まず、治療やリハビリにおいては、体の傷めた部分だけでなく、全身のバランスなども考慮します。例えば、足を傷めた場合、足を診るだけでなく、体幹や上肢のバランスが弱ければそこをサポートし、その柔軟性にも気を配ります。また、練習の前後のアップの仕方やストレッチなども指導します。これまで、私は理学療法士や接骨院の方々 、学校のコーチ、チームトレーナーと連携して、ケガの状態、治療やリハビリの状況、練習の際の注意点などを共有する取り組みをしてきました。医師が患者さんに情報を伝えても、きちんと指導者にまで伝わらず、結局意味を成さないことでケガを繰り返すのはよくある話です。そこにメスを入れるのは大変でしたが、良い取り組みだと考えています。医療・リハビリの側から、スポーツチームへ直接情報共有ができると、ケガに対する意識が高まり、実際の練習や試合もより配慮されたものになると思っています。
納得・信頼の治療のためにコミュニケーションを重視
開業にあたって準備をされたことを教えてください。

中西整形外科に長年勤めていたスタッフに多数残っていただけるので、これまで中西整形外科で治療・リハビリをされていた患者さんにも、安心して通院を続けてほしいです。敷地の中にカフェスペースがあって、そこで患者さんが待ち時間を過ごせるのですが、とてもすてきな取り組みだと感じており、なるべく同じような環境を続けられたらと思っています。また、詳しい検査とわかりやすい説明のために、筒状ではなく、左右が開けた状態で検査できるオープン型のMRIを導入しています。これであれば、圧迫感も少なく、閉所恐怖症の方でもあまり恐怖を感じずに検査ができると思います。また、病気や痛みで下を向いている患者さんに少しでも安心して笑顔になってほしいと思い、クリニックの天井に空を作りました(笑)。患者さんが負担なく通えて、笑顔で帰れるようなクリニックにしたいですね。
患者さんとのコミュニケーションを大切にしているんですね。
そうですね。患者さんに触れ、目線を合わせて話をすることが、患者さんに納得して治療やリハビリを受けていただくことにつながると思っています。人は痛みがなくなると治ったと思って、治療やリハビリをやめてしまうことが多いんです。でも、完全に治ったわけではなく、続けて治療やリハビリが必要な場合があります。そういった場合に治療を続けてもらうには、患者さんとの信頼関係が重要と考えます。私は長くがん治療にも携わってきたので、患者さんに自分の状態をきちんと知ってもらい、治療の必要性を理解してもらうために、言葉と時間を尽くしたいですね。
読者へメッセージをお願いします。

継承前から中西整形外科に勤務しているので、クリニックの環境、患者さんの様子なども、ある程度理解しているつもりです。中西先生の患者さん第一の診療を引き継ぎ守り、最良の医療を提供したいと考えています。時間を取って来院いただくのですから、来る前より少しでも症状が改善して、来て良かったと笑顔で上を見ていただけたらと思います。首、肩などの体の痛みやしびれ、スポーツ傷害やケガ、加齢に伴うO脚変形や骨粗しょう症などもご相談ください。また、骨軟部腫瘍の専門家として「大学病院まで行くほどではないが相談したい」「すぐ受診できるよう近くで診てほしい」と思っている方がいらっしゃれば、相談に乗ります。もちろん、大学病院などとも連携しており、スポーツ傷害も含め必要があればご紹介しますので、気軽にご来院ください。






