稲見 誠 院長の独自取材記事
いなみ小児科
(世田谷区/三軒茶屋駅)
最終更新日:2025/08/29
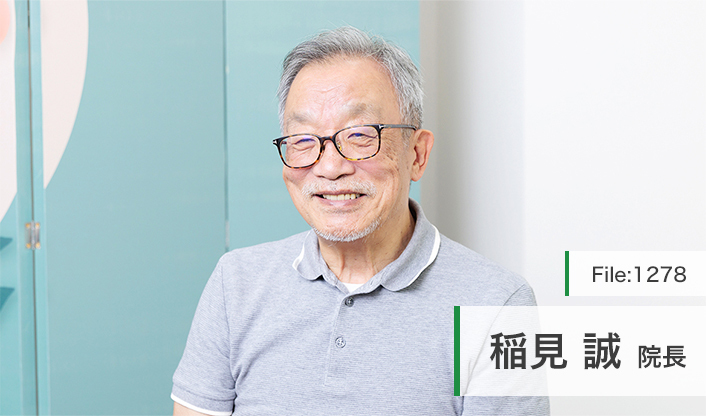
世田谷区下馬の閑静な住宅街にある「いなみ小児科」。駐車場の壁一面に描かれたカラフルな動物のイラストを前に、子育ての悩みにうなだれがちな親も思わず顔を上げずにはいられないだろう。院長の稲見誠先生が下馬に開業したのは1988年にさかのぼる。2015年に現在の場所へ移転し、地下1階から地上3階、延べ800平米の広さに拡充した。さらに、2025年7月には隣に新築したビルに、クリニックで行っている産後ケア専用ルームと子育て支援サービスの機能を移した。小児科診療のみならず、幅広い面から親子をサポートするクリニックとして、多くの近隣住民から親しまれ、悩める親子の居場所づくりを追求し続ける稲見院長。にこやかな表情の内に秘めた熱い思いをじっくりと聞いた。
(取材日2024年6月10日/情報更新日2025年8月20日)
多角的に子育てをサポートするクリニック
クリニックの隣に新しい施設がオープンしたそうですね。

はい。当院ではお子さんの病気を診るだけでなく、さまざまな育児支援にも力を入れてきました。これまでは、地下1階から地上3階までの建物内に、診療スペースと病児保育「ハグルーム」、産後ケア専用ルーム「Mama’s room」、親子で利用できる育児支援サービス「ひょっこりひろば」のスペースを設けていました。育児支援は診療スペースとは別フロアで行い、感染症対策を徹底してきましたが、出入り口が共通のため、感染症が疑われる患者さんと接触する可能性もゼロではありませんでした。そこで、より安心して育児支援をご利用いただけるよう、隣接地に専用の建物を新設しました。内装は「赤ちゃんとお母さんが安心できる空間を」とだけ希望を伝え、あとは建築の専門家と育児支援のスタッフに任せました。木のぬくもりを感じる温かな空間に仕上がったと思います。
子育て支援に乗り出したきっかけは何だったのでしょうか。
お母さんたちの涙です。開業してから診察中に泣いてしまうお母さんが多く、大学病院時代にはなかったことなので非常に驚きました。今は核家族化や共働きの影響で、子育て中の方が孤立しやすい状況にあります。どうにかしなければという一心で、多角的な機能をクリニックにプラスすることにしたのです。ひょっこりひろばでは子どもたちに遊び場を提供するとともに、「季節の病気」「手作りおもちゃ」といった勉強会や、ヨガ教室、誕生会、赤ちゃんのハイハイレースなど、親子が楽しく参加できるイベントなどを開催、ママ友・パパ友ができる場にもなっています。乳幼児が楽しそうに遊ぶ姿やお母さん同士が交流している様子を見かけると、私もうれしいです。
産後ケアルーム「Mama’s room」は、どのような人が利用できます?
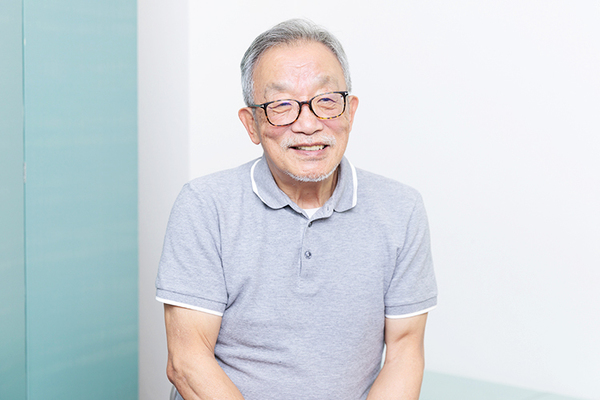
「Mama’s room」では、産後4ヵ月未満の母子を対象に母体ケアや乳児ケア、授乳・育児相談などを行っています。世田谷区の産後ケア事業として実施しており、利用を希望される場合は当院ではなく、お住まいの地域の子ども家庭支援センターにお申し込みいただくかたちです。産後ケアは「お母さんに休憩してもらうサービス」と軽く思われがちですが、中には「子どもがかわいいと思えない」「子育てがわからない」と泣きながら訴えるほど、シビアな状態の方もいます。そうしたお母さんの声に助産師が耳を傾け、寄り添いながら、育児への自信を取り戻せるようサポートしています。助産師だけでなく医師や看護師、保育士、心理士、保健師など多職種が、それぞれの立場から支援できるところが当院の強みだと思います。1人で悩んでいる方はぜひご相談ください。
安心して受診してもらうための工夫が多彩
病児保育室「ハグルーム」についても教えてください。

「ハグルーム」は、2003年に世田谷区の委託事業として立ち上げました。利用するためには、まず世田谷区保育課で事前登録をしておく必要があります。熱が出たときなど、利用したい日の前日もしくは当日の朝に予約をしてもらいます。その後、一度診察し、空いていれば利用可能です。もちろん、流行性の疾患については隔離部屋で過ごしてもらうようにしているのでご安心ください。私は病児保育に関しては比較的早くから取り組んでいて、当院には病児・病後児保育について専門に学んだスタッフが10人ほどいます。研究大会にも参加して、日々より良い保育のためのスキルアップを怠らない、自慢のスタッフたちです。
母乳相談に特化した外来についてもお聞きします。
これまで産後ケアを担当していた助産師から「母乳に関する相談が多いので、専門的な外来をつくってはどうか」という提案があり、新たに始めることにしました。もう1人ベテラン助産師を迎え、産婦人科を専門とする女性医師2人とともに、母乳に関する相談に幅広く応じています。火曜と金曜の9時から11時30分までと週に2回の試みですが、母乳マッサージに通われているお母さんも少なくありません。今は働きながら母乳育児に挑む人も増えているので「いかにして母乳を途切れさせないか」手を尽くします。完全母乳はもちろん、混合栄養にも対応可能です。ミルクを禁止しないのはお母さんを追い詰めないためです。お母さんの不安を取り除くのが何よりも大切ですからね。
育児相談にも注力されていますね。
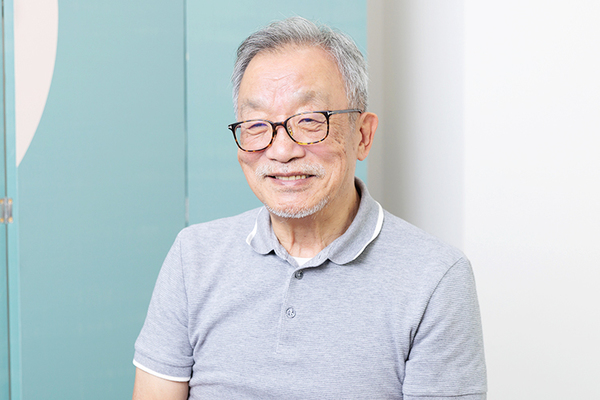
「Mama’s room」は4ヵ月未満の子どもを持つ人が対象ですが、5ヵ月目から急に子育てが楽になるわけではありません。対象期間を過ぎた親子も引き続き見守りたいという思いから、育児相談窓口を設けました。月1回の予約制で、当院独自の事業のため区外からでも利用できます。また、発達障害や不登校などの子どもとその親を対象に、心理士によるカウンセリングも実施。1組あたり1時間をかけ、親子一緒でも別々でも対応可能です。心理士は「前向き子育てプログラム」という参加体験型の学習会も開催しており、どなたでも参加できます。誰にも相談できず、インターネットで答えを探す親御さんも多いと思いますが、インターネットには誤情報もあります。だからこそ、病気でなくても気軽に相談できる場があり、親御さんの「相談する力」を育むことが大切だと考えています。
親子の気持ちを肯定し、共感することを大切に
診察の際にはどのようなことを心がけていますか?

まず「お母さんの気持ちを認める」ことを大切にしています。例えば「子どもが泣くたびに母乳を飲ませているが、体重が少しも増えない」と困っているお母さんに、頭ごなしに「泣くたびに母乳を飲ませるだけでは駄目」と言っては心を閉ざしてしまうかもしれません。「とても大変でしたね」とお母さんの行動をまず受け止めて、「母乳の量が十分に出ているか調べてみましょう」とその先のポジティブな解決策を提案していきたいと思っています。また、お子さんに対しては、どんなに小さくても1人の人間として見て、積極的に声かけするようにしています。
小児科医としてやりがいを感じるのはどんなときですか?
ありきたりですが、やはり子どもたちの笑顔や、お母さんからの「ありがとうございました」という感謝の言葉が大きなモチベーションになっています。また、病気の治療や子育てのサポートは、目の前の親子の安心や健康を守るためだけでなく、少子化対策にもつながると感じています。以前、子育て支援に関わる保育士が、あるお母さんから「ここがなければ2人目は考えられなかったと言われた」と喜んで話してくれたことがありました。私もその話を聞いて本当にうれしく、これまでやってきたことが報われた気がしました。医療従事者の中には、いわゆる「コンビニ受診」に否定的な意見もあるようですが、私はそれで構わないと思っています。困ったときに気軽に立ち寄れる場所でありたいし、そう感じてもらえることが大切だと考えています。
最後に読者へのメッセージをお願いします。
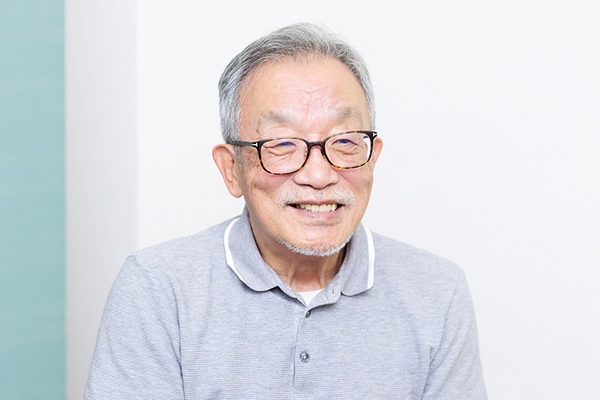
以前は出産直後の母子は産科で診るのが一般的で、小児科に来るのは生後3〜4ヵ月が多かったのですが、産後ケア事業に取り組むことで生後1ヵ月から介入でき、赤ちゃんの栄養やお母さんの心身の状態を早期に把握できるようになりました。昔は近所のおじさんやおばさんが叱ってくれたりごはんを食べさせたりしてくれたものですが、今の地域社会では難しい。祖父母に頼れない共働き家庭も増えています。だからこそ、小児科の医師が祖父母や近所の大人の役割を担い、いつでも頼ってもらえる存在になりたいと思っています。もし私に話しにくければ、女性医師、看護師、助産師、心理士に声をかけてください。気の置けない親戚に話に来る感覚で、どんなに小さなことでもご相談ください。






