海部 久美子 院長の独自取材記事
海部医院
(高松市/古高松駅)
最終更新日:2025/04/08
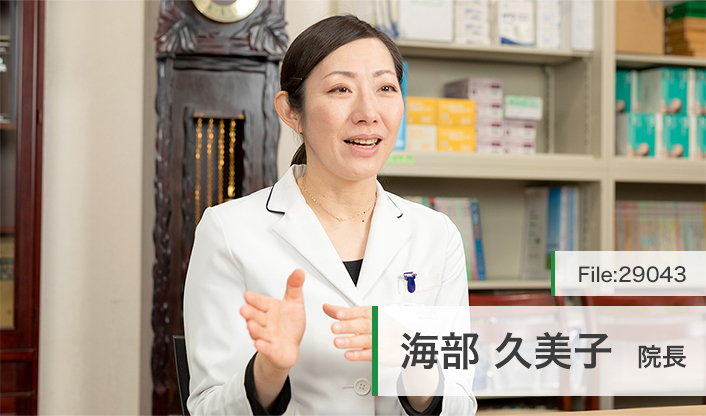
高松市高松町で1978年に開業し、約半世紀の歴史を持つ「海部(かいふ)医院」は、内科・皮膚科・泌尿器科・腎臓内科・循環器内科と5つの診療科を標榜。そのすべての科に、各分野を専門とする女性医師が在籍している。3階建ての建物の1階には4つの診察室や検査室などが並び、2階には19床の病室、3階には広々とした透析室を設けている。初代院長の長女として生まれた海部久美子院長は、艶やかな黒髪を丁寧にセットし、颯爽と白衣を着こなす女性医師。専門は腎臓内科だが、現在は循環器内科を除く4つの診療科を受け持つジェネラリストだ。「何でも話せる、何でも屋さんが理想」とほほ笑みながら、常に全力投球で診療に取り組む海部院長を取材した。
(取材日2025年2月8日)
ジェネラリストとして、透析患者の全身管理を請け負う
お一人で、たくさんの診療科を担当されている方だと伺いました。

専門は腎臓内科なのですが、当院に来られる透析患者さまの全身管理を担いたいという想いから、「何でも屋さんになる」という発想に至りました(笑)。もちろん、専門外のスキルを学ぶのは簡単なことではありません。ですが、当院では泌尿器科が専門の父や、皮膚科を専門とする勤務医の先生が診療を行っていましたので、素晴らしい恩師に恵まれた環境でスキルを磨くことができました。毎日新しいことを勉強できるのはとても楽しく、今も楽しく診療しています。現在は内科と腎臓内科を中心として、曜日や時間によっては皮膚科や泌尿器科も担当するという体制です。医師は合計7人で、各診療科に女性医師が在籍しています。女性が行きにくいといわれる泌尿器科にも、父と二人三脚で診療していたベテランの女性医師が勤めていますし、2025年4月からは私の妹も泌尿器科の診療に加わりますので、女性の患者さまも安心して受診できるのではないでしょうか。
診療所の歴史についてお聞かせください。
1978年に、私の父が開業しました。以前は3階に住まいがありましたので、ここから学校へ通っていた頃の私を知っている患者さまもいらっしゃいます。中には、開業当時から50年近く勤めているスタッフもいますね。3階を透析室にリニューアルしたのは、約20年前のことです。地域の需要に応えて増築工事を重ねた結果、ベッド数57台の透析室が完成しました。父の専門は泌尿器科でしたが、昔は腎臓内科ではなく、泌尿器科の医師が透析治療を行っていたんです。患者さまのためなら昼夜を問わず出かけていく父を見ながら、私も医師という職業や、腎領域の診療に興味を抱きました。父はとてもバイタリティーのある人間で、診療前の早朝から釣りへ出かけたり、診療後に医師仲間と野球をしに行ったり。そんな、のびのびと働く姿にも憧れを覚えました。
先生のご経歴についても伺えますか?

大学は兵庫医科大学に進学しました。父を通じて交流があった腎臓内科の先生が、ちょうどこの大学の教授に就任されたことが大きな理由です。卒業後は兵庫医科大学の人工透析部と救命救急センターで研修を受け、その後は「腎臓内科の医師たる者、ジェネラリストであれ」という恩師の教えから、神戸市の市中病院に入職。透析患者さまを診るためには、さまざまな病態に応じる必要があると身をもって学んだのが、この頃です。一般的な風邪症状から、急性心筋梗塞まで幅広く治療を経験した後は、香川医科大学(現・香川大学医学部)の大学院へ進学。高血圧症や腹膜透析などの研究に取り組み、さらに腎臓病研究で知られる医師がいた久留米大学へと国内留学しました。臨床医ではなく、研究医としての日々を過ごしたことで、物事を深く考える力や姿勢を身につけられたと思います。2013年4月に帰郷した後は、父の急逝に伴い8ヵ月ほどで院長に就任しました。
入院治療にも対応する、地域に根差した診療所
院長就任から10年以上たちますが、振り返ってみていかがですか?

当院はこの高松町という地域に根差した診療所ですので、その役割や責任を果たすことに力を尽くしてきました。いざという時に寄り添えるように、まずは誰もが訪れやすいような雰囲気づくりを心がけ、腎疾患の予防・啓発を目的とした、地域での市民講座も積極的に開催してきました。最近は近隣の保健師さんからお招きいただく機会も増えましたが、まだまだ「慢性腎臓病」と聞いても首をかしげる人が多く、この疾患の治療や、治療を行う必要性についての認知が広まっていない状況です。慢性腎臓病の背景には、生命を脅かすような複数の疾患が潜んでいるかもしれません。腎臓の機能低下を予防するための治療をきっかけとして、合併する疾患を早期に見つけ出し、その症状が悪化するリスクを減らしたいと願っています。
先生が担当されている診療科の主訴を教えてください。
内科であれば、高血圧症や糖尿病などでしょうか。その中には、慢性腎臓病が隠れていることも多いです。年齢別に見ると、若い方は健康診断の精密検査、ご高齢の方は原因不明の倦怠感などを理由によく受診されています。腎臓内科では、腎疾患の症状として足の腫れを訴える方が目立ちますが、尿が泡立つ、尿に血が混じるといった自覚症状で来られる方もいらっしゃいますよ。皮膚科の主訴はかゆみ、やけど、外傷、ニキビなど、本当にさまざまです。患者さまの年齢層も幅が広く、下は0歳から、上は100歳以上まで。泌尿器科は男性の患者さまがほとんどで、最も多い症状は頻尿です。ご高齢の方は、何度もトイレに行くことが転倒のリスクにもつながりますから、「この年齢だから」と納得してしまうのではなく、もっと積極的に受診していただければと思います。夜中のトイレの回数が軽減できれば、生活の質は少なからず向上に向かうはずです。
これから、より精力的に取り組んでいきたいことはありますか?

今はマンパワーが足りない部分がありますが、救急医療に対応する体制を強化したいと考えています。当院には開業当時から19床の病床がありますので、入院が必要な救急患者さまを受け入れることが可能です。本当に困っている患者さまを私たちが受け入れ、一次・二次救急の受け皿になることで、最後の砦となる三次救急を守りたいです。有床診療所は全国的に減少傾向にあり、この地区も有床診療所の数が激減してしまいました。私としては、「ここが、この地区の診療所の最後の砦」という気持ちで救急患者さまを迎え入れています。
明るく楽しく、健康に人生を送ってほしい
高齢者医療も、取り組むべき課題になりそうですね。

そのとおりです。時代は、超高齢社会となりました。私たちはこの地域の中で、ご高齢の方が安心して暮らせる環境づくりに取り組まなければなりません。そのためには、通院患者さまの体力づくりも必要です。私自身は内科が専門で、運動機能の回復をめざす場を提供できていなかったのですが、今はリハビリテーションの重要性を痛感しています。今後は整形外科の診療所やデイケアなどと連携しながら、一人でも多くの患者さまを元気にして差し上げたいです。患者さまが元気になるためには、「未病の段階から自分の体を守る」という患者さまの意識も必要ですから、教育活動にも引き続き力を注いでいきます。
先生の診療のモットーを教えてください。
透析患者さまとは特に長いお付き合いになりますので、打ち解けた関係性を築くことを心がけています。医療機関では、どうしても「ここは病院だから」「相手は医師だから」と、心の距離をつくってしまう患者さまが多いでしょう。ですが、私たちはそれを望んではいません。例えるなら、ご近所さんとお話しするような感覚でいいんです。何でもお話をする中で、その方が求める医療やサービスを適切に把握しながら、皆さまが安心できる最良の治療、模範的医療を提供していくこと。それが、当院の診療理念です。60人近いスタッフも、常日頃からこの理念を共有し、実践してくれていると思っています。
最後に、読者へのメッセージをどうぞ。

皆さまが、最後まで明るく楽しく健康に人生を送られることを心から願っています。患者さまの元気なお姿を見ることが、私の毎日の励みです。数ある治療の中でも、透析治療は命を預けるに等しい行為であり、医療者にも大きな責任が伴います。私は患者さまと、本当の家族のような関係性を築きながらさらにスキルを磨き、そして最後までともに力を合わせて、患者さまの人生に寄り添いたいと思います。






