西 智奈美 理事長の独自取材記事
田村医院
(奈良市/新大宮駅)
最終更新日:2024/08/09
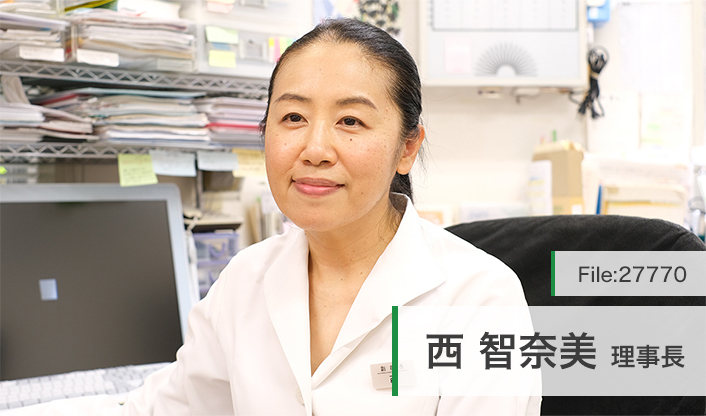
「田村医院」は1977年開業の半世紀近い歴史を持つクリニックだ。同院の理事長である西智奈美先生が、父の田村和夫先生とともに同院での診療にあたり22年がたつ。3世代、4世代にもわたって長年通い続ける患者も多く、近隣住民から「相談しやすいクリニック」として親しまれている。西先生自身もこの町で育ち、「ご近所のおじいちゃん、おばあちゃんたちにお世話になった愛着のある地域」と話す。内科と小児科を診療し、患者の体調不良や健康不安の相談に親身になって耳を傾け、受け止め解決へと導く。町のホームドクターとして尽力することを何よりも大切にする西先生に、地域に深く根づいた医療提供へかける思いと、クリニックの描く未来像について話を聞いた。
(取材日2024年7月17日)
ホームドクターとして診療する父の姿に憧れて
西先生はお父さまである田村先生とこちらで診療されているとのことですが、そのきっかけを教えてください。

石川県金沢市にある大学を卒業した後は、金沢市内の病院や奥能登地域にある医療機関で勤務していたのですが、結婚し出産を機に22年前に地元奈良に戻ってきました。もともと父が開業した当院を継承したいと思い医師を志望したこともありますし、何より奈良の街が好きなんです。ここには子どもの頃から住んでいましたので、この街に育ててもらったようなもので、外で遊び回るのが好きな子どもだったこともあって、近くに住む皆さんにはよく面倒を見ていただいていましたね。なので、この辺りは思い入れや親しみが深いですし、この地域で診療にあたることで地域の方々に恩返しができればうれしいです。
やはりお父さまの姿に憧れて、医師をめざされたのでしょうか。
父が当院を開院したのはこの辺りに住宅が建ち始めた時期で、地域には子どもがたくさんいました。そんなこともあり夜中も自宅に電話がかかってきては診察に行く、そんな父の姿を見て育ちました。「大変そうだな」と思っていましたが、それでも地域の皆さんから頼られるかかりつけ医に私もなりたいと、医師の道を志望しました。もともと、父は「患者さんの家族のような気持ちで診療したい」と思い当院を開業しましたし、父の生きざまはまさに「ホームドクター」の言葉がぴったりとあてはまりますね。ずっと、父のように小さいクリニックで地域の人たちを診察する医師になりたい、という気持ちがありました。
スタッフの皆さんと共有している想いはありますか?

患者さんは困り事を抱えて受診されているので、寄り添って優しく接しようと伝えています。そして気持ち良く笑顔で帰っていただけるようにみんなで頑張ろう。そんな思いで毎日診療していますね。スタッフもみんなその気持ちをもって勤めてくれていると思います。長年勤めてくれているスタッフも多いため、患者さんとも仲良くなっていることが多いです。患者さんも関係性ができていれば、思いついたときにスタッフに相談することで、言いたいことをきちんと伝えられると思いますし、緊張して忘れてしまうことがないように、友達や家族と話す感覚で、思いついたら相談できる環境作りをしていきたいと思います。長く勤めてくれているスタッフだからこそできることですね。
長年変わらず、患者の一番近くで健康を支える
内科と小児科の診療は、どのように行われているのでしょうか。

私と父2人で内科と小児科の両方を診察しています。今では内科は内科、小児科は小児科と、それぞれを専門とするクリニックが多いように思いますが、父が当院を開業した50年ほど前は両方に対応するクリニックが多かったのです。そのため当院では今も地域の皆さんが慣れ親しんだスタイルで、内科と小児科の両方の診療にあたっています。ですので、子どもから大人まで困ったことがあれば何でも相談していただきたいです。このクリニックで賄いきれない部分に関しては、適切に近隣の医療機関へ紹介して、連携を取りながら診療しています。
来院される患者さんにはどういった方が多いのでしょうか。
患者さんは昔から通ってくださる方が多いですね。父が若い頃診ていた患者さんのお子さんが大きくなって、さらにそのお子さんも来てくださるなど、3世代4世代で通ってくださる患者さんもたくさんいらっしゃいます。年代としては、お若い方が風邪などで来院されることもありますが、最近は思春期のお子さんが起立性調節障害や不登校の悩みで来院されることもあります。しかし一番多いのは、やはり中高年の患者さんの生活習慣病の管理ですね。どの疾患でも内科で対応ができるものに関しては当院でも診療していますし、より専門性を要する場合は適切な医療機関につないでいますので、困ったことがあれば何でも相談していただきたいです。
まさに地域に寄り添ったクリニックという印象ですね。地域とはどのような関わりを持たれていますか?

私は母校の小学校の校医も担当しています。実はこの地域の小学校ができた時、私は第1期生だったんです。そのこともあって、今も母校に貢献できていることがうれしく思いますね。また、この10年ほどでこの地域でも病診連携の体制がかなり進歩しました。当院は夜20時まで診療していることもあり、どうしても夜間救急の部門のある医療機関に患者さんを送らなければいけないケースも考えられますので、近隣の医療機関の後方支援をお願いできる関係性を築きながら診療しています。また精密検査が必要になった場合には、ここからほど近い奈良市総合医療検査センターへの紹介と予約の対応を行っています。検査後の結果についての説明は当院でお伝えしますし、その後のフォローもお任せください。
夜間の診療や院内処方を、長年続けていらっしゃるのはなぜでしょうか。
これまでずっと当院では院内処方を採用してきました。ご体調の悪い患者さんにとって、医療機関を出てから薬局に行かなくてはならないのはお骨折りではないかと考え、その負担に配慮するために院内処方をしています。患者さんのために当院でできることは取り組み続けたいと思います。開業当初から変わらず夜は20時まで診療をしていますが、これも院内処方を導入しているからこそできることですね。夜遅くなるとどこの調剤薬局も閉まってしまうので、お薬を受け取れるのは翌日以降になってしまいます。夜間に診療していて院内でお薬を受け取れますので、お仕事帰りに立ち寄ってくださる患者さんも多いですね。
これからも「相談しやすいクリニック」として
診療の中で先生が大切にされているのはどのようなことでしょうか。

患者さんのお話を、とにかく親身になってよく聞くことを大切にしています。お話を伺って「問題はなさそうだな」と思うこともあるのですが、一見異常がないように見えても訴えによく耳を傾けて突き詰めて考えてみると、問題が見つかるケースもあるのです。すぐに診断につなげることができなくても、後から判明することがあると肝に銘じて、まずは患者さんのお話を100%受け止めることを大切にしているんです。その上で、このクリニック内で完結できることなのか、専門医院を紹介するのか、最善を考えて方針を決めていきます。ですので、小さなことでも気兼ねなく話していただきたいと思います。
これからの展望をお聞かせいただけますか。
今のように患者さんから親しみを感じてもらって、なんでも言いやすいし聞きやすい、相談しやすいクリニックを続けていくことが目標です。「ここに来たらなんでも聞けるね」と患者さんから変わらず思ってもらえるクリニックをめざしています。大きな病院で提供されるような医療システムに対応しているわけではありませんが、当院でできることは当院で対応して、できないことは適切な医療機関におつなぎしています。利便性のためにだんだんとデジタル化を取り入れることはあっても、中にある医療の本質は変わらない、そんなクリニックでありたいです。
最後に読者へメッセージをお願いします。

ご自身の健康の問題で困ったことがあれば、相談に来ていただきたいです。体調不良への不安やストレスを抱えて来院される患者さんが多いので、スタッフ一同明るくコミュニケーションを取ることでリラックスしていただき、少しでも問題解決に結びつけていけるよう頑張りたいと思っています。また、小児のワクチン接種や乳児健診も対応していますし、日頃から通院されている患者さんの来院が難しくなれば、訪問しながら継続して診療も行っています。患者さんを最期まで診ていく姿勢を、これからも続けていきたいと考えています。






