西村 吉明 院長の独自取材記事
西村クリニック
(奈良市/新大宮駅)
最終更新日:2024/06/03

近鉄奈良線・新大宮駅から徒歩10分。「西村クリニック」は、大通り沿いに面したビルの2階にある。院内処方のための薬棚や心電図検査室、婦人科の内診室など、適切な診療に必要な設備を十分に備える。待合室はたくさんの光が差し込むよう設計され、居心地の良い空間だ。インフォームドコンセントを大切にし、患者とのコミュニケーションを何より大切に考えると話す西村吉明院長。医師となったきっかけや転機、子宮がん検診の重要性、プライベートや患者に対しての誠実な思いまでを、たっぷりと話してもらった。
(取材日2024年4月15日)
開業から35年、世代を問わず多くのニーズに対応する
まずはクリニックについて教えてください。

当院は1989年に開業しましたので、もう35年ほどの間診療を続けていますね。現在は内科、婦人科、皮膚科と3つの診療科を標榜しています。内科は6〜7割ほどで、残り3〜4割が婦人科と皮膚科の患者さんですね。年齢層は若い方から高齢の方までさまざまです。内科の場合は、後期高齢者の慢性的な疾患をよく診療しています。一方で30代などの若い方も、風邪や腹痛などの一時的な疾患でいらっしゃいます。おおよそ半数は近隣地域の方ですが、もう半数は他の地域の方です。当院は駅からは徒歩10分ほどの距離がありますが、大通りに面していることもあり、職場が近い、あるいは通勤経路の方も通院しやすいようですね。
3つの診療科を標榜され、幅広い診療をされているのですね。
開業当初から内科・皮膚科・婦人科を診療するクリニックでした。開業当初は当院に面した道路は一車線で狭く、ビルの2階にあるため患者さんが来院されにくかったのですが、ビルにエレベーターが設置されたことで高齢の方にも来ていただきやすくなりました。内科の患者さんは、特に生活習慣病と呼ばれる高血圧症や糖尿病、脂質異常症などで通われる方が多いです。婦人科や皮膚科の患者さんの中には、他の人に言いたくない、ばれたくないと他の方の目を気にされる方もいらっしゃいますので複数の診療科を標榜することで診療に心理的ハードルのある方も受診しやすくなったことは良かったと思っています。
診察の際に特に大事にしていることは何ですか?

基本的なことではありますが、病気の原因を探るにあたって、何に一番困っていらっしゃるのか、患者さんのお話をきちんと聞くことが大切だと考えています。痛みや不調の経過を筋道を立てて上手にお話しくださる患者さんもいれば、中にははっきりした要因が思い浮かばず、うまく言葉にすることが苦手な患者さんもいらっしゃいます。病気には何かしらの原因がありますので、まずは不調がいつ頃から始まったのかを聞くことから丁寧に始めます。その際に最も注意していることは「背景に重大な病気が隠れていないかを見逃さない」ことです。例えば胸がぐっと苦しくなるという症状には、更年期障害の可能性や、狭心症の可能性など複数の病気が隠れていることもあります。命に関わる疾患を見逃さないことを第一に考えて、日々診療にあたっています。
恩師に促され入った医学部、先輩に導かれた婦人科の道
医師を志した理由について教えてください。

学生の頃から勉強は理数系が得意で、特に数学が好きでした。当初から医者になろうと思っていたわけではなく、大学も医学部を受けたのは1校だけ。当時の担任の先生に強く勧められたことがきっかけでした。当時、水俣病や四日市ぜんそくなどの公害が社会問題として話題になっていたこともあり、他大学の環境工学科に進もうかと迷っていましたが、家族が病気になったら自分がサポートしてあげたという想いが芽生え、医学部に進むことにしました。専門とする診療科を迷う中、大学時代仲の良かった先輩が当時の婦人科部長で「手術の手伝いが上手だから、うちに来る気はないかね」と声をかけてもらったことをきっかけに婦人科を選びました。
その後、勤務医としてご経験を積まれたのですね。
卒業後は大阪市内の病院に約10年勤めました。その間、私は自分の子どもを勤務先の病院で自分の手で取り上げました。当時は医師になって7年目くらいで少しずつ自信がついてきた頃でしたが、1人目の時は妻の出産がなかなか進まないことに焦って、いろいろな可能性やリスクを考え、それに対応するため普段はやらないような処置および対応を考えて備えていました。その際、当時いた病院のベテランの先輩医師が「そんなに心配しなくて大丈夫、もっとゆっくり自然の経過を見たら」とアドバイスをしてくれたことを今でもよく覚えています。医学的知識や技術的な処置について万全を期することは当然ですが、この経験からすべての患者さんを自分の身内を診るように丁寧な気持ちで診よう、どのような時も、最善を尽くしたと思えるように誠意をもって診察しようという思いを強く持つようになりました。その後、縁があってこの場所で開業することとなったのです。
お休みの日はどのように過ごされていますか?

学生時代は野球をしていましたが、医師になってからはあまり運動をせず、休みの日も仕事を片づけたり論文を読んだりして過ごすことがほとんどでした。しかし、友人に誘われて数年前から山登りを始めました。最近は真夏と真冬以外はほぼ毎月登山をしています。近くの生駒山から始まり、二上山や大和葛城山、最近は月ヶ瀬や吉野のほうに足を延ばすこともあります。特にお勧めしたいのは、標高1235mの三峰山です。頂上の景色も良いですが、そこから少し下ったところにある八丁平と呼ばれる場所の景色は筆舌に尽くしがたく、登山をしたことがない方も一度は登っていただきたい場所ですね。
患者の利益のために全力を尽くす
患者さんに接する上で、特に気をつけていることは何ですか?

原因を追求していくことで根拠を示し、患者さんに納得していただいた上で治療を進めることを心がけていますね。例えば婦人科にいらっしゃる患者さんには「更年期障害の症状がつらい」と来院されることがあります。現在は、インターネットで調べて来院される方も多いので、火照りや動悸といったホットフラッシュの症状だと思い更年期だと思われるのかもしれません。しかし、その不調が本当に更年期のホルモンバランスの崩れによるものなのか他に原因があるのかは、ホルモン検査によって具体的な数値を見ないとわかりません。ホルモンの値に異常がないのであれば、更年期障害ではない他の要因を疑い、次の治療を考えていくことが重要です。このように、きちんと原因の追究することで、患者さんご自身も安心して治療に臨めると思っています。
定期検診などもされているのでしょうか?
はい。最近は子宮頸がんの検診に来られる若い方も増えました。子宮頸がんは、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染が原因であることがわかっているのですが、数十種類あるそのウイルスのうち、子宮頸がんの原因となるものは約10種類が98%を占めるといわれています。日本では年間におおよそ1万人の方が子宮頸がんに罹患し、3000人弱の方が亡くなっています。がんになる前の予備軍の方も含めるともっと多くの方がいるでしょう。子宮頸がんにより大変な思いをされ、中には子どもが望めなくなる方もいらっしゃいます。また、どんどん若年化していて、ピークは30歳代後半とされる病気です。どうか積極的に検診に来ていただきたいと思いますね。
最後に、クリニックの理念を教えてください。
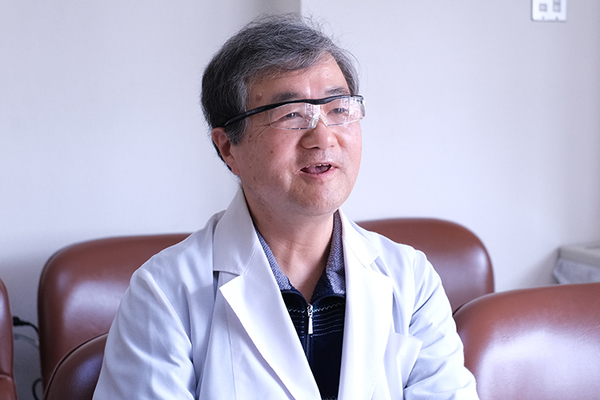
やはり、患者さんとのコミュニケーションを大事にしていますね。患者さんが何を求めていらっしゃるのかを十分に理解して、大きなことから小さなことまできちんと丁寧に説明をして、ご納得いただくまで言葉を尽くし、その上で治療を行うことを大事にしています。また、患者さんの体の中が今どういった状態なのか、どんな流れで治療を進めればその人をより健全な状態へと導けるのかといった病態生理学の考えから、論理的に診断することもモットーの一つです。まだまだ患者さんのために診療を続けたいという思いは持ちつつも、私も70歳になりました。思いを引き継いでくれて、医学やデジタル機器の進歩に柔軟に対応できる次世代への継承の準備も進めていきたいと考えています。






