久保 知一郎 院長の独自取材記事
久保医院
(八尾市/八尾南駅)
最終更新日:2021/10/12

八尾南駅から車で約5分。太田エリアの住宅街にある「久保医院」は、久保知一郎院長の父である研二先生が1983年に開業して以来、地域のかかりつけ医として幅広い世代に親しまれてきた。内科と小児科、循環器内科を標榜している同院は、外来診療に加えて在宅医療にも対応し、通院が難しい患者のサポートにも注力している。「高齢化がいよいよ進む中、在宅医療の選択肢を視野に入れた上で、介護のことも含めて気軽に相談してほしい」と考えている久保院長。診療では多職種間での連携を大切にし、一人ひとりに合ったオーダーメイド治療を提供することを心がけている。そんな久保院長に、現職に就任した背景や在宅医療にかける想い、今後の展望などについて、たっぷりと話を聞いた。
(取材日2020年7月8日)
在宅医療に注力し、病気とうまく付き合える医療を提供
まずはじめに、これまでのご経歴について教えてください。

大学を卒業した後は大学病院や総合病院に勤務し、研修医としてさまざまな診療科をローテーションしたこともあって、幅広い経験を積めました。循環器内科の専門の医師として勤務するようになってからも、心臓に特化しながら消化器内科や呼吸器内科、小児科など、循環器以外の内科診療をする機会が多くありました。患者さんが元気になって自宅に帰る姿を見ると、「担当してよかった」とやりがいを感じていましたが、その一方で、これからの時代は「病気を治すこと以上に、病気とうまく付き合っていくこと」を重視しなくてはならないという考えもありました。高齢化が進む日本においては、慢性疾患と長期的に向き合っていく必要性があり、加えて「最期は自宅で迎えたい」と願う患者さんの多さを目の当たりにしたのです。それをきっかけに、病気を治す医療だけではなく、患者さんの要望をかなえられる地域に密着した医療に興味を持つようになりました。
どのような経緯でこちらの医院で診療することになったのでしょうか?
地域密着型の医療に魅力を感じ、「地域のかかりつけ医として貢献したい」と考えるようになってしばらくして、もともと開業医として診療に従事していた父を手伝うようになりました。地域に根差した医療を提供し、医師会でも積極的に活動していた父の姿を幼い頃から見ていたこともあって、僕自身も同じようになりたい気持ちが強くなり、2011年に副院長に就任したのです。当院で診療するようになって今年で9年目ですが、生まれ育った地で地域医療に携われていることにやりがいを感じています。
注力している診療内容はありますか?
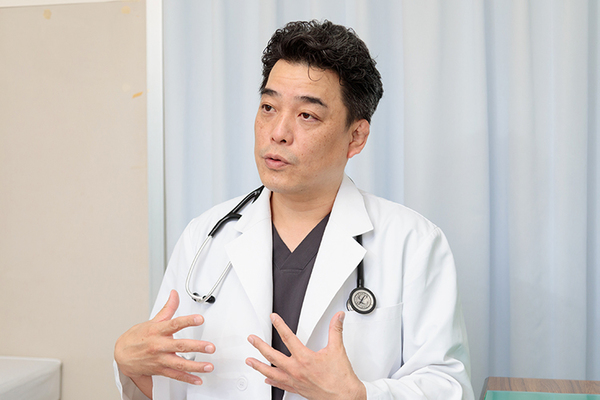
地域医療を担う開業医として、当院では在宅医療にも注力しています。昔から通院してくださっている患者さんとはこれからもお付き合いしていきたい一方で、年を重ねるとどうしても通院が難しくなってしまいます。在宅医療への介入が欠かせないと思い、当院は外来診療と在宅医療の2本柱で診療を実施しています。在宅医療の対象は、がん患者さんや高齢で通院が難しい方、難病をお持ちのお子さんまで、多岐にわたります。365日24時間体制で対応していますから、ご本人やご家族が在宅医療を必要だと感じている場合は、どんなことでも気軽にご相談ください。
患者一人ひとりに合った「オーダーメイド治療」を
注力されている在宅医療についてお聞かせください。

当院で実施している在宅医療は、がん患者さんや難病をお持ちの患者さんなど、通院が難しいけれど治療が必要な方を対象としています。病院と並行して当院の在宅医療を活用してくださっている方、ターミナルケアを希望されているがん終末期の方も多くいらっしゃいます。すでに病院を受診していて、がん治療を受けている患者さんの場合は、治療中の痛みを緩和することが主な目的とし治療を行います。がん終末期の患者さんだと、緩和ケアを中心とした医療となりますね。どの患者さんに対しても、住み慣れた環境で残された時間を過ごせるよう、医師と看護師のほか、ケアマネジャーやヘルパーなどが連携し、患者さんの要望に寄り添ってサポートしています。患者さんの症状は日々変化し、早い段階で対処することが求められるので、職種間で連携しながらもそれぞれの視点から介入することが大切です。
職種間連携も欠かせないのですね。
在宅医療は、医師1人の視点だけで成り立つものではありません。看護師やケアマネジャー、ヘルパーの存在が必要不可欠で、互いの視点を生かした連携がとても重要なのです。患者さんの要望をかなえるには、病気に関すること以外も含めて、各視点から得た情報をスタッフ全員で共有することが必要です。そのため当院では、治療に関わること以外であっても、些細な情報もすべて共有するようにしています。医師が見えているのは患者さんの生活のほんの一部なので、スタッフ間で意見交換し、患者さんとご家族も含めて在宅医療の方針を決めています。
在宅医療において大切にしていることはありますか?

在宅医療には決まった形がなく、患者さん一人ひとりに対する治療法がすべて異なります。一人として同じ状況の方はいらっしゃいませんから、オーダーメイド治療を提供することが大切だと僕は考えています。そのために、患者さんとそのご家族と密なコミュニケーションを取ることを心がけています。僕たち医師や看護師など、在宅医療を提供する側が考える方針と、患者さんやご家族が希望する方針が違っていては、患者さんは納得して治療に取り組むことができません。ですから、一方的にこちらの考えを押しつけるのではなく、コミュニケーションをしっかり取ることで、納得した治療につなげられるよう努めています。あとは、病院との連携も欠かせないと考えています。時には在宅にこだわらず、病院で治療を受けたほうが患者さんにとってメリットになる場合もあるため、迅速に判断して紹介するようにしています。
患者や家族にとっていつでも相談できる存在でありたい
印象に残っているエピソードはありますか?

在宅医療に取り組むようになってから診させていただいた、がん患者さんのことは今でも忘れられません。体調があまりよくなく、意識がはっきりしていることも少なかったのですが、訪問すると必ず体を起こした状態で、「よく来てくれました」と笑顔で声をかけてくださる方でした。僕ら医師や看護師、ケアマネジャーなどを交えて、みんなで写真を撮ったことがあるほど、家庭や生活の中に入って診療させていただいていたのです。何より、ご本人だけでなく、ご家族もその方の意思を尊重し、前向きに在宅医療に取り組んでいました。最期を迎えたときも「よく頑張ったね」と、家族全員が穏やかな表情でその方を囲んでいた光景が本当に印象的で……。在宅ならではの温かい空間に居合わせることができ、この先も在宅医療に貢献していきたいと強く感じた出来事となりました。
今後の展望を教えてください。
これまでと変わらず、在宅医療に力を入れて取り組んでいきたいと考えています。さらに、この地域にお住まいの皆さんに、「在宅医療の必要性」を伝えていきたいとも思っています。病院への入院や施設への入居といった選択肢に絞らず、自宅で療養できることを知っていただいた上で、どのように治療していくかを決めていただきたいのです。在宅医療で実現できることを積極的にお伝えすることで、われわれが提供できる医療について理解していただきたいと思っています。そうすることで、患者さんやご家族が望む「最期の迎え方」をかなえられるのであれば、僕もうれしいです。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

「いつでも相談できる存在」として、当院で応えられることは何でも対応したいと思っているので、気になることは気軽に相談してください。ご自身についてではなく、親御さんのことでも構いませんので、介護のことも絡めて相談していただければと思います。また、当院は難病を抱えている患者さんの在宅医療にも対応しています。お子さんから高齢の方まで、日常において困っていることがあれば、深く考えずにいろいろな観点からお話ししていただければと思います。






