阪上 博史 院長の独自取材記事
阪上耳鼻咽喉科
(茨木市/茨木駅)
最終更新日:2025/08/04

JR京都線の茨木駅東口から徒歩約3分。住宅街にある「阪上耳鼻咽喉科」は、1951年開業の歴史がある医院。阪上博史院長は父の後を継ぎ、2代目院長として40年あまり診療を続けてきた。0歳から100歳までと幅広い年齢層の患者が訪れるが、コミュニケーションを大事にする阪上院長は子どもにも高齢者にも、さっくばらんに親しみやすい口調で話しかける。団塊の世代である阪上院長は70歳を過ぎた今も、刻々と移り変わる流行の感染症に向き合い、日々知見を深めていく。「還暦を越えてからはいろいろなものへの執着心も薄れ、さらに患者目線での治療を追求するようになりました」と語る阪上院長。診療での心構えや最近多い主訴などについて話を聞いた。
(取材日2022年3月28日)
専門とするアレルギー疾患をはじめ幅広く対応
こちらは、1951年開業と歴史のある医院ですね。

父が開業した医院ですが、私は2代目として33歳の時に当院で診療を始めました。京都府立医科大学附属病院の後、国立舞鶴病院(現・国立病院機構舞鶴医療センター)や京都第一赤十字病院で勤めてからです。父が体調を崩したために、思っていたより早く継ぐことになり、開業医になるには少々若い年齢でした。私が来てから、父はちょっと体調が戻ったので2~3年ほどは一緒に診療しました。自分が生まれ育った場所ですし、患者さんには3世代4世代と続けて来院されているご家族もいて、昔から知っている方が多かったので、診療の引き継ぎはスムーズに行えましたね。基本的には手術をしないので、精神的な負担は軽くなった気がしました。しかし、チームとして対応する大学病院などとは違って、こちらはすべてが自分の責任ですから、プレッシャーはありました。
耳鼻咽喉科でのご専門は何ですか。
アレルギーです。アレルギー性鼻炎や花粉症などですね。特に関心があったというよりは、先輩から「人がいないのでやってくれ」と言われて引き受けたのですが、これが難しい。正直「しまった」と思ったほどです。当時は今ほど、アレルギーについて解明が進んでいませんでした。診療をしながら、論文を読んだり講演会に行ったりして情報を集めましたが、一番ホットな情報が入ってくるのは、会食の席でしたね。大学や大病院の先生たちと食事をして、先進の治療法など情報を仕入れて勉強し、診療の現場で生かしてきました。
こちらへ見える患者さんはどういった方々ですか。

地元の方々の他、大阪や京都などからクチコミで来られる方もいらっしゃいます。年齢層は赤ちゃんから100歳のお年寄りまでと幅広いですね。そのうち小学生までの子どもさんが3分の1強で一番多いでしょうか。それでも少子化で、数としてはひと昔前よりは減りました。その中で鼻炎や喘息を含めたアレルギー疾患の子どもさんが目立ちますが、食生活や環境など社会の変化が関係しているのだと思います。親御さんの教育や病気に対する姿勢も、お子さんに反映され、回復のスピードに差が出ていると感じます。多様な患者さんに応じて、治療も柔軟に対応しないといけないと考えています。
多様化する患者や疾患にも向き合う
最近多い主訴は、なんでしょうか。

高齢の患者さんの難聴が増えていますね。4人に1人がおじいちゃん、おばあちゃんという超高齢社会になりました。年を取ったらいろいろと衰えてきますが、聴覚が衰えると認知症になるのが早まるリスクが高いといわれていますから、補聴器を使うことは必要だと思います。そのため当院では月に1日、補聴器の相談を受ける外来を設けています。補聴器をつけると雑音も入ってくるので、「うるさいから」とすぐに装着をやめる方も少なくありませんが、脳が必要な音と雑音を取捨選択するように慣れるのには、1~2週間の訓練が必要なんですね。なので、テレビをつけたままの部屋で使用するといった、雑音に慣れてもらうためのアドバイスもしています。
診療の際に心がけていることは何ですか。
コミュニケーションを大事にしています。患者さんとたくさん会話をしますね。まずは「こんにちは」とあいさつから始まって、症状だけでなくいろいろな角度から話を伺い、ご本人の治療に対する考え方も理解したいですから、できる限り話を聞きます。私から話すときは、語尾をやわらかく話すようにしています。とはいえ、こちらが迎合するのではなく、診察の結果と対処について、私の考えもしっかりお伝えします。その際、なんでも自分で治そうと「我(が)」を張ることがないようにしています。必要な場合は大規模病院でも検査を受けてもらって、先方の所見と合わせて判断をしていきます。
新型コロナウイルス感染症流行のさなかですが、診療にも変化はありますか。
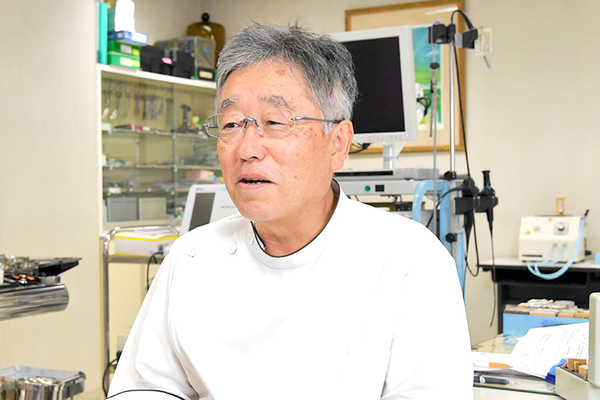
そうですね。当初、受診を控える患者さんはいらっしゃいました。現在、スタッフは皆ワクチンを接種した他、院内での感染症対策も徹底しており、来院される方の不安がないようにしています。慢性疾患の患者さんには、感染症のリスクを考慮して、1回来院されたら1ヵ月分の薬をお出しするようにしています。喉の痛みを訴える患者さんなど、感染症が疑われる患者さんにも対応しており、院内で隔離をして診察しています。
医師として培ってきた知見を生かし地域を支える
医師をめざしたきっかけを教えてください。

耳鼻咽喉科の歯科医師をしていた父の希望です。物心ついた時から「医院を継いでくれ」と言われていました。祖父も大阪市内で泌尿器科医院を開業していましたので、そういう環境だったためか、気持ちの上での抵抗はなかったですね。地元の大阪府立茨木高等学校を卒業して京都府立医科大学に進みましたが、医学部に入ってからも研究はあまり好きではなかったので、大学に残るよりは開業医のほうが向いているという思いもありました。5歳年下の弟も耳鼻咽喉科の医師なのですが、彼は私と違って研究が好きなので、大阪大学を出て研究と臨床を続け、現在は兵庫医科大学病院の病院長として大学病院で診療しています。
大学時代はどのような学生生活を過ごされましたか。
私は1949年生まれで「団塊の世代」でして、大学入学当時は学生紛争が盛んでした。学生の街・京都は特にそうだった気がします。私が通っていた京都府立医科大学がある辺りも騒然としていましたね。4月に入学しましたが、自宅待機が続き、授業が始まったのは10月。その一方で、教授たちはまだまだ封建的でとても怖かったですね。白いものでも教授が「黒」と言えば「黒」と言わないといけないような雰囲気でした(笑)。中学高校では特にスポーツはしていませんでしたが、大学ではサッカー部に入ってポジションはサイドハーフ。タッチライン側にいるミッドフィルダーを務めていました。
今後の展望を教えてください。

私も70歳を過ぎました。開業医には定年がないのですが、今までの経験を生かしながら、継続して地域医療に力を入れたいと考えています。何でも相談できるようにして、相談を受けたらきっちり対応すること、患者さんを大学病院などへ紹介する場合は、うまく連携が取れるように尽力したいと思っています。なので、患者さんのほうも堅苦しい感じにならないように、治療方針に関しても、何でも一緒に話し合いながら治療を進めていきたいですね。60を過ぎた頃から、いろいろな執着がなくなってきて「楽しく仕事ができればいい」という姿勢になってきました。楽しければスタッフも院内の空気も明るくなって、患者さんにも良いことだと思います。これからも、地域の皆さんと仲良くやっていけたらいいですね。






