松田 泰明 院長の独自取材記事
松田耳鼻咽喉科
(大阪市鶴見区/放出駅)
最終更新日:2025/09/09

学研都市線放出駅から徒歩1分の「松田耳鼻咽喉科」。この街で生まれ育った松田泰明院長が父のクリニックを引き継いで29年になる。松田院長は患者の治癒力や生命力を引き出すような治療を心がけ、必要以上に薬に頼らない方針で診療を行う。また、子どもが多く通う同院は0歳児から受診が可能。松田院長は「子どもたちには、僕のほうが癒やされているんです」と、にこやかに話してくれた。漢方薬の処方や花粉症の舌下免疫療法にも取り組み、いつも新しい治療法や機材などについて学び続け、アップデートを続ける松田院長に、日々の診療への想いを聞いた。
(取材日2023年4月19日/更新日2025年9月4日)
花粉症対策として舌下免疫療法を提供
花粉症の治療にも力を入れていらっしゃると伺いました。

今年はかなり花粉の飛散量が多かったようで、この数年来院されていなかった患者さんも多く来院されていました。ここ数年、薬局で購入できる薬も増えているので、セルフケア対応で済ませる方も少なくないのですが、今年はそれだけでは無理だったとおっしゃる方が多かったですね。当院では、抗ヒスタミン薬を中心とした経口内服薬・点鼻薬・点眼薬・テープ製剤などを中心に処方しています。その他、舌下免疫療法の選択も可能です。舌下免疫療法はスギ花粉症とダニアレルギーによる通年性アレルギー性鼻炎にしか使えませんが、今までの投薬治療であまり症状の変化を感じられなかった方は、検討されてみると良いと思います。
舌下免疫療法について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?
舌下免疫療法は、アレルゲン免疫療法の一種で、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少しずつ体内に吸収させることで、アレルギー反応を弱めていくための治療法です。当院では8年前から始めたのですが、3~5年という長いスパンを要する治療で、最近、治療を終えた方が少しずつ増えてきているタイミングです。治療の方法としては、舌の裏側にラムネのような薬を置き、ジワッと溶かす簡単なものですが、少しずつ体を慣れさせていくために、花粉の飛んでいない時期も毎日続けることが必要になります。
継続的に長く取り組む必要があるのですね。
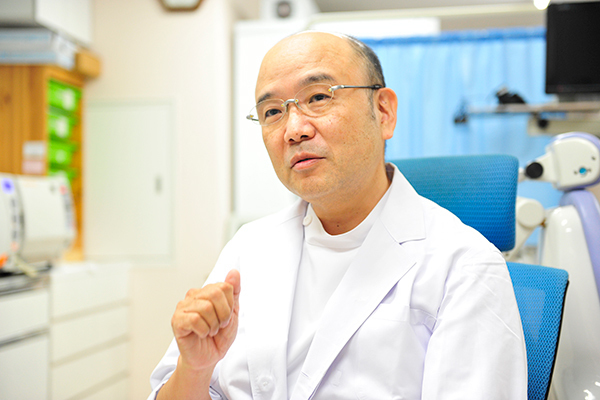
そうなんです。すぐに結果が出るというよりも、年々少しずつ変化して改善をめざしていく、そんなイメージです。毎日の服薬、毎月の通院が必要になるので、そのあたりに困難を感じる方にはお勧めできません。ですので、どんなメリットとデメリットがあるかということをまずはしっかり説明をして、この治療法を選ぶかどうかの選択は患者さんにお任せしています。やる、やらないはあくまでその方次第です。症状の出るシーズンだけ服用する経口内服薬や点鼻薬などと違って、舌下免疫療法の場合は、副作用のリスクがあるため、花粉症シーズン中には治療を開始できません。治療を開始しようと思っても、始められるのは花粉の飛散が落ち着いた夏以降。ですので、それまでの間にじっくり考えて、治療を開始するかどうか検討していただきたいと思います。
患者の持つ治癒力や生命力を引き出すことに尽力
漢方薬も積極的に処方されていらっしゃるとお聞きしました。

漢方薬は西洋薬よりも、バリエーションが豊かで、症状のステージに寄り添いながら、こまやかに対応できるのが魅力ですね。漢方薬は一つの薬で複数の症状に作用するものが多いので、処方する薬を少なくすることが図れる点も気に入っているところです。耳鼻咽喉科を受診される患者さんは不定愁訴のある方が少なくないのですが、そういった症状にも西洋医学の薬よりも漢方薬のほうがマッチすることが多いですね。漢方は、長年の経験則をもとに体系化されているので、例えば、雨の日になるとめまいがひどくなるというような訴えの患者さんに対して漢方薬なら対応ができるんですね。日々勉強してアップデートしながら、より患者さんの症状や希望に添うような処方をこれからも心がけていきたいと思っています。
先生が治療の際に大切にされていることを教えてください。
私は、患者さん自身が持っている治癒力や生命力を最大限に引き出し、自然なかたちで回復へと導くことを理想としています。無理に患者さんの状態を変えてしまわない、ということですね。当院の診療方針で「体と心に優しい診療」を掲げているのはそういうことなのです。また、薬の処方については、必要最低限にとどめるよう努めています。例えば、風邪の多くはウイルス感染が原因であり、軽い症状の場合は無理に薬を出すのではなく、「薬はなくても問題ありませんが、どうされますか?」と患者さんと相談しながら判断しています。さらに、患者さんの症状や不安を言葉だけで伝えるのが難しい場合も多いため、当院では電子内視鏡を用いて、実際に体の中を見ながら症状を理解していただくこともあります。患者さん自身が自分の状態をしっかり把握し、納得した上で治療を進められることをめざしています。
お子さんのために検査体制も整えられたとお聞きしました。
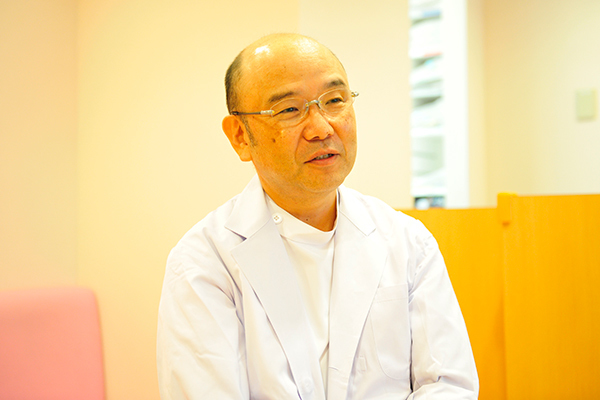
そうですね。当院に来られる患者さんは0歳からお年寄りまで幅広いですが、特にお子さんの割合が高いと感じています。正直にお話しすると、僕自身はもともと子どもの診療が苦手だったんです(笑)。しかし、自分に子どもができてミルクを飲ませたりおむつを替えたりするうちに、だんだん子どもたちのかわいさにふれ、接し方も変わってきました。お子さんへの想いを大切にしながら、当院では注射針を使わずに指先からのわずかな血液一滴で検査ができるドロップスクリーン検査によるアレルギー診断の環境を整えました。お子さんがほとんど泣かずに安心して受けられるのが特長です。 また、検査時間も短く、約30分で結果が出るため、当日に結果をお伝えでき、再診の手間もかかりません。お子さんや親御さんの負担をできるだけ減らしながら、適切な診断を心がけています。
すべては患者とより良い治療のために
ここ数年で感じていらっしゃる変化などはありますか?

今は、インターネット上にたくさん情報があって、患者さん自身もあふれる情報の中で不安や疑問を逆に深めてしまっている部分があるように思います。思い込みの中で悩みを深めずに、まずは気軽に来院して相談していただきたいと思っています。こちらがこの治療がいいと思っても、患者さんが納得されるかどうかはまた別なので、患者さんの本音を知りたいという思いもありますね。医師には本音をなかなか言いづらいという患者さんもおられると思うので、もし僕に話しにくい場合はスタッフに話してもらえたらうれしいです。
授乳中の方からのご相談も多いのですね。
はい。特に「妊娠中は薬を飲んではいけない」と思い込んで、体調が悪くても我慢してしまっている方が少なくありません。妊娠中でも使える薬はありますし、最近では信頼できる研究データも増えてきています。授乳中についても同様で、使用可能な薬は意外と多いんです。当院では、妊娠中の方には「この薬は基本的には大丈夫ですが、念のため産婦人科の先生にも確認してみてくださいね」とお伝えするようにしています。専門の先生と連携しながら、安心して治療が受けられるよう心がけています。つらい症状を無理に我慢するよりも、まずは相談してみてほしいです。我慢しなくてもいいところまで耐えてしまう方もいて、それはきっと心身ともにきついですから、不安なことがあれば一人で抱え込まずに、まずは気軽に相談してもらえたらと思います。
読者へのメッセージをお願いします。
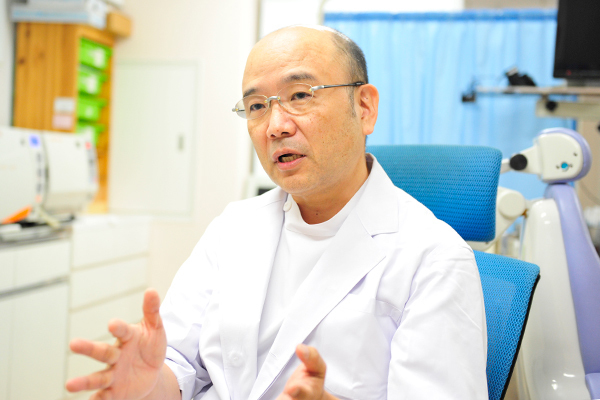
来院くださる患者さんのためになるように、日々幅広く情報収集に努めています。医師の仕事は、毎日がテスト問題を解くようなものだと感じています。患者さんの症状や背景にあるものは、皆さん一人ひとりまったく違うため、同じ症例というのは存在しません。医師にとって患者さんの診療は、毎回違うテストを受けているようなものです。そしてテストを解くには、やはり勉強が必要です。ツールや知識、技術など、あらゆる面でアップデートしていかないと、最適解を導き出すことはできません。だからこそ、学びを止めることなく、これからも成長し続けたいと思っています。また、より患者さんが来院しやすいように、SNSからの予約体制も整えました。忙しい方でも、スムーズに予約していただけます。皆さんのお役に立てるよう、今後も研鑽を積んでまいりますので、何かお困り事や気になることがあれば、いつでも頼っていただきたいですね。






