福井 宏有 院長の独自取材記事
医療法人修真会 福井整形外科
(大阪市淀川区/東三国駅)
最終更新日:2025/09/08

開業から約半世紀にわたり、地域に慕われ続ける「医療法人修真会 福井整形外科」。院長の福井宏有先生は、日々の診療にとどまらず、乳児の股関節脱臼の早期発見や骨粗しょう症検診の推進活動にも精力的に取り組んできたドクターだ。学生時代にはイギリスやドイツなど、ヨーロッパ各国の病院で学びを深め、その当時の思いを現在の医療活動にも生かしているという。福井先生の経験や実績は、より良い医療のために誠意と勇気をもって関わったものばかりで、話を聞けば聞くほど実直で優しい人柄が伝わってくる。待合室の一角にある「お座敷コーナー」は、患者に愛される癒やしの空間。そこで、学ぶ姿勢を忘れない診療スタンスについて話を聞いた。
(取材日2017年8月2日)
欧州の医療現場で学び、そこで得た情熱は今も胸に
まずは、クリニックの特徴をお聞かせください。

1980年に開業した当初は、23床のベッド数を備えた有床の診療所としてスタートしました。今は外来診療のみですが、以前は通院治療だけでなく入院治療にも対応していたので、24時間365日、それこそ盆も正月も休みなしで診療していました。「朝8時から夜20時まで、診療時間が長くて先生大変じゃないですか?」と、患者さんに言われることがありますが、昔に比べたら今は楽をさせてもらっています。その当時は、救急医療の受け入れも行っていたので、交通事故の患者さんが救急車で搬送されてきて、即手術ということもありました。裏口に救急車が入れるスペースを今も確保しているのはその名残です。
学生時代に行かれた海外講習が、医師人生に大きな影響を与えたそうですね。
整形外科はイギリスが発祥地といわれ、ボーンセッター(接骨の術者)と看護師が医療に取り入れたのが始まりだとされています。自分の専攻する科が誕生した場所を、学生のうちに訪れてみたいと思い、1人でイギリス、イタリア、フランス、スウェーデン、ドイツを巡って、ヨーロッパ諸国の名の知られる病院に講習に行きました。わずか4ヵ月間だったとはいえ、とても貴重な経験となりました。ちょうどヨーロッパにいる時に、アポロ11号が月面着陸を果たし、院内のテレビに釘づけになりながら、欧州の医師たちと大いに盛り上がりました。「ヨーロッパもアメリカも、こんなに進んでいるんだ。よし、僕も日本に帰ったら頑張ろう!」そんな熱い思いを胸に帰国しました。
大学ではどのような勉強をされたのですか?

当時の教授が「現場で学べ」という方針だったこともあり、大学に戻ってからは、積極的にいろいろな病院に行って経験を積みました。夏休み、冬休み、春休みのほとんどは、病院に泊まり込んでいましたね。スキルアップのためなら休日がなくても惜しいとは思わず、自ら志願して整形外科以外の科にも飛び込みました。おかげで、産科のお産に何度も立ち会ったり、小児整形外科や脳外科では、とても多くの実績を残されている先生方の手術につかせていただく機会にも恵まれました。記憶に残っているのは、大学6年生の時に行った脳外科の講習です。頭を打った数日後に、認知症の症状が出た患者さんがいました。CTもMRIもなく、今のような精度の高い検査ができない時代でしたが、慢性硬膜下血腫という病気が背景にあるとわかったことで、適切な治療につながりました。覚悟を決めておられたご家族が、涙を流して喜ばれていた姿が今も忘れられません。
学べる場所がないのなら、自分たちがつくるしかない
法医学や救急医療も熱心に勉強されたそうですね。

大学卒業後に法医学を学び、医療と法の接点や問題点について勉強しました。診療に直接的に関係するものだけでなく全体的な体系を理解しておくことが、より良い医療を提供するために必要だと感じていたからです。また、有床診療所を開業するにあたって、診療科に関係なく事故や急病の人を診療し、重症な場合は救命救急処置を行う救急医療の知識が不可欠だと考えました。しかし40年以上前ですので、当時は救急医療の仕組みが整っておらず、学べる場所はありません。そこで、同じ志を持った医師同士で協力し合って、南千里に大阪府立千里救命救急センター(現・済生会千里病院千里救命救急センター)を立ち上げたのです。救急医療に精通した先生をお招きして研修会を開催すると、全国からたくさんの先生が勉強に来られました。教授・助教授クラスの先生も多く出席されており、その方たちは大学に戻られてから救急医療部門の設立に貢献されていましたね。
乳児健診の股関節検査にも精力的に取り組まれたそうですね。
整形外科は英語で「オルソペディックス」と言います。オルソは「治す」、ペディックスは「小児」という意味で、もともと整形外科は、子どもの三大疾患である「先天性股関節脱臼(こかんせつだっきゅう)」「筋性斜頸(しゃけい)」「先天性内反足(ないはんそく)」を治すところからスタートした科なのです。股関節脱臼の検査は、赤ちゃんの3~4ヵ月健診の重要項目の1つです。昔は治らない病気とされていましたが、今は治療技術が進み、早めに治療していけば治癒が見込めるようになりました。股関節は僕の得意分野なので、ボランティアで乳児健診を手伝うだけでなく、検査データをもとに統計を割り出すなど、股関節脱臼の早期発見に積極的に取り組みました。子どもの病気は早期治療で治癒が望めるものが多く、正しい治療によってその子の未来は広がるはず。もし僕が整形外科以外の道を選んだとすれば、小児科に進んでいたのではないでしょうか。
院内全体に温かみがあって、特に待合室は居心地が良い空間ですね。
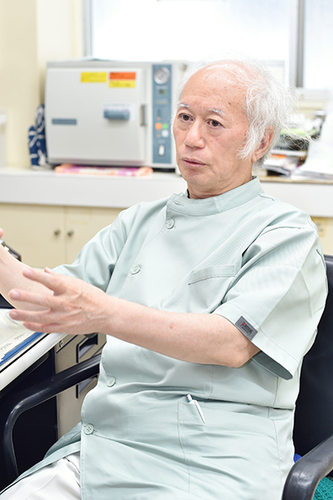
整形外科は足腰の悪いお年寄りの患者さんが多いので、院内スペースにゆとりをもたせ、快適に過ごせる空間にしたいと思いました。お子さんが来た時に楽しめたらと、待合室に2畳の「お座敷コーナー」を設置したんですが、ソファーよりも座りやすいと皆さんにとても好評です。僕の趣味が読書なので、昔から待合室の本棚はいつも充実しています。医療系の本や僕の好みのものばかりだとつまらないので、患者さんに読んでもらいたいお勧めの本やはやりの本を、職員に持って来てもらったりしていますよ。
学ぶ姿勢を忘れず、地域の医療機関との連携を大切に
骨粗しょう症検査についてお聞かせください。

運動器の衰えによって要介護になるリスクが高い状態になるという「ロコモティブシンドローム」を防ぐためには、骨粗しょう症の予防と早期発見が重要です。当院でも骨粗しょう症検査を行っていますが、より多くの方に検査を受けてもらうため、近隣のクリニックにも検査の実施を呼びかけて、クリニックで行ったレントゲン検査の結果を当院に送ってもらい、検証してお返しするというのを、20年以上前からやっています。骨粗しょう症は閉経後の女性に多く見られますが、若い人や男性でもかかる病気です。正しい方法でカルシウムを摂取し、年齢や病気のタイプに応じた適切な治療を受けて、病気を防いでいくことが大切です。
週に2回、勉強会に出席されているそうですね。
僕は頼まれたら断れない性格なんです。断れないから、自分ができるようになるために勉強する。自分ができない時は、その分野に詳しい先生に協力してもらい対応する。ずっとその繰り返しでやってきて、今でもいろんな勉強会に顔を出しては、整形外科だけでなくさまざまな診療科の先生と情報交換を行い、地域との交流を図っています。一方、患者さんにも治療や予防に対する意欲を高めてもらいたいので、疾患や健康に関するパンフレットをお渡しして自宅で読んでもらったり、患者さんが参加できる院内勉強会を月に1度開催したりしています。こちらが学べる機会を用意することでコミュニケーションが図られ、患者さんやご家族の方が治療に積極的になってくれます。
最後に、診療に対する思いをお聞かせください。
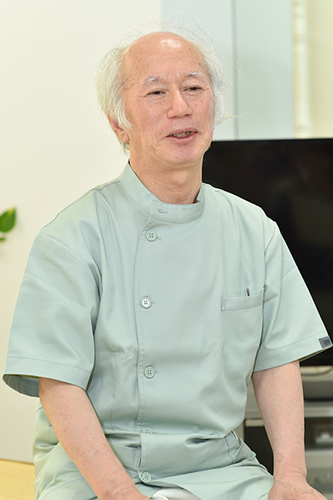
自分のやっていることが正しいか正しくないかの判断は、時にわからなくなることや、答えがないことがありますが、少なくとも僕は「間違ったことは絶対にしない」という信念のもとで診療しています。そして、医師として患者さんに温かい気持ちで接することを、いつも心がけています。患者さんの話をしっかり聞いて、きちんと応えるのは当たり前のことですが、「この先生は自分の気持ちをわかってくれている」と、患者さんに思ってもらえるような対応をすることが大切だと思っています。これからも地域の病院やクリニックとの連携を大事にして、約半世紀も診療してきたこの場所で、医療に従事していきたいですね。






