竹屋 美幸 先生の独自取材記事
大西診療所
(大阪市城東区/深江橋駅)
最終更新日:2025/09/09

深江橋駅から5分。阪神高速東大阪線沿いにある「大西診療所」は、戦後すぐに木造2階建ての有床病院として開院。長きにわたって地域の医療を支えてきた由緒ある診療所を、3代目として継承予定の竹屋美幸先生に会いに行った。大阪大学医学部附属病院で長く勤務し、モットーは「患者さまが健康で元気に過ごすための良き相談相手」であること。「少しでも元気になって帰ってもらえたらうれしいです」と快活に話す。小児から高齢者まで、また生活習慣病から認知症まで、多様な内科疾患を総合的に診察する美幸先生がどのような診療所づくりをしていくのか、話を聞いた。
(取材日2023年3月15日/更新日2025年8月28日)
祖父から父へ、3代続けて地域医療に邁進
とても歴史のある診療所だと伺っています。

はい。戦後まもなく、祖父がこの場所で外科、内科、小児科を標榜して、開院したことが始まりです。まだ周りに田んぼがあるようなのどかな時代で、入院設備も備えた木造2階建ての病院でした。その後、1986年に父が後を継いで、専門である泌尿器科を診療科目に加え、同時に建物も建て替え、形態も病院から診療所へと変えました。今、診療所のとなりの敷地が、実家のあった場所です。私はここで生まれて育ち、子どもの頃はよくこの近所で遊んでいた記憶があります。
では将来は医師に、と期待されていたのですね。
いえ、父からそういうことを言われたり、進路を決められることはなかったですね。私は高校生の頃、どちらかというと理系の科目が得意で、自分は理系の道に進むかなという意識がありました。その中で祖父や父が医師で医学の道が身近にあり、またやりがいのある職業と思え医学部へ進学することを決め、兵庫医科大学医学部へ入学しました。
ご経歴についても教えてください。

大学卒業後はまず麻酔科で研修を行いました。当時は卒後すぐに、自分が進む科を決めなければいけなかったのですが、当時は総合内科のような部門がなく専門臓器の決断に至らず、悩んだ末に、まずは全身管理を行う麻酔科に決めました。そこで勤務するうちに特定の臓器に特化しない高齢者を診察し、また高血圧・糖尿病・動脈硬化など生活習慣病も勉強できる大阪大学医学部加齢医学講座の存在を知り、そちらへ移りました。そこでは大学院へ進む機会があり、高血圧に関連する遺伝子の研究や高齢者を対象にワクチンの有効性や肺炎に関する研究をしました。その後留学する機会を得まして、カリフォルニア大学サンディエゴ校で高血圧関連遺伝子の解析研究を行っていました。帰局してからは臨床を主にしたく、以前の内容に加えてプライマリケアにも従事するようになり、併せて認知症の診断・治療にも関わるようになりました。
先生がご専門の総合内科とは、どのような分野なのでしょうか?
私のめざす総合内科には病気を患った方だけでなく健康な方まで、小児から高齢者までずっと診るプライマリケアという分野も含みます。疾患に関しては風邪、発熱、腹痛、頻尿、浮腫などの症状から高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病まで、広範囲の疾患に対応します。内科、小児科、外科、産婦人科、皮膚科、精神科、緩和ケアなどのさまざまな診療科の知識を持ち合わせ総合的に評価し診断・治療を行い、必要に応じて専門の医師に紹介するなど地域医療連携を図ります。体調がすぐれないけれど何科で診てもらえばいいかわからないという方が最初にかかるところの側面もあります。特には漢方薬を使用したり、日常生活のアドバイスなども行います。また、予防医学にも力を入れており、一般の健康診断、企業検診や特定検診、予防接種や患者さまの背景を考慮しながらの生活指導や健康に関する相談などで健康のサポートも行います。
何科にかかればいいかわからない時に駆け込める場所
どのような患者さんが来院されますか?

地域の方が多いですね。祖父に続いて父もこの周りの学校の校医をしていることもあるためか小さいお子さんから祖父をご存知の高齢の方までおられます。時には、昔話を聞かせてくださる方もいらっしゃいます。診療内容としては、生活習慣病や風邪、頭痛、腹痛など内科的疾患、日常生活でのけが、血尿、膀胱炎などの泌尿器科疾患、花粉症や湿疹などアレルギー疾患などさまざま対応させて頂いております。現在、私は週4回の診察ですが、完全継承を視野に入れて院内の改装なども計画中です。また、予防医学の観点から当院では健康診断も積極的に受け入れており、特に企業健診や特定健診については近年受け入れを強化しています。
高血圧症や糖尿病などの診察、治療はどのように進むのでしょうか。
高血圧症の場合は、ご自身で測った結果が「高い」と心配でいらっしゃる方もおられますが「症状がないから、大丈夫」と放ったままの方もけっこう多いのが実情ですね。高血圧も糖尿病も気づかないうちに進んでいることが多く、どちらもまずは問診でお話を伺い、血液検査や合併症の検査をしながら、生活習慣や運動習慣などの非薬物療法から始まり、薬物療法を行っていきます。治療目標はそれぞれ患者さまの背景を考えながら総合的に判断するように気をつけています。
認知症の診療についても教えてください。

この数年は大学で物忘れの外来に長く携わってきました。幸い、内科受診のように受診できると思いますので、認知症についても気軽にご相談いただきたいですね。ここでも内科受診のように診察させていただくことができますが、認知症の場合もまずは問診です。問診による認知機能検査を行います。できればご家族からもお話を伺いたいです。併せて近くのクリニックで画像検査をしてもらって、総合的に判断していきます。認知症の中には治療で改善が見込めるタイプもありますので、必要に応じて神経内科や脳神経外科、精神科へ紹介することもあります。「もっと詳しく調べたい」方がいらっしゃれば、大学病院へ紹介させていただきます。1週間ほどの入院で、あらゆる角度から検査を受けていただけますから、興味がおありの方は、いつでもお知らせください。
地域の人が健康で元気に過ごすための、良き相談相手に
こちらの特筆すべき点はどのようなところでしょうか?

一番は、日本内科学会の総合内科専門医として幅広い視点から診療を行いますので、体調に何か問題が起きたときに、地域の方々が気軽に受診していただけることではないでしょうか。「いつも頭が重い」「なんだか体がだるい」などの症状から「あれもこれもつらくて、まず何科に行けばいいの?」という方も来院していただければ、必要に応じて専門の医師との連携も取りながら最適な医療を提供できればと思っています。地域の方が最初に気軽に駆け込める場所になっていきたいですね。予防医療として子どもから大人の予防接種はもちろん、特定健診、企業の健康診断も随時受けつけています。また、認知症も専門に診察していますので、物忘れが気になりだした方も気軽にご相談いただければと思います。
先生が患者さんに心がけていることはどのようなことですか?
いつでも気軽に相談してもらえる雰囲気でいることでしょうか。患者さんはお一人お一人違った背景をお持ちです。そういったことをお聞きしながら、一緒に考えていける医師でありたいと思っています。その辺は、老年・総合内科の診療の中で身についているのではないかなと、自負もしています。うまくいっているかどうかはわかりませんが(笑)。あまり短い診察時間にならないように心がけながら、患者さんの悩みに耳を傾け続けたいですね。大学で診療してきた老年・総合内科の目的の一つは「幸福長寿の実現」です。健康寿命を延ばし、高齢の方々がさらに幸福を感じられるシステム作りについて研究し、診療することに努めてきました。そしてこれからは「地域の人たちがいかに日常生活を過ごしやすくできるか」についてさらに考えながら、長く診療していきたいと思っています。
今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。
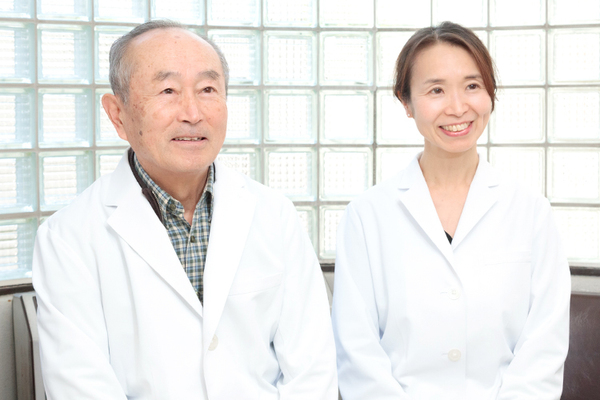
医療を通じて、地域の人たちと気軽に交流できる場を作れたらいいなあという夢を持っています。勉強会ほど堅苦しいものではなくて、皆さんが集まって一緒にお話をすることで、少しでも健康に対する意識づけができる活動をしたいですね。私のスタンスは地域の方が健康でいるための良き相談相手でいること。困った時に、気負わずに打ち明けてもらえるような、そのような位置づけでいたいと思っています。診療所に来られた方が、私と会話することで少し元気な気持ちになって帰られたり「また少し頑張ってみよう」と思ってもらえるように、お手伝いをしていきたいですね。






