成長・発達に不安を感じたら
小児神経分野の専門家に相談を
としかわこどもクリニック
(京都市山科区/山科駅)
最終更新日:2025/08/07


- 保険診療
「発達が周囲の子よりも遅いかもしれない」「この症状はてんかん?」など、子どもの成長に一度不安を感じると、気になり続けてしまう保護者も少なくないだろう。どこに相談するべきなのかわからず、どんどん悩みが大きくなってしまうこともあるかもしれない。「些細なきっかけで気づくこともあるので、まずは普段の診療の際に相談してみてください」と話すのは、日本小児科学会小児科専門医、日本小児神経学会小児神経専門医として長く研鑚を積んできた「としかわこどもクリニック」の利川寛実院長。発達障害や発達遅滞、起立性調節障害、てんかんなどの診療のほか、訴えが出てこず放置されがちな子どもの頭痛にも対応。しっかりと子どもの話に耳を傾け、困り事に寄り添う利川院長に、小児神経分野の診療について聞いた。
(取材日2025年7月18日)
目次
保護者の不安に寄り添い、子どもの話をじっくりと聞いて原因を探る
- Q小児神経分野とは、どんな疾患が対象なのでしょうか?
-
A
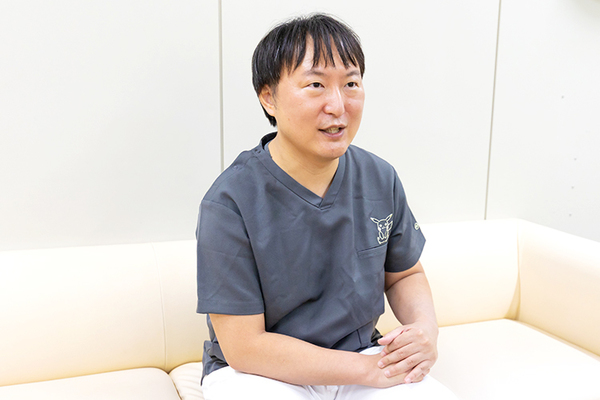
▲穏やかな表情と優しい声色が印象的な利川院長
小児神経は非常に広い範囲を診る分野で、これと絞るのは難しいですね。わかりやすく言えば、子どもが成長する過程には神経や脳などの発達があり、そこに関わるすべての疾患が対象です。おなかの中で脳が発生する段階でうまくいかなかったとか、発達障害や起立性調節障害、神経の変性疾患、てんかんなども含まれます。てんかんは大人になって事故を起こした方のニュースなどがあり、怖いと思われている病気の一つなのかもしれません。てんかんの動きか見てほしい、発達が遅れているかもしれないというご相談のほか、頭痛で受診される方も多いです。
- Q小児の頭痛の特徴はありますか?
-
A

▲子どもへの丁寧な問診をもとに、治療方法を探っていく
ほかの疾患とは違い、頭痛は自覚症状なので自分で訴えるしかありません。なんとなく元気がないときによくよく聞いてみると、頭が痛かったということもあります。大人と同じく、痛みがいつくるかわからない、痛み止めの薬に頼るしかないなど、頭痛が日常に与えるストレスは大きいもの。場合によって漢方薬を活用したり、頭痛ダイアリーをつけて頭痛のきっかけを探ったりと、ある程度コントロールできるようになれば生活の質も変わってきます。原因が心因性の場合は話をしっかりと聞いてあげることで改善が見込める場合も。どちらにせよ、頭痛で困っているお子さんに「痛みを訴えてもいいんだ」と知ってもらうことが大切だと考えています。
- Q受診すべきタイミングや診察の流れを教えてください。
-
A
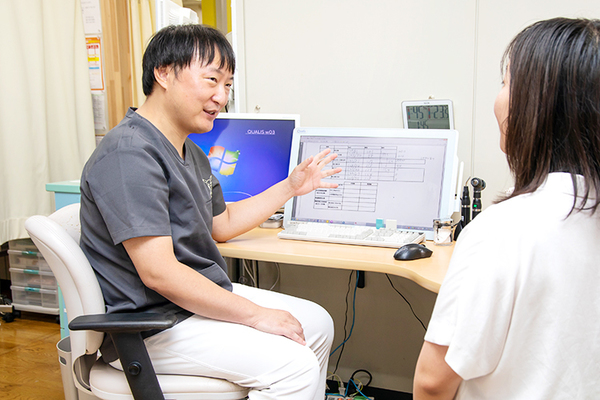
▲少しでも気になる症状があれば早めに受診を
些細なきっかけで気づくこともあるので、まずは何か気になることがあったときに受診していただくのが一番だと思います。診察では、最初に細かく問診を取ることで原因を探っていきます。うまく話せないお子さんも多いので、特に気をつけて話を聞き、困り事がどこにあるのかをピックアップできるようにしています。問診と血圧のチェックなどを行い、脳波検査が必要であれば近隣の連携する病院にお願いします。否定できるものは否定した上で話を進めていき、別の疾患の可能性などを考慮しながら「大丈夫」と声をかけることも大切にしています。
- Q受診するときのポイントや気をつけるべき点はありますか?
-
A

▲子どもの年齢や状況に応じた診療を行っている同院
年齢や状況にもよりますが、お子さんがうまく話せないときや、家では“頭が痛い”と言っていたのに医師の前では黙ってしまうという場面では、保護者が代弁者になることが必要です。一方で、思春期になると保護者の前で話すのをためらう子もいるので、親御さんが症状などを細かく説明してくださっても、必ずお子さん本人に問いかけるようにしています。ゆっくりと話を聞けるよう予約枠を調整するので、相談事があるときは事前に電話でご連絡ください。また、診療の際にこちらで気がかりなことがあるような場合は、別日に再度受診いただくことをご提案する場合もあります。
- Q小児神経専門医にかかるメリットを教えてください。
-
A
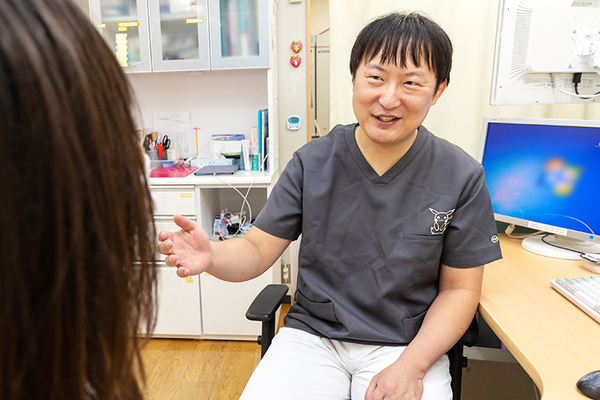
▲どんな小さな悩みでも、気軽に相談をしてほしいと話す利川院長
風邪や予防接種など、普段から「かかりつけ医」として通っていただいている中で、成長や発達について気軽に聞いてもらえることがメリットだと思います。また、妻である副院長も小児神経分野を専門としています。お互いにまったく同じ症例を診てきたわけではないので、状況に応じて意見を言い合えることが当院の強み。もちろん必要であれば大きな病院への紹介もしていますが、気構えずに近所のクリニックで相談をしていただければと思います。






