先進のロボットスーツを用いた
神経難病のリハビリテーション
宇野胃腸内科脳神経内科
(松阪市/松ヶ崎駅)
最終更新日:2025/09/19


- 保険診療
神経難病に特化する「宇野胃腸内科脳神経内科」では、神経難病による運動機能の低下に対し、早期からのリハビリテーションに力を入れている。新たに外来のリハビリ専用施設を建設し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの多職種が協働して、患者一人ひとりの疾患や状態に応じた支援を実施。パーキンソン病治療の経験が豊富な宇野研一郎副院長は、「神経難病=諦めるしかないというスティグマを何とかしたい」という思いから、先進機器であるロボットスーツを導入。ロボットスーツが疾患によって低下した筋肉の動作をサポートし、患者の「動きたい」という意志に寄り添った質の高いリハビリが可能になる。リハビリの選択肢を広げるロボットスーツの特徴や、問診から使用までの流れについて詳しく聞いた。
(取材日2025年7月10日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Qロボットスーツはどのような仕組みで動くのでしょうか?
-
A
人が歩きたいと考えると、脳から筋肉へ微弱な生体電気信号が送られます。皮膚に貼った電極パッドでこの信号を感知し、ロボットスーツが装着者の動きに合わせて、関節や筋肉の動作をサポートするという仕組みです。これにより、普段は筋力が低下して少ししか体を動かすことができない方でも、歩けるようになることが望めます。さらに、「このように筋肉を動かした」という情報が脳にフィードバックされることで、動作の学習にもつながります。ロボットスーツを外した後でも歩きやすくなることが期待できるケースもあり、継続的に使用することで、自分の力で動く感覚を取り戻すきっかけになることにもつながります。
- Qどのような患者さんが使うのか教えてください。
-
A
ロボットスーツの対象疾患は、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、封入体筋炎、シャルコー・マリー・トゥース病、先天性ミオパチー、遠位型ミオパチー、筋ジストロフィー、遺伝性痙性対麻痺、HTLV‐1関連脊髄症の10個です。この対象となる神経難病の方しか使えません。ただし、ロボットスーツが筋肉から出る信号をキャッチするため、病気が進行して筋肉の委縮が進んでいる方は使用できないため、早めにリハビリを受けていただくことを推奨しています。他にも、ペースメーカーなど埋め込み式の医療器具を使用されている方、妊娠中の方などは、ロボットスーツの使用が難しいケースがあります。
- Q重そうに見えますが、患者さんへの負担はありますか?
-
A
ロボットスーツ本体は、約12キロありますが、当施設では「吊り下げ式」を採用し、本体を専用の機器で吊るすことで患者さんへの負担を大きく軽減することが可能です。使用時は患者さんの状態に合わせて、吊り方や支え方を細かく調整できるため、重いと感じる方でも利用可能です。さらに、理学療法士が付き添い、装着中の患者さんの声を聞きながら調整を行うため、安心して取り組んでいただけます。最初はうまく動かせない方もいらっしゃるかもしれませんが、回数を重ねることで徐々にスムーズに動けるようになるようお手伝いしています。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1医師の問診と理学療法士の評価
-
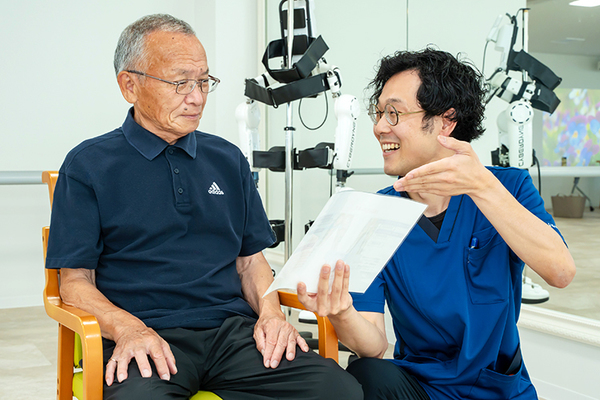
ロボットスーツは両脚を入れるタイプで、使用には一定の身体条件がある。そのため、身長・体重・靴のサイズ・腰幅などを測定し、初回に適応を確認する。続いて、関節の可動域や筋力の状態について、理学療法士が評価を行う。確認すべき部位は疾患によって異なるが、日常動作を含めた総合的な評価を行う。また、このリハビリは継続によって効果が期待されるものであるため、患者本人の継続意志を確認することも重要なプロセスだ。
- 2ロボットスーツのフィッティング
-

ロボットスーツを装着する際は、上半身はTシャツ、下半身はクリニックが用意した電極を貼りやすい服に着替える必要がある。女性患者には、女性の理学療法士およびスタッフが対応するため、安心してフィッティングを受けられる。装着時はまず座った状態で、腰と脚にベルトを用いてロボットスーツを固定する。
- 3初回のデータを記録
-

ロボットスーツを装着した後は、初回のデータを記録するセッションを約1時間かけて実施する。専用機器で本体を吊り下げた状態で、患者に歩行してもらいながら、体重移動の仕方や歩行時の重心バランスに関する詳細なデータを取得する。歩行中、患者自身は目の前のモニターを通じて、現在の重心の位置や体重の移動状況をリアルタイムで確認することが可能である。
- 4リハビリ開始
-

最初は思うように体が動かないこともあるため、理学療法士に体を支えてもらいながら歩行訓練を行う。歩行用の機器の前には大きな鏡が設置され、患者は自らの姿勢や位置のずれを確認しながら、約20分間歩行を行う。疾患や症状によっては強化すべき部位が異なるため、ロボットスーツを装着した状態でスクワットを3〜4回実施する場合もある。訓練の内容は、理学療法士が個々の患者に応じたプランを提案。
- 5継続通院で機能改善をめざす
-

リハビリの期間が空くと、機能が戻ってしまうため、継続して通院することが肝心。同院では、週2回の通院で、間の3日間は自宅で動作の復習に取り組むことを推奨している。そのため、通い続けるためのモチベーションを維持することも大切な要素となる。同じ疾患の患者と話す機会を増やすことで、モチベーションの維持につなげるため、同院にはカフェが併設されている。







