ヘッドホン・イヤホンで難聴も
聞こえにくくなる原因と治療
大島耳鼻咽喉科気管食道科クリニック
(八王子市/京王八王子駅)
最終更新日:2024/09/09


視覚や嗅覚、味覚、触覚とともに五感とされ、私たちが外界を認知するために欠かせない大切な感覚である聴覚。突然失われてしまったり、いつの間にか聞こえにくい状態が続いていることに気づいたらどうだろう。「聞こえにくさにはさまざまな症状や原因があります。近年では、ヘッドホン・イヤホンによる難聴や聴覚情報処理障害(APD:Auditory Processing Disorder)などのケースも注目されており、専門家の判断を仰ぐことが重要です」と、八王子「大島耳鼻咽喉科・気管食道科クリニック」の大島清史院長は話す。同院でも「突然聞こえにくくなった」「以前より聞こえにくくなっているような気がする」など、聞こえの相談が増えているという。そんな大島院長に聞こえにくさの原因や治療、対処法について、詳しく聞いた。
(取材日2024年2月29日)
目次
聞こえにくさの症状や原因はさまざま。自己判断せず専門の医師に早めの相談を
- Q耳が聞こえにくくなるのにはどのような原因が考えられますか。
-
A

▲患者の聞こえに関する幅広い悩みに対応する
耳は外耳、中耳、内耳からなり、それぞれの部位に難聴を引き起こす原因が考えられます。外耳では耳垢、外耳炎、中耳は急性中耳炎や滲出性中耳炎、奇形など、内耳ではメニエール病や遺伝性難聴、「ヘッドホン・イヤホン難聴」とも呼ばれる騒音性難聴などです。外耳や中耳の障害による難聴を伝音性難聴、内耳に由来するものを感音性難聴と区分しますが、両者が混在する混合性難聴もあります。突然聞こえにくくなるケースもあれば、徐々に聞こえにくくなることもあり、原因の追求が難しい場合も。さらに、耳の機能自体には問題がないにも関わらず、言葉を聞き取ったり、それを理解したりすることが難しい、聴覚情報処理障害もあります。
- Q「ヘッドホン・イヤホン難聴」とはどのようなものなのですか。
-
A

▲機器を活用して、精密な検査を行っている
ヘッドホンやイヤホンで大きな音を聴き続けることで起こる騒音性難聴を、特に「ヘッドホン・イヤホン難聴」と呼ばれています。耳に過剰な圧力がかかり続けることで、音を感じる役割を果たす内耳の有毛細胞が損傷し、将来的な難聴リスクが懸念されています。世界保健機関(WHO)は2050年までに25億人近くがある程度の難聴になると予測。国会などでもグループを立ち上げて検討を始めました。一度壊れてしまった有毛細胞は、現在の医学では治すことができません。再生医療分野での研究はスタートしていますが、実用化にはまだ至らない段階です。現時点でできるのは大きな音を聞き続けないという予防のみなのです。
- Q聴覚情報処理障害についても詳しく教えてください。
-
A
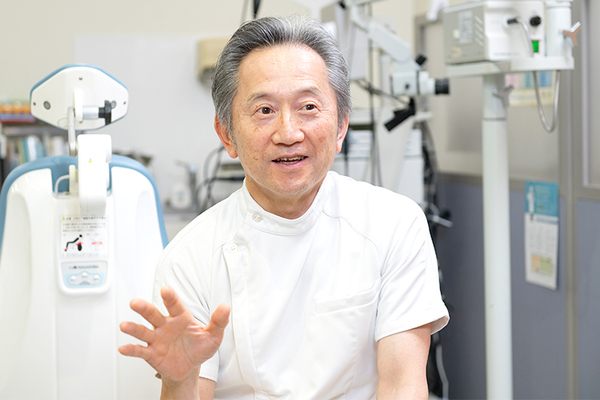
▲違和感があれば自己判断せずに受診をと話す院長
聴覚情報処理障害は、音としては聞こえるが、言葉として聞き取りが難しい、内容の理解に時間がかかる状態です。長年研究されていますが実態はまだ不明で、発達障害の一種である可能性も指摘されています。言葉の聞き分け力を調べる語音明瞭度検査を含め、聴力検査では異常なしです。しかし、早口や小声で話されたり、雑音が多い中だったりするとうまく聞き取れず、頻繁に聞き返したり、指示に従わなかったりします。黒板等に書いてある文字は問題なく理解できるので、学校生活ではやり過ごせてきた人が、社会に出てから対応できず悩むケースも少なからずあるようです。
- Q聴覚情報処理障害の人が気をつけるべきことはありますか。
-
A

▲聞こえづらさは生活の質に影響を与えてしまう
まずは自身がどういう状態であるのかを知り、周囲の人にも聴覚情報処理障害であることを正しく認識してもらうことが大切です。その上で、ゆっくり話してもらったり、ホワイトボードやプリントアウトなどの視覚的資料を補助的に用いてもらったりするよう、配慮をお願いしましょう。聴覚情報処理障害の人では、指示を受けたのに聞き取れなかったことによる対応の抜けがトラブルにつながるケースが多いようです。言葉のみでの指示は十分に聞き取れない可能性があることについての理解を促し、伝え方に工夫してもらうことが必要でしょう。
- Q治療法について教えてください。
-
A

▲専門知識に基づき治療を行う
ヘッドホン・イヤホン難聴には現状治療法がないので、予防が大切です。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では4つのポイントを集めた「あいのて」をキーワードに予防を呼びかけています。「あ」は音量を上げ過ぎない、「い」は医師に相談する、「の」はノイズキャンセリング機能を使う、「て」は定期的に休むです。聞こえづらさを補う手段としては補聴器がありますが、国内では高価な補聴器を購入する際の補助制度が十分に整備されておらず、普及が広がらないのが現状です。眼鏡はかければ見えるようになりますが、補聴器は使い始めてから調整し慣れてよく聞こえるようになるまで3ヵ月程度を要します。そのことも念頭に上手に活用してほしいですね。






