滝澤 誠 院長の独自取材記事
滝澤医院
(杉並区/永福町駅)
最終更新日:2025/07/15
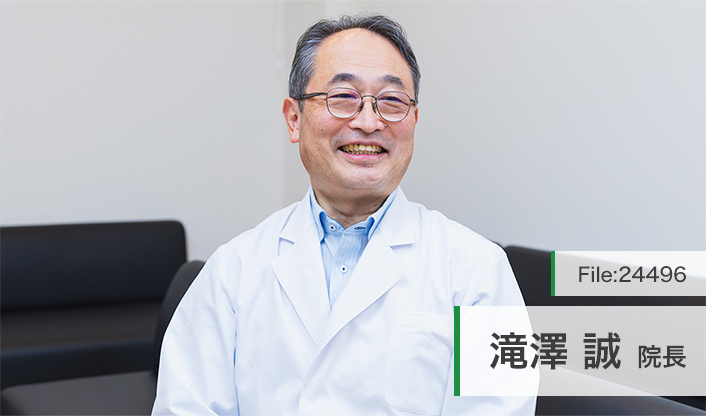
永福町駅から徒歩約3分の場所にあるのが、「滝澤医院」だ。地域の人々のかかりつけ医として、内科と小児科に加えて、糖尿病・代謝内科の専門的な診療を提供する同院。滝澤誠院長は、杏林大学医学部付属病院の糖尿病・内分泌・代謝内科で約20年にわたって研鑽を積んできた経験を生かして、患者の生活習慣を考慮しながら、寄り添う医療を提供している。「風邪や胃腸炎などの日々の不調から、生活習慣病の管理まで、幅広い年代の人が気軽に相談できるかかりつけ医でありたいですね」という滝澤院長に、最近、現在の場所に移転してきた同院の取り組みや、診療する上で大切にしていることなどを聞いた。
(取材日2025年6月4日)
内科と小児科から糖尿病・代謝内科まで、幅広く診療
こちらは、どのような医院ですか?

内科では、風邪や胃腸炎、インフルエンザなどのほか、糖尿病、高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病をメインにしています。小児科も風邪や胃腸炎などの初期治療が多いですね。特に糖尿病・代謝内科は、これまで診療や研究を続けてきたことを生かしながら、専門性の高い診療を提供しています。当院で対応できない検査や治療が必要な場合は、私の出身である杏林大学医学部付属病院や、昨年から杏林大学が運営することになった杏林大学医学部付属杉並病院などと連携して対応しています。それらの病院には、私が直接知っている先生も多いことから連携もしやすく、患者さんにもメリットは大きいと思います。
最近、移転したのですね。
以前の医院の建物は、すでに50年以上前の建築のため、老朽化によっていろいろな問題も出てきていたので、移転する場所をずっと探していたんです。私が望んでいる条件と合うところがなかなか見つからなかったのですが、長年診療していた歯科医院が昨年閉院され、賃貸物件となっていたものをご縁がありこの度お借りすることになりました。駅からも近く良い場所だったので、今回移転することにしました。ただ、以前の場所は住宅街の中にあり、それこそサンダル履きで来るような患者さんもいたんです。そういう方からは、「もうサンダルで来られる距離ではなくなった」なんて言われますけどね(笑)。
院内の雰囲気などで意識したことはありますか?
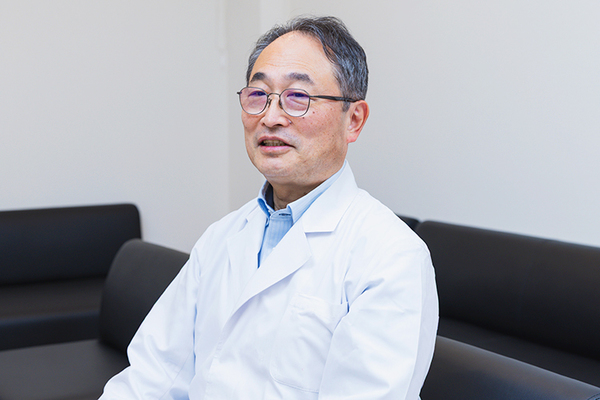
待合スペースは、以前に比べて広くなりました。全体的に落ち着いた雰囲気を意識していて、受付横の柱はモザイク模様になっています。特に狙ったわけではないんですが、良いアクセントになっていて、患者さんからも「おしゃれですね」と言っていただいています。診察室は、これまでより少しコンパクトになりましたが、代わりに処置室を新たに設けて、検査や感染症の患者さんはこちらで対応できるようにしています。入り口から院内すべてをバリアフリーにし、トイレも広くしていますので、車いすの方でも安心してご利用いただけると思います。待合室には大きなモニターを設置して、今後診察の順番を表示したり、患者さんの役に立つ情報を表示するなどの利用を考えています。さらに、無料で使える無線LANの導入やキャッシュレス決済への対応も、順次進めているところです。
患者が本当に伝えたいことをくみ取れるよう心がける
専門の糖尿病の診療について、詳しく教えてください。

糖尿病は高齢者に限らず、若い方でもなる病気です。でも、若い方は仕事が忙しく、健康診断で高血糖を指摘されても、自覚症状もなく、生活に支障がないからと放置している人もいます。その結果、50代以降に悪化して、治療せざるを得なくなってしまうのです。でも、初期であればお酒を少しセーブするとか、食事に気をつけることで改善へつなげることが見込めるケースも多いので、早めに受診することが何よりも大切です。また、一度始めた治療を中断してしまう人が多いのも糖尿病の傾向です。経済的な問題、仕事の忙しさによる時間的な問題など理由はさまざまですが、中断したことで悪化して、合併症が進んでしまった人をたくさん見てきました。糖尿病の怖さは、重篤な合併症を引き起こすリスクがあることです。ですから、通院を続けることが大切だという意識を持てるようなサポートもしていければと思っています。
ほかに力を入れていることはありますか?
例えば、生活習慣病でこれまでずっと同じ薬を使っているけど、「本当にそれで良いのだろうか」「新しい薬や治療があるのではないか」などと考えている方や、良くなっているのかわからないことで、自己判断で通院をやめてしまった方もいると思います。それまで使っていた薬や治療方法はもちろん尊重しますが、それに代わって患者さんにより適していると考えられるものがあれば変えて、それによって病状が安定し、患者さんにも満足してもらえれば良いなと思っています。また、HPVや帯状疱疹をはじめとするワクチンの接種や健診にも対応していますので、必要なときには相談いただきたいと思います。
診療の際に心がけていることを教えてください。
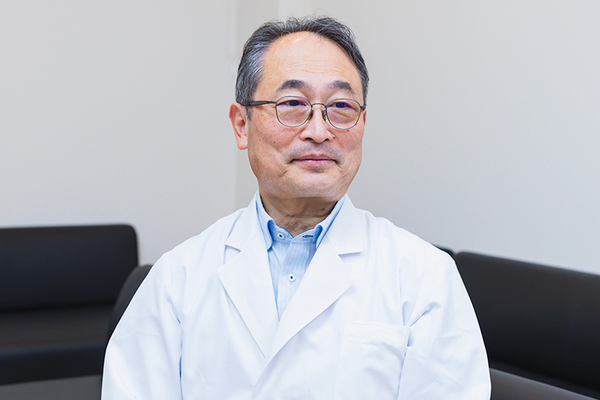
患者さんの話は、表面上のことだけでなく、本当に伝えたいことをくみ取るよう心がけています。そのため、ご家族や生活の背景、時には趣味のことなど、治療とはあまり関係のない話をすることもあります。特に初診の場合は、診察時間が長めになってしまうかもしれません。また、「病院で検査を受けたけど、データの意味がわからない」「こう指示を受けたけれど、なぜそうしないといけないのか」と疑問を持ちながらも質問できなかったという声もよく聞きます。大学病院などには大勢の患者さんが訪れるため、どうしても診察時間が限られてしまいます。当院では、できるだけわかりやすく説明して、なぜそれが必要なのか納得してから治療を受けていただくように心がけています。その結果として患者さんに喜んでもらえたら、それが医師としてのやりがいだと考えています。
地域の人々にとって身近な存在でありたい
話は変わりますが、先生はなぜ医師を志したのですか?

うちは父だけでなく、母方の祖父も医師でした。医師の道へ進んだのは、祖父の影響のほうが強いかもしれません。そして、杏林大学医学部を卒業後は、米国アルバート・アインシュタイン・メディカルセンターで、主に代謝や内分泌と骨の関わりを研究しました。代謝や内分泌を専門にしようと決めたのは、考えてから動くような分野のほうが私の性格に合っているのではないかと感じたからです。帰国後は、心臓血管研究所付属病院で循環器の診療に携わった後、杏林大学医学部付属病院の糖尿病・内分泌・代謝内科で約20年にわたり、経験を積みました。2016年からは共済会櫻井病院に副院長として勤務し、それと並行して当院で週に何日か診療するようになりました。2010年に父が亡くなったのを機に、当院を引き継ぎました。
今後の抱負はありますか?
移転をきっかけに、これまでやりたくても何かと難しくてできなかったことに、少しずつ取り組んでいきたいと考えています。その一つが、臨床検査技師のスタッフを迎えることです。臨床検査技師がいると、院内で超音波検査や、いわゆる「血管年齢」を測る検査などができるようになります。これまでは、そういった検査が必要なときは、対応できる医療機関を紹介する体制でした。でも、院内でできるようになれば、患者さんがわざわざほかの病院に行かなくても済みますし、私もその場ですぐに検査結果を確認できるので、診療のスピードも上がります。そういった意味でも、大きなメリットがあると思っています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
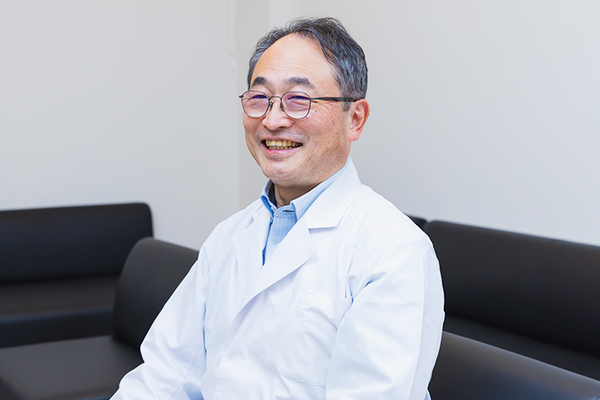
今回の移転先の開設届は5月1日になりました。実はその日は私の65歳の誕生日でもあるんです。65歳といえば、一般の会社では定年です。私も医師になってから約40年、ずっと大学病院などとかけ持ちで診療をしてきましたが、移転を機にこれからは基本的に当院一本で診療をしていくことにしました。そのため、午前中は日曜・祝日を除いて毎日診療を行っています。とはいえ、無理はしないようにと思っていますので、もしちょっと疲れてしまったら、臨時でお休みをいただくこともあるかもしれません(笑)。その際は、どうぞご理解いただければと思います。そして、永福町は私が小学生の頃から住んでいる、思い入れのある街です。そんな地元で、「ちょっと困ったときに相談できるかかりつけ医」として、地域の皆さんにとって身近な存在でありたいと思っています。健康で何か気になることがあれば、気軽に相談してください。






