鴨下 衛 院長の独自取材記事
鴨下眼科クリニック
(港区/六本木駅)
最終更新日:2026/01/20

「鴨下眼科クリニック」は1996年に六本木に開業して以来、長年にわたり近隣住民の目の健康を守ってきた。鴨下衛(かもした・まもる)先生は、父である鴨下泉理事長の後を継ぎ、2024年に2代目院長へ就任。2025年9月には、ビルの老朽化に伴い移転。同じ六本木駅近くでも、より閑静なエリアで新たなスタートを切った。鴨下院長はこれまで東京都済生会中央病院の眼科医長として、白内障手術や糖尿病網膜症への硝子体手術などを数多く手がけてきたスペシャリスト。幅広い眼科疾患に対応しながら、いざというときは専門性に裏づけされた診療を提供できるのが強みだ。「将来的な地域医療を見据え、地域の皆さんに貢献していきたい」と訪問診療にも意欲的。そんな鴨下院長に、これまでの歩みや今後の展望について詳しく聞いた。
(取材日2025年10月24日/再取材日2025年12月23日)
網膜・硝子体を専門とし、臨床と研究に尽力
まず、眼科医を志したきっかけを教えてください。

医師をめざしたのは、救急救命室が舞台のアメリカの医療ドラマを見て「かっこいいな」と憧れた、10代らしいシンプルな理由からでした。大学を卒業して2年間の初期研修を終えた後は東京医療センターで救命救急を1年間経験。やりがいはありましたが、多くの患者さんを最終的に各診療科に受け渡す日々の中で「受け持った方を最後まで見届けたい」という思いが強くなっていきました。また、救急医はジェネラリストであることを求められますが、むしろ専門的な分野を突き詰めたいとも考えるようになったんです。そして、眼科に改めて興味を持つようになりました。父にはまったく強制されませんでしたが、同じ眼科を選んだからこそ一緒に働けて、患者さんに優しく誠実に接する父の姿も間近に見られ、良い経験をさせてもらっています。
これまでのキャリアについて詳しく伺えますか?
慶応義塾大学の眼科医局に入局し、最初の数年間は眼科医としての基礎を学びました。その後、上司の誘いで大学院に進学して網膜分野の研究に取り組みました。マウスを使った網膜電図という検査を、朝から晩まで真っ暗な部屋にこもって繰り返した日々は、今でも忘れ難いですね。4年間で英語論文を4本書き、海外の研究発表会にも積極的に参加。卒業後は慶應義塾大学病院の網膜・硝子体グループに所属し、基礎研究を続けながら臨床の研鑽を積みました。その後に勤務した東京都済生会中央病院は糖尿病治療で知られており、数多くの糖尿病網膜症を診療。これまでの網膜分野の研究を生かせただけではなく、医長として後輩の手術指導や科の運営、他科との連携強化など、より幅広い経験を積むことができました。
さまざまな専門性を持つ先生方やスタッフが在籍しているのですね。

目に関するお困り事は一通り気軽に相談できるクリニックでありながら、必要に応じてより専門的な診療も提供できるのが当院の強みです。私と父は網膜・硝子体が専門ですが、その他にも近視・白内障・緑内障・眼瞼下垂などを得意とする先生方が在籍しています。大学病院や国立病院から来ていただいているので、高度な治療が必要な場合もスムーズに紹介できます。また、明るく優秀なスタッフたちも当院の自慢です。手術のサポートも安心して任せられる看護師、難しい検査や小児の検査もスムーズに行う視能訓練士、コンタクトレンズに詳しいスペシャリストなど、それぞれが強みを持っています。受付の3人は目配りも十分で、いつも明るく患者さんに気さくに声をかけてくれているのでとても助かっていますね。
白内障手術から近視抑制、訪問診療まで幅広く対応
こちらではどのような白内障手術を受けられますか?

当院では、主に単焦点レンズによる日帰りの白内障手術を保険診療で行っています。選定療養による多焦点眼内レンズにも対応していますが、安全性を重視して厳選しています。一般的な白内障手術は難しいものではなく、手術日の院内滞在時間も90分から120分程度ですが、強い不安を感じる方も少なくありません。そこで、当院では手術中に静かなクラシック音楽を流すなど、患者さんが少しでもリラックスできるように環境を整えています。白内障は加齢による原因がほとんどで、視力が低下して日常生活に不自由を感じるようになったら手術を検討するタイミングです。入院手術が必要なときも、提携している病院をご希望に合わせて紹介しています。
ご専門である網膜疾患の治療についてもお聞かせください。
例えば糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などの継続的な管理に力を入れています。初期ならば、レーザー治療や硝子体注射などができるので、見え方に少しでも違和感があれば早めにご相談ください。すでに進行して手術が必要な段階になっていても大学病院などにスムーズにつなげ、術後のフォローアップも行っています。中でも糖尿病網膜症に関しては、これまで東京都済生会中央病院で数多くの経験を積み、内科の先生とタッグを組んで患者さんを見守る重要性も理解していますので、気軽にご相談ください。
その他にも、幅広い年齢層の悩みに対応しているそうですね。

最近は小児の近視治療に関する相談が増えています。夜間にコンタクトレンズを装着して近視矯正を図るオルソケラトロジー、低濃度アトロピン点眼薬による近視進行抑制治療などにも注力しているところです。一方、通院が難しいご高齢の患者さんには訪問診療もできる限り対応したいと考えています。特に緑内障の患者さんは眼圧コントロールのための点眼治療が欠かせませんが、通院できなくなると症状が悪化する方も珍しくありません。訪問診療ならばオンライン診療と違って眼圧も測定できますし、目薬の正しい使い方も詳しくお伝えできます。目やにが多く視界が悪いなど、日常的なお悩みにもきめ細かに対応し、患者さんとご家族が安心して過ごせるようサポートしたいと思っています。
かかりつけ医としての役割を果たし地域医療を支えたい
先生ご自身が目の健康のために大切にしている習慣はありますか?

情報収集やコミュニケーションのためのツールとして便利なスマホですが、長時間にわたり画面を凝視しないように気をつけています。スマホだから悪いというのではなく、近距離で一つの物を見続けることは目への大きな負担になるんですね。スマホ以外でも現代人は手元で物を見ながら作業する時間が長く、誰もが目のオーバーワークに陥りがちと言っても過言ではありません。患者さんのライフスタイルにもよく耳を傾け、デスクワークが多い働き世代には、仕事の合間に外を散歩する時間をつくったり、せめて遠くを見たりするようにお勧めしています。
今後の展望をお聞かせください。
地域のかかりつけ医としての基盤づくりを、より強固にしていきたいと考えています。現在、限りある医療資源を効率良く活用するため、大学病院や総合病院は高度医療や入院治療に特化できるよう、かかりつけ医の在り方を見直す政策が進められています。私たちのような開業医は、適切なタイミングを見極めて基幹病院に紹介する診断力や、治療後のフォローを引き受ける万全の体制をますます求められることになるでしょう。さらに、クリニックでも一般的なプライマリケアだけではなく、ある程度、専門的な治療ができることも大事だと思っています。今後も患者さんが気軽に来ていただける場所をめざしながら、実は専門的な診療も行っているという特色は強化していきたいです。長く勤務していた慶應義塾大学病院や東京都済生会中央病院の他、地域の基幹病院と良好な関係性を構築していますが、さらに病診連携を深めていきたいですね。
最後に読者へのメッセージをお願いします。
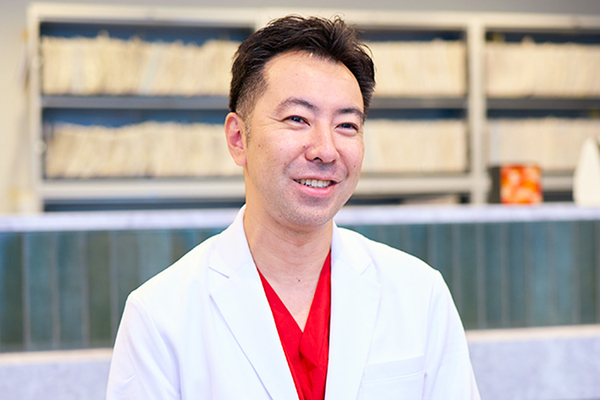
当院は目に関することならば、どんなに小さなお悩みでも気兼ねなく相談できる親しみやすいクリニックをめざしています。「視界が良くなると、世界がもっと良くなる」というコンセプトのもと、患者さんの生活をより明るくするお手伝いをすることが願いです。基本的には予約制ですが「急に見えにくくなった」などの異変があったら、予約の有無に関わらず遠慮なくお越しください。待ち時間も気持ち良く過ごせるように、落ち着いた雰囲気をイメージした待合室など、くつろげる空間づくりにもこだわっています。症状の改善をめざすのはもちろん「心も軽くなった」と思っていただけるような場所が目標です。地域のかかりつけ医として、皆さんの目の健康をしっかりと支えていきたいと思っています。
自由診療費用の目安
自由診療とはオルソケラトロジー(両眼)/18万7000円~、低濃度アトロピン点眼薬による近視進行抑制治療:初回の検査費用/5600円~、点眼薬(1ヵ月分)/4380円、選定療養を用いた多焦点眼内レンズによる白内障手術/28万円~+医療保険による白内障手術費用






