山口 剛 理事長の独自取材記事
友生歯科医院
(横浜市磯子区/磯子駅)
最終更新日:2025/06/13

磯子駅から徒歩5分の場所にある「友生歯科医院」。駅前のマンション1階というアクセスの良い立地だ。歯科用CTや口腔内スキャナー、CAD/CAMシステムといったデジタルツールを駆使し、インプラント・審美歯科・矯正歯科をメインとした総合的な治療を行っている。山口剛理事長は、まだインプラントが一般的でなかった頃から治療を手がけニューヨーク大学での留学を経て、インプラントについて専門に学び取り組んできた。今では歯科医師としての長年の経験と、口腔外科領域の知識や技術を生かした顎変形症治療や審美歯科にも対応する。今回は山口理事長に、同院の治療内容について、また歯科医療に対する思いを聞いた。
(取材日2022年12月16日)
先進のデジタルツールを駆使し、高度な歯科医療を
歯科医師を志されたきっかけと、磯子での開業までの経緯をお聞かせください。

子どもの頃に小児喘息の患者として医療に接する機会が多く、いつの間にか医療系に進みたいと考えるようになったのが、のちに歯科医師をめざしたきっかけです。医科と歯科で迷い「努力した成果がはっきりとわかりやすいのは歯科」と恩師や先輩からの助言、また工作や物作りが好きだったことから歯科を選びました。日本歯科大学卒業後は、複数の歯科医師が在籍するクリニックで勤務しました。率先して勉強会に参加しスキルや知識を向上させていたことや、「先生は話しやすい」と指名してくださる患者さんが増えたことが自信につながり、開業を考えるようになりました。1987年にグループ1院目となる 「山口歯科医院」を開業、当院の開業は2001年のことです。
こちらではどのような治療が受けられるのでしょうか?
歯科用CTや口腔内スキャナー、CAD/CAMシステムといったデジタルツールを駆使し、インプラント・審美歯科・矯正歯科をメインとした総合的な治療を行っています。やはり当院の得意分野であるインプラントを希望される方が多いですね。グループ1院目の「山口歯科医院」は、一般歯科や小児歯科が中心の地域密着型のクリニックです。その中には、矯正・審美歯科・インプラントといった自由診療を望まれる患者さんも一定数いらっしゃいました。そのニーズに応えるべく開業したのが当院。脳波モニターを使った静脈内鎮静法を取り入れた麻酔を用い、より高度な治療も行っています。
歯科衛生士さんも高い意識と技術力を持っているのですね。

これは当院がインプラント手術を多く担っており、その後の歯科衛生士によるメンテナンスがインプラントの長持ちに不可欠であることと大きく関連しています。インプラント手術の終了は、インプラントと付き合っていく「スタート」でもあります。長期間機能させるためには、患者さんご自身のセルフケアと、プロフェッショナルケアが重要です。プロフェッショナルケアの利点は、インプラントの周囲組織である粘膜や骨の劣化を食い止めるべく、定期的な検査とクリーニングを行うこと、また有病の方の服薬状況の確認ができることです。関係する知識や経験を積んだスタッフが定期的に症状をチェック、異常があれば速やかに歯科医師に伝達することで、スムーズな修復が望めるのです。
高齢者・有病者の治療には不可欠なリスク管理
こちらで行うインプラント治療について教えてください。

現在当院では多くのインプラント手術を行っています。2003年にはニューヨーク大学のプログラムに参加。インプラントに精通する指導者に直接学ぶことができ、私自身の考え方や治療方法も劇的に変わりました。アメリカ人は歯科治療に対する理想とニーズが高く、歯を大切にする習慣も違います。将来的に日本でも要求されるであろう高いスキルが学べましたし、完成度も高くなり、先進的な治療を行えるようになったと自負しています。
世界レベルの情報を積極的に取り入れていらっしゃるのですね。
はい。先日はとあるミーティングでスウェーデン・ドイツ・アメリカの先生方と話す機会があり、当法人の治療内容は世界レベルに近いところまで達していると感じ自信を持ちました。当院の持つ先進の医療機器や治療技術を、当院の若手歯科医師たちに伝えていきたいと思うのです。常に世界レベルの情報を取り入れることは重要です。歯科材料や医療機器、新しい技術、スタッフの教育、患者さんのリスク管理。特に日本は高齢社会に伴い有病者数も増加傾向にありますから、リスク管理は避けて通れません。
リスク管理ということは、歯科医師にも医科の知識が必要とお考えでしょうか?
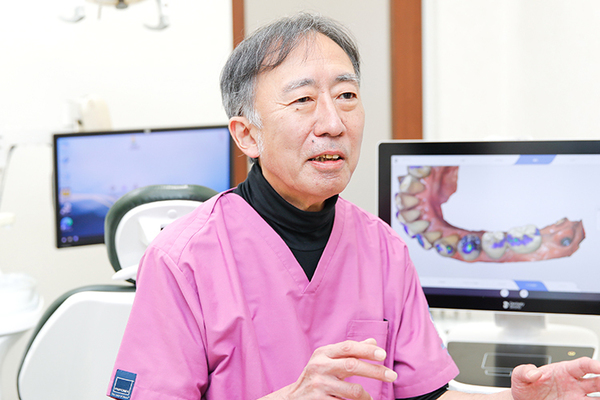
もちろんです。歯科医師は歯を治すだけの存在ではありません。「歯科を扱う医師」でなくてはならないと私は考えています。歯科にいらっしゃる患者さんの中には、ご高齢の方や、糖尿病・心臓病・骨粗しょう症といった全身疾患を患う方も少なくありません。それを踏まえた上で、今やろうとしている治療のメリットやデメリットを考え、それを患者さんにも伝えることが必要ですね。私は地域の中核病院で20年間、全身麻酔を伴う骨折や上顎洞炎の手術に多く携わってきました。この経験は、今も患者さんのリスク管理に十分に生かせています。患者さんの疾患を把握し、他科の医師の所見に頼るのみでなく、自らデータを読み取り判断すること。これを私自身も実践し、当院の若手歯科医師にもその必要性を伝えています。
とても難しい症例にも対応されているそうですね。
インプラント治療は、骨が少ないという理由で上の奥歯の治療が一番難しいのですが、上の奥歯の骨の付近にある「上顎洞」と呼ばれる部分は耳鼻咽喉科領域で、ここの部分を回避してインプラントを打つ手術法が多いのが現状です。しかし本来なら、この「上顎洞」に真っ直ぐに入れたほうが、術後の炎症も少なく、また長持ちのしやすさにもつながるので、当院では耳鼻咽喉科の医師にも手術やカンファレンスに参加してもらい、より良い治療へとつなげています。この手術法ですと、歯科医師が入れたインプラントを目視で確認できるので、失敗しにくいというメリットがあります。
良い歯科医院との巡り合いが、健康長寿の秘訣に
審美歯科にはどのような特徴がありますか。

単に色調や形態の回復・改善を図るためだけではなく、いわば「一歩進んだ審美歯科」を意識し診療しています。例えば噛み合わせや顔貌の治療後に歯科的かつ審美的な治療を提案します。このような本質的で包括的な医療を提供するには、そこまでするメリットを患者さんに理解してもらうことが必要です。患者さんのご要望と、医学的根拠との間で着地点を模索して治療を進めます。それだけの治療を実践するわけですから、質の面で妥協はしません。当院の隣にあるグループ内技工所と連携することで、先進のデジタルシステムを用いた精巧な補綴物提供につなげています。
先生の先進的な考え方や高い技術力はどのように育まれたのでしょうか。
私は地域の中核病院の口腔外科に勤め、手術室で骨を削ったり移植したりする仕事に携わってきました。そのおかげで治療技術も向上しましたし、自分自身の糧になったと思っています。常に進歩しようという気持ちが大切だと思っています。そうでないと誰もついて来てはくれないでしょう。スタッフには、自ら向上し続けようという意欲を持つこと、患者さんのことを第一に考え、私のことを信頼し、健康でいてくれること。そして、同僚から好かれる人間でいてほしいと伝えています。
最後に読者へのメッセージをお願いします。

良い歯科医院と巡り合ってください。それが健康長寿の秘訣です。治療後のメンテナンスを欠かさず、お年を召されても噛むことができれば、いつまでも元気ではつらつと過ごすことができます。噛むことが認知症予防にもつながり、食事も会話も楽しめて、いつまでもご家族と楽しく過ごせることにつながります。歯科医院選びで大切なことは、高い知識・技術力・設備があること、優秀な歯科衛生士がいること、チームワークが良好であること。そして歯科医師と患者さんも人と人、フィーリングが大切です。歯科医院を選ぶ際は、ぜひこれらのことをチェックしてみてください。当院では、セカンドオピニオンを求めて来院される患者さんも増えています。
自由診療費用の目安
自由診療とはインプラント/18万7000円、審美歯科(ホームホワイトニング)/3万3000円、マウスピース型装置を用いた矯正/38万5000円
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。







