小原 功輝 院長の独自取材記事
げんきの家在宅クリニック
(岐阜市/岐阜駅)
最終更新日:2025/10/14

岐阜市福富天神前にある「げんきの家在宅クリニック」は、在宅医療と緩和ケアを専門とするクリニックとして2025年4月に開業した。通院が困難な人や、終末期を自宅で穏やかに過ごしたいと願う人に対し、訪問診療や疼痛管理を中心とした医療支援を行っている。院長の小原功輝先生は、消化器内科の医師として病院勤務を経た後、長きにわたり在宅緩和ケアに携わってきた。「病気ではなく、その人自身を診たいんです」とやわらかな口調で語る小原院長。患者一人ひとりの「どう生きたいか」という想いに真摯に耳を傾け、最期までその人らしい時間を支える診療を実践している。誰もが安心して在宅医療という選択肢を持てるよう、地域に根差した医療の在り方を日々模索する小原院長に、在宅医療への想いを語ってもらった。
(取材日2025年6月13日)
その人の“どう生きるか”を支える在宅医療を届けたい
まず、小原院長のこれまでの歩みを教えてください。

木沢記念病院(現・中部国際医療センター)で消化器内科の医師として勤めました。その後、さまざまな医療機関で経験を積んできましたが、患者さん一人ひとりとじっくり向き合える診療スタイルが自分には合っているな、と感じるようになりました。病気で医療の現場を離れた時期もあるのですが、その時に「本当に自分がやりたい医療は何だろう」とじっくり考えました。復帰を考えていた時、在宅緩和ケアで知られる小笠原内科に声をかけてもらい、もともと緩和ケアに興味があったこともあって、思い切って在宅医療の世界に飛び込んだんです。院長の小笠原文雄先生のもと、在宅緩和ケアを学ぶ中で、自分ならこういう在宅医療をやってみたいという形が少しずつ見えてきました。そんな中、ご縁があって「げんきの家」グループと出会い、独立を決意しました。
自分の理想に近い在宅医療とは、具体的にどのようなことをイメージされていたのでしょうか?
在宅医療を始めた頃は、「病院で提供している医療をどこまで自宅で再現できるか」という視点でした。しかし、経験を積むうちに、それだけでは足りないなと気づいたんです。病気はその人の生活の一部にすぎず、何より大事なのは「どう生きたいか」という本人の思いなんですね。ですので、医療だけでなく福祉や介護とも連携しながら、その方の生き方を支えることが必要だと考えるようになりました。当院では「あなたらしい生き方のお手伝い」を理念に掲げていて、主役はあくまで本人とご家族です。こちらが何かを押しつけるのではなく、その方が望む生き方に寄り添って、いくつかの選択肢を提案できる立場でありたいと思っています。在宅医療の本質は、やっぱり本人の気持ちを尊重して支えていくことだと思っています。
生き方を支える医療が大切だと思うようになったきっかけはありますか?

きっかけは、ある患者さんとの出会いでした。以前の勤務先で私が担当となった高次脳機能障害や持病を抱え、一人暮らしをしていた方で、医療的にも課題が多く、性格的にもこだわりが強い方でした。当初は診療も拒まれ、対応に苦慮することもありましたが、時間をかけて関係を築く中で、その方が自分なりの生活をとても大切にしていることに気づいたんです。医療の正しさよりも、自分らしく暮らすことを優先したいという想いと生き方に寄り添い、必要な医療は提案にとどめる。それが本当の意味での“支える医療”なのではと気づきました。本人の意思を尊重しながら、柔軟に寄り添う、それが自分の在宅医療の原点です。
どのような状況でもその人らしく過ごせるよう伴走する
印象に残ったエピソードがあれば教えてください。

消化器内科で働いていた頃、今も忘れられない患者さんがいました。高齢の男性で、抗がん剤治療を続けていましたが、状況は厳しくなっていました。ご家族が「最期に温泉に連れて行きたい」と話していたのですが、悩んだ結果、治療継続を選びました。しかし病状は悪化し、希望をかなえることなく亡くなられました。治療継続は医学的には正しい選択であったと思いますが、その時「誰のために、何のために治療しているのか」と強く考えさせられました。治らない中での治療がご家族の願いを阻んだことに疑問を抱いたことが、緩和ケアに興味を持つきっかけになりました。病気が治らなくても、その人の時間をどう豊かに支えるかという視点が必要だと感じたのです。この経験が、後の在宅医療の道へつながりました。
小原院長の想いの原点となるようなお話ですね。
そうですね。もう1つ印象的なエピソードとして、以前の勤務先の在宅医療で関わった末期がんの患者さんのことが浮かびます。腸閉塞を起こしやすい状態で、普通なら食事を控え点滴中心の対応をしますが、その方は「おいしい物を食べたい」と強く望まれました。旅行先で好きな食事を楽しみながらも、その度に痛みや詰まりを経験されたそうですが、ポジティブに生き抜かれました。私はその姿を見て「理解し納得した上で自分の意思で生きる人は、強く、幸せに見える」と実感しました。医療従事者としてはリスクを伝えつつも、その意思を尊重し、応援することが大切です。私たちの役割は「その時を迎えるまでどう生きるか」を支えることです。どんな状況でも、その人らしく過ごせるよう伴走し続けたいと思っています。
診療時、大切にされていることはありますか?
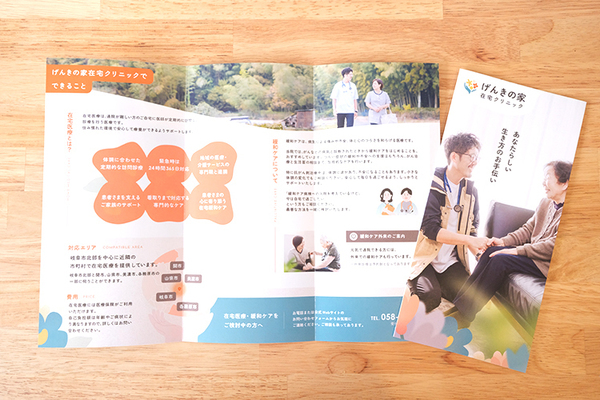
患者さんの話をじっくり聞くことが何より大切だと考えています。「話しても大丈夫」と思ってもらえるよう、和やかな雰囲気づくりを心がけています。スタッフも患者さんと接する際は丁寧で明るい対応をしてくれていて、そのおかげでクリニック全体が誠実で明るいイメージになっていると思います。在宅医療ではその人の家に伺うため、写真や趣味の品などから人生や価値観を感じ取ることも大切な技術です。また、ご家族の想いや負担にも目を向けることも重要です。特に病状が重くなると、ご家族の疲労も大きくなりがちですから、精神的・身体的な負担をできるだけ軽くする方法を常に考えています。ご家族が無理せず支えられる環境を整えることも、私たちの大切な役割だと思っています。
在宅医療も選択できることを、多くの人に知ってほしい
実際に、どういった患者さんが利用されていますか?

在宅医療では、がんの終末期で「自宅で過ごしたい」という患者さんへのケアが多く、疼痛管理や必要な医療的サポートを行っています。ただし、それに限らず、通院が難しくなった方への薬の配達や体調確認、施設に入所している方の軽い不調への対応など、患者さんの背景や状態に合わせて幅広く支援しています。今後はまず、在宅医療とは何かを知ってもらうことが大切だと思っています。無理して通院をしている方や、家族が苦労して付き添うケースも少なくありません。自宅でのケアという選択肢があると知るだけで、負担は大きく軽減されるはずです。望まない入院を避けるためにも、「知らなかったから選べなかった」という方たちに、在宅医療の存在を届けていきたいと思っています。
訪問診療は、どのように利用したらいいのでしょうか?
入院や通院中の方なら、病院の地域連携室や医療相談室で相談でき、地域の在宅医療ネットワークを紹介してもらえます。また、介護保険を利用している方は、ケアマネジャーに相談すると医師につなげてくれる場合もあります。当院へのお問い合わせは、ホームページの問い合わせフォームからご連絡いただくのが一番手軽かと思いますが、直接電話でのお問い合わせも大歓迎です。通院がつらくなってきたと感じたら、ぜひ早めにご相談ください。迷った場合でも遠慮せず、まず一度相談してみてください。気軽に相談できる環境づくりが大切だと考えています。
最後に、今後の展望と読者にメッセージをお願いします。

私たちの目標は、「この地域に当院があって本当に良かった」と感じていただけるようになることです。もっと広い範囲の方々にもそう思ってもらえるようになればいいですね。病気になったり体が弱ってしまったりしても、当院があるから安心して過ごせる、そんな存在になれたら最高ですね。まだまだ先の話かもしれませんが、そういったクリニックをめざして日々取り組んでいきたいと思っています。そして、もしご縁があって当院をご利用される際は、ご本人やご家族の希望や願いをしっかりと受け止め、その実現に向けて全力を尽くします。あなたらしい生き方のサポートができるよう、精いっぱい努めますので、どうぞよろしくお願いします。






