佐々木 康裕 院長の独自取材記事
ささき内科クリニック
(練馬区/光が丘駅)
最終更新日:2025/06/11

練馬区土支田2丁目の街道沿いにある医療モールの2階に、2025年4月にオープンしたのが、「ささき内科クリニック」だ。明るく落ち着いた雰囲気の院内が印象的な同院。佐々木康裕院長は、製薬会社で研究員を務めた後に医師へと転身したという、ユニークな経歴の持ち主。同院では、内科一般の診療に加え、糖尿病の専門的な診療や内視鏡検査など、幅広い医療を提供。研究者および医師として培った経験や知識を生かし、地域の人々に信頼される「かかりつけ医」として、地域医療への貢献をめざしている。「健康に関して気になることがあれば、小さなことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください」と、優しい笑顔で穏やかに語る佐々木院長に、クリニックの特色や地域医療への思いを聞いた。
(取材日2025年5月18日)
地域の人々から頼られるかかりつけ医をめざす
最初にクリニックを紹介していただけますか?

当院は、地域の皆さんが健康について気軽に相談できる「かかりつけ医」をめざし、今年4月に開院しました。私は、総合内科、糖尿病、消化器、消化器内視鏡が専門で、それらの専門的な診療はもちろん、風邪などのよくある症状や、練馬区の特定健診をはじめとする各種健診にも幅広く対応しています。この周辺には、内科、特に糖尿病を専門的に診療できるクリニックがほとんどないようでした。私は宮城県の出身ですが、東京に出てから10年以上、ずっと練馬区で暮らしています。妻の両親も含めてなじみの深いこの場所で、地域の皆さんのお役に立ちたいという思いで開業を決意しました。
院内の雰囲気や設備でこだわったところはありますか?
まず、清潔感を重視しました。加えて、待合室の壁や椅子には私の好きな木目調のデザインを多く取り入れ、患者さんが落ち着ける、居心地の良い空間づくりを心がけています。設備面では、先進の内視鏡システムを導入しています。特に、胃の内視鏡検査システムは、AIによる診断補助機能を搭載しています。また、エックス線撮影装置にも同様に、AIによる診断支援機能が備わっています。病院であれば、検査画像に対して複数の医師によるダブルチェックが行われますが、クリニックでは基本的に医師一人で対応します。こうした環境でも診断の質を保つため、AI技術を活用できる機器を導入しました。そのほか、糖尿病の指標であるHbA1c(ヘモグロビンA1c)を即日測定できる血液検査装置や、内視鏡検査後に休憩するリカバリールームも用意しています。
ご専門の糖尿病の診療について教えてください。

糖尿病は、初期の段階では血糖値が高いだけで、ほとんど自覚症状が現れません。しかし、その間も体内では少しずつ臓器がダメージを受け続けています。そのため、健診などを通じて早期に糖尿病を発見し、初期のうちに治療を始めることが非常に重要です。初期であれば、食事・運動指導による生活習慣の改善によって血糖値のコントロールをめざすことで、合併症を防ぐことも期待できます。治療の指標としては「HbA1c」があり、これは過去1〜2ヵ月間の血糖の状態を反映するもので、治療の経過を把握しやすい点が特徴です。この数値が改善すれば、患者さんご自身も成果を実感でき、治療のモチベーションにもつながるでしょう。こうした指標もうまく活用しながら、患者さんと一緒に無理のない形で、長く続けられる治療をめざしていきたいと考えています。
専門的な糖尿病診療や内視鏡検査にも対応
糖尿病治療で大切にしていることは何ですか?

近年、糖尿病治療は大きく進歩しており、優れた治療薬が次々と登場して、治療の選択肢も広がっています。ただ、私はHbA1cといった指標の値を良くすることだけでなく、心不全や腎障害といった合併症の予防こそが、より重要だと考えています。糖尿病の患者さんには、高血圧や脂質異常症など、複数の生活習慣病を併せ持つ方も多く、これらが相互に影響し合って、結果的に腎不全に至り、人工透析が必要になるケースも少なくありません。最近では腎臓を保護する効果が期待される薬剤など、新しい選択肢が登場しています。そのような合併症を防ぐためにも、こうした薬を積極的に活用しながら、患者さん一人ひとりに合った治療を通じて、長期的な視点で合併症の予防に努めていくことが、これからの糖尿病治療には欠かせないと考えています。
内視鏡検査にも対応しているのですね?
糖尿病の患者さんの中には、大腸がんを併発している方が意外と多いんです。ですが、患者さんが「胃が痛い」「下痢や便秘が続く」などの症状を訴えた場合に、ほかの医療機関に紹介して検査を受けてもらうのでは、患者さんの負担になります。そこで私は、消化器内視鏡検査も自院で対応できるようにと考え、研鑽を積んできました。当院では、胃と大腸の内視鏡検査の両方に対応しており、鎮静剤を使用するなど、患者さんができるだけ楽に受けられるように配慮しています。また、胃と大腸の内視鏡検査は、同日に続けて受けていただくことも可能です。さらに、検査結果については、原則として当日中にご説明しています。40歳を過ぎた方や、ご家族に胃がんや大腸がんの既往がある方はリスクが高いですから、がんの早期発見のためにも、ぜひ一度内視鏡検査を受けていただきたいですね。
他に力を入れていることはありますか?

糖尿病や高血圧の方が、睡眠時無呼吸症候群を併発しているケースも少なくありません。実際、睡眠時無呼吸症候群を治療することで糖尿病や高血圧の治療がうまく進みやすくなることも多く、患者さんからのニーズも高いため、この病気の治療には力を入れて取り組んでいきたいと考えています。かつて、睡眠時無呼吸症候群の検査には入院が必要でしたが、当院の睡眠時無呼吸症候群検査では、業者から機器が患者さんの自宅に送付され、患者さんはそれを就寝時に装着するだけで完了します。使用後は、装置を返送してもらえれば解析が行われます。また、CPAP(持続陽圧呼吸療法)が必要な場合も同様に、装置が自宅に届くようになっています。睡眠時無呼吸症候群は、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患のリスクも高めることがわかっています。睡眠時無呼吸症候群が心配な方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
患者の思いに応えることを大切に
診療の際に心がけていることはありますか?

患者さんが何を求めているのかをくみ取ることです。詳しい検査をしてほしいのか、薬だけもらえれば良いのか。逆に、できれば薬は飲みたくないという人もいます。ですから、私の考えを押しつけるのではなく、できるだけその思いに応えられるように心がけています。加えて、診療では「褒める」こと。例えば、HbA1cの値が良くなっていたら、「すごく頑張りましたね」と声をかけます。大人になると、誰かに褒められることって意外と少ないものですから、頑張った結果をしっかり評価して、前向きな気持ちで治療に取り組めるようにしたいと思っています。努力が結果につながることで自信が生まれ、それが次のモチベーションにもなると考えています。
話は変わりますが、先生はなぜ医師を志したのですか?
私は、医師になる前は製薬会社で研究員として働いていました。その時、糖尿病の新薬の開発に携わっていたのですが、次はその薬を使う側として、実際の治療に関わりたいと思ったんです。加えて、当時から「これから先、糖尿病の患者さんはさらに増えていく」といわれていて、そういった意味でもこの分野に関心がありました。実は、私はあまり話すのが得意なほうではありません。研究者の頃は人と話す機会もそれほど多くありませんでしたが、医師になってからは患者さんとコミュニケーションを取る中で、感謝の言葉をいただいたり、笑顔になってもらえたりすることがあり、そういう瞬間に「医師になって良かったな」と思いますね。
最後に今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。
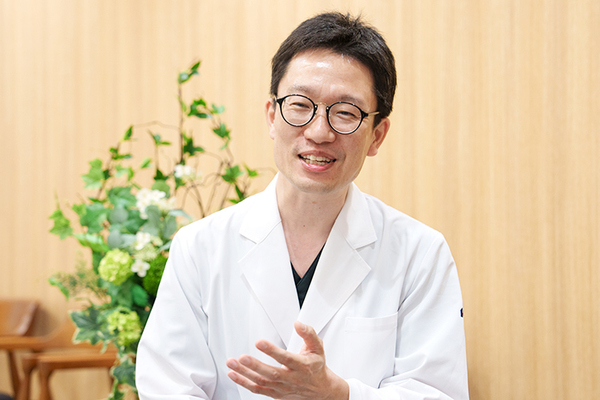
当院では「内科一般」「糖尿病」「消化器」の3本柱を中心に、検査や治療を一貫して行える体制を整え、できるだけこのクリニック内で完結できる医療の提供をめざしています。地域の皆さんにまずは健診などを通じて当院を知っていただき、少しでも健康に貢献できればと考えています。専門分野に限らず、風邪などの一般的な体調不良でも気軽に受診していただける「かかりつけ医」としての役割も果たしたいと思っています。健康に関して気になることがあれば、小さなことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。






