松浦 賢太郎 先生、千葉 伸太郎 先生の独自取材記事
新橋睡眠・内科クリニック
(港区/新橋駅)
最終更新日:2025/06/13

新橋駅から徒歩約1分のビルの7階に2025年2月オープンしたのが「新橋睡眠・内科クリニック」だ。睡眠時無呼吸症候群に対し豊富な知識や経験を持つ医師が在籍し、専門性の高い診療の提供をめざす同院。患者に合わせて幅広い治療の選択肢を用意しているのと同時に、根治をめざした治療にも力を入れている。「私自身も長年、睡眠時無呼吸症候群に悩まされてきましたので、患者さんの苦労はよくわかります」と話す松浦賢太郎先生と、「元気になる睡眠医療を皆さんに届けたいですね」と語る千葉伸太郎先生に、同院の取り組みや診療にかける思いなどを聞いた。
(取材日2025年5月21日)
専門性の高い睡眠時無呼吸症候群の診療をめざす
最初にクリニックを紹介してください。

【松浦先生】当院は、風邪や生活習慣病をはじめとする一般内科と、睡眠時無呼吸症候群の専門的な診療を行うクリニックとして、今年の2月に開業しました。一般内科は午前中に、松浦友里奈院長が診療しています。午後は睡眠時無呼吸症候群の診療を、私と千葉伸太郎先生が担当しています。睡眠時無呼吸症候群については、東京慈恵会医科大学などの専門施設と連携しながら、エビデンスに基づいた質の高い治療の提供をめざしています。当院で対応が難しい精密検査や外科的治療が必要な場合には、連携する専門施設で行う体制を整えています。
特徴は、どのようなところでしょうか?
【千葉先生】まず、睡眠時無呼吸症候群を専門とする医師が診療を行っている点です。睡眠時無呼吸症候群といっても、重症度や病態、原因などは患者さんごとに異なります。そのため当院では、専門の医師による的確な診断をもとに、一人ひとりに合わせた個別化医療の提供をめざしています。また、治療法としてはCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)が一般的ですが、当院ではこの治療をオンライン診療で受けられる体制も整えています。さらに、CPAPは継続が重要な治療ですが、患者さんからは「いつまで続ければ良いのか?」といった疑問がしばしば寄せられます。当院では、そのような患者さんに対して、睡眠時無呼吸症候群の根治をめざす治療を提案できることも特徴です。
治療は、どのように進めるのですか?
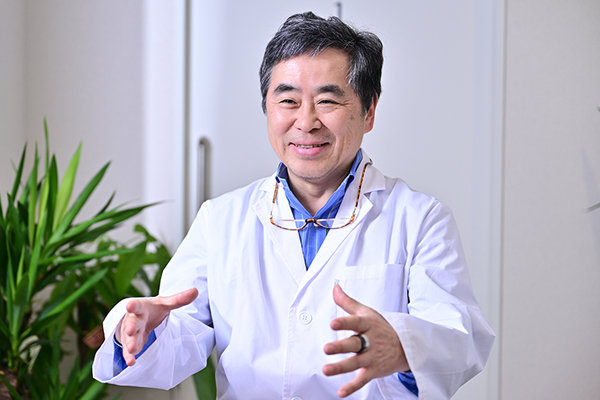
【千葉先生】睡眠時無呼吸症候群の最大の問題は、合併症を引き起こす可能性があることです。放置すれば、健康寿命が短くなるリスクも高まりまので、合併症の発症を防ぐことが治療の第一目標です。さらに、日中の強い眠気を改善するなどQOLの向上や、安全性の確保も重要です。これらの観点から、まず選択される治療法がCPAPです。ただし、CPAPは睡眠中の呼吸をサポートするだけで、根本的に解決する治療ではありません。そこで、次のステップとして患者さんごとの原因を見極め、それに応じた治療が必要です。例えば、最も多い原因は肥満ですが、その場合は、当然ながら減量です。減量は、基本的に患者さん自身が取り組むことですが、自己管理が難しい場合には連携の大学病院の肥満に特化した外来で、栄養指導を受けてもらうこともできます。さらに、選択肢として胃を小さくする手術や、自由診療ですが薬物療法も考えられます。
睡眠時無呼吸症候群に対する多彩な治療の選択肢を用意
そのような治療を受ければ、睡眠時無呼吸症候群は根治するのですか?

【千葉先生】睡眠時無呼吸症候群の根本的な治療は、決して簡単なものではありません。減量をはじめ、さまざまな治療を組み合わせるなど、非常に個別性の高いアプローチが求められます。それによって、将来的にCPAPを不要とすることをめざします。しかし、実際にはCPAPの使用をすぐに終了できるケースは限られます。例えば、減量によって症状が軽くなった場合には、顎の小さい人であればマウスピースへ変更する。さらに、マウスピースから最終的には装着なしでの睡眠をめざしますが、この過程は容易ではありません。ですが、CPAPからマウスピースへ移行できれば、特に出張などの多い勤労世代にとっては装置の携帯や使用に関する負担が軽減されるなど、QOL的な面でもメリットは大きいと思います。
ほかに治療方法はありますか?
【千葉先生】CPAPには、継続率という課題があります。世界的なCPAPの長期使用継続率は約50%とされており、日本では正確な統計はないものの80%前後と見られています。それでも一定数の患者さんが継続できていないのが現状です。つまり、CPAPだけですべての患者さんに対応するのは難しいのです。そのため、「ポストCPAP」の選択肢として「舌下神経電気刺激療法」があります。睡眠時無呼吸症候群に対するペースメーカーのような装置を体内に埋め込み、夜間のみ舌の筋肉に電気刺激を与え、気道の閉塞を防ぐのです。舌下神経電気刺激療法は、CPAPが無効であることなど一定の基準を満たした場合のみ適応になりますが、当院ではこの治療の提案もすることが可能です。
CPAPの継続はなぜ難しいのでしょうか?

【松浦先生】CPAPの長期使用継続率が約5割にとどまる理由の一つに、導入時のサポートが不十分であることが挙げられます。CPAPは、患者さんによっては練習が必要であり、正しく使えるようになるまでに時間がかかる場合があります。実際、装着時の呼吸の仕方にはちょっとしたコツがあるのです。当院では、CPAP導入時に専門スタッフが丁寧に対応し、必要に応じて院内で練習を行ってから、ご自宅での使用につなげています。また、CPAPの装置は機種によって使用感や呼吸との相性が異なることもあるため、当院では複数の機種を取りそろえ、患者さんに合った装置を選んでいただけるようにしています。もし合わないと感じた場合には、別の機種への変更にも柔軟に対応しています。
元気になる睡眠医療を届けたい
オンライン診療にも力を入れているとか。

【松浦先生】睡眠時無呼吸症候群は、特に男性の勤労世代が多いんです。そして、治療もCPAPを続けながら減量に取り組むなど、内容は比較的シンプルなんですね。その確認を、例えば毎月、数時間もかけて通院するのはすごく効率が悪いですよね。ですから、治療内容がある程度固まったら、できるだけアクセスが良く、患者さんがフレキシブルに通院できるほうが、モチベーションの維持にもつながります。それらのことを考えると、オンライン診療が適しているのです。当院では、落ち着いている患者さんには、3ヵ月に1回のオンライン診療にしていますが、CPAPには通信機能があり、その間もデータはこちらに送られてきています。そのデータを見て、何か問題のある患者さんには、3ヵ月待たなくてもこちらから連絡して、受診していただきます。
診療の際に心がけていることはありますか?
【松浦先生】私自身、睡眠時無呼吸症候群でずっと苦労してきました。「いびきがうるさいから廊下で寝て」なんて言われたことも(笑)。そうした経験があるからこそ、患者さんのつらさは本当によくわかります。そのため、一人ひとりを丁寧に診ることを常に心がけています。意識しなくても、自然と親身になってしまいますね。
【千葉先生】「病気を診ずして病人を診よ」。これは東京慈恵会医科大学のモットーであり、それが第一です。その中で、睡眠時無呼吸症候群においては、例えばCPAPを導入すればそれで治療が完了したかのような対応が一般的に行われ、「患者さん」そのものを診ていない面があります。だからこそ、今日お話ししたような個別化医療を実践し、その方に最適な治療を提供することを大切にしています。
最後に今後の抱負と読者へのメッセージをお願いします。
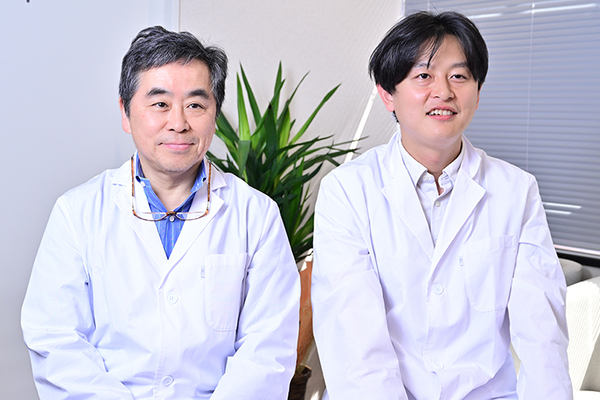
【千葉先生】現在の睡眠医療は、少し誤解されている部分があります。例えば、CPAPで無呼吸指数を下げることが治療の目的とされがちです。つまり、症状を軽減して安定させることがゴールのようになっている。しかし本来の睡眠とはそういうものではありません。睡眠は、しっかり眠ることで元気になり、幸せを感じられることが何より大切です。元気になる睡眠医療を皆さんに届けたいと思っていますし、それをここから発信していきたいですね。
【松浦先生】いびきや無呼吸は、私自身も長年悩まされてきましたので、まだ診察を受けていない方にも広く関心を持っていただき、治療が必要な場合には、ぜひお手伝いしたいと考えています。加えて、きちんと診断されていないケースや、医学的根拠が不明確な民間療法のようなものが広まっている現状もあります。だからこそ、正しい情報の提供と適切な治療方針の提案ができるよう努めていきたいです。
自由診療費用の目安
自由診療とは肥満の薬物療法/2万円~






