林 哲朗 院長の独自取材記事
みそら内科クリニック目黒
(目黒区/学芸大学駅)
最終更新日:2025/08/19

東急東横線・学芸大学駅から徒歩圏内、目黒区の住宅街に2024年7月に開院した「みそら内科クリニック目黒」は、医師とスタッフが一丸となり、医療と生活、福祉の面から患者を支えていくことをモットーとしている。院長の林哲朗先生は日本内科学会総合内科専門医・日本糖尿病学会糖尿病専門医であり、家庭医療も専門分野だ。同クリニックでは専門性がどのように生かされているのか、また、所属するスタッフらの役割について、林先生に詳しく聞いた。
(取材日2025年3月18日)
幅広い世代の患者に横断的な診療を行う
院長は総合内科と糖尿病の専門家ですが、もう一つの専門である家庭医療とは何ですか。

家庭医療とはプライマリケアを専門領域とする医療分野で、小児から高齢者まで幅広い世代を対象に、疾患を横断的に診ます。よって、心臓や肺などいくつかの臓器にまたがる複合的な疾患にも対応します。その上で、患者さんのメンタル面や生活面にもアプローチして包括的に診察することが大きな特徴です。施設で例えるなら地域の診療所のようなものでしょうか。大規模病院で目にする総合内科・総合診療科は、家庭医療の領域と重なる部分がいくつかあると思いますが、地域でのプライマリケアの実践により重点が置かれるのが家庭医療の特徴です。
開院した理由を教えてください。
大規模病院では患者さんと向き合う期間が入院中の1週間や2週間くらいだったりして、治療はできても生活面やメンタル面までフォローする時間がありません。患者さんが抱える問題をピックアップできても、患者さんが退院したら、その後は地域のクリニックのようなプライマリケアの医師にバトンタッチすることになるからです。それならばクリニックを開院して自分自身がプライマリケアの側に行き、一人ひとりと時間をかけてじっくり向き合い、患者さんの健康をサポートしていきたいと思いました。
このエリアに開院した理由は何でしょうか。

私は慶應義塾大学と東京慈恵会医科大学大学院・ハーバード公衆衛生大学院を経て、国立病院機構東京医療センターに20年近く在籍し、診療をしていました。当院が休みの日は後進指導をしに行くことがあり、東京医療センターとは今もつながりがあります。このエリアは東京医療センターから近く、医療連携がしやすいことが理由の一つですね。また、近隣にある昭和大学病院、東邦大学医療センター大橋病院、共済病院、東京都立広尾病院、慶應義塾大学病院とも連携しています。当院のスタッフは東京医療センターでかつて一緒に働いていたり、今も在籍していたりするメンバーです。当院の医師は全員が総合内科や家庭医療を専門にしているので、どの医師が担当しても同じ水準の幅広い診療が可能です。
総合内科の専門家がいるクリニックにはどんな強みがありますか。
総合内科の医師は、内科の全領域で外来から入院で治療するレベルの疾患を診ます。カテーテル検査や内視鏡検査などは専門の医師に依頼しますが、一般的な疾患の診察であれば対応するため、患者さんが複数の病院に通う手間を省いたり、どの科に行けば良いのかわからない患者さんを受け入れたりすることができます。例えば糖尿病を罹患している方が脳梗塞を発症し、さらに肺気腫を患った場合、本来3つの科で診察を受けるのですが、総合内科があれば1ヵ所で済みます。当院なら私が糖尿病の専門家でもあるので、横断的な診断に加えて生活習慣病の専門的な診察やアドバイスができます。
生活習慣病・感染症・がんの予防に注力
幅広い年齢層への対応と横断的な診察の他に、クリニックの特徴はありますか。

予防医療に力を入れています。大きく分けると3つあり、生活習慣病の予防、感染症の予防、そしてがんの予防です。まず生活習慣病は、糖尿病や高血圧、脂質異常症の場合、治療より予防がメインになります。理由は患者さんに目立った自覚症状がなく、日常生活に困っていないことが多いからです。その中でも糖尿病は高血圧、脂質異常症を起因とし、生活の質を低下させる深刻な合併症を引き起こしやすいです。年齢を重ねたとき心血管疾患などの重篤な病気にならないよう“予防”していくため、薬に加え食事や運動など生活面からも患者さんをサポートする仕組みを考えます。感染症予防としては、各種ワクチン接種や定期接種、生後2ヵ月の赤ちゃんのワクチン接種も行っており、高齢者には、個々の基礎疾患を鑑みた上でワクチン接種プランを提案しています。がん予防は、年齢やリスクに応じたスクリーニング検査の推奨など、早期発見につながる取り組みを行います。
こちらのクリニックでは、生活習慣病の予防や治療をどのように行っていきますか。
当院には管理栄養士や社会福祉士が在籍しており、クリニック全体で患者さんをサポートしていきます。生活面を支えることについては、医師より管理栄養士さんのほうが長けています。また当院の看護師は豊富な実務経験に加え、診療とケアを統合した高い専門性と看護実践能力を有しています。社会福祉士は介護保険などの介護・福祉の知識があるので、例えば長年生活習慣病を患っている方が、歩行が困難になってきたときにどのようなサービスが必要なのか、どのような手続きが必要なのかなどをアドバイスができます。大規模病院や在宅医療中心のクリニックには在籍していても、社会福祉士が一般のクリニックにいるケースは珍しいと思います。設備面では、ヘモグロビンA1cや血糖値の当日検査が可能な機材を導入し、糖尿病の病態が悪化しているときや緊急性のある場合に使用できるようにしています。
生活習慣病を糖尿病の専門家が診るメリットは何でしょうか。

生活習慣病の症状には糖尿病や高血圧、高コレステロールなどがあり、中でも糖尿病の対応は特殊で複雑です。合併症によって視力が低下する、腎臓の機能が低下して透析が必要になるなど、深刻な事態を回避するためにどうコントロールしていくかが重要なのですが、糖尿病は新薬がどんどん開発されており、飲み薬の他に注射製剤もある。例えば、肥満の方には体重をできるだけ減らすことに有用な薬を、高齢の方には副作用が少なくて低血糖症状になりづらい薬を、寝たきりの方なら薬を飲んだり管理したりすることが難しいだろうから週1回使える注射製剤にして介護している方が使える薬をメインにする。そんなふうに、患者さんの状態に合わせてきめこまやかに対応できるところが糖尿病専門家の強みといえるでしょう。
クリニック全体で患者の健康をサポート
通院する患者層を教えてください。

乳児から90代の高齢の方まで、さまざまな世代の患者さんが通院されています。生活習慣病では30代後半から上の世代が大半です。小児科の受診も多く、小さなお子さんを連れて一家総出で来院されるということもありました。なので、風邪やインフルエンザが流行っている時期は、乳児ワクチンの小さいお子さんはカウンセリング室で待機できるようにしたり、生活習慣病の患者さんと発熱した患者さんの待合室を離したり、できる限りの方法を考えて対応しています。診察室では病気の話だけするのではなく、雑談も交えて、患者さんが言いたいことや好きなことを話せるように意識していますね。患者さんとの交流から、公共のスポーツ施設や気持ち良く散歩できる近隣の公園について情報を得るので、それを他の患者さんに教えることもありますよ。
病気を予防するために先生がお勧めすることは何ですか。
毎年健康診断を受けることでしょうか。結果が出て受診勧告があっても放っておいてしまう方が結構いるのではないかと思いますが、健診結果をクリニックに持参すれば、治療の必要はなくても生活習慣の改善が必要なことが判明したりします。生活習慣病はかけ算で、悪い状態×放置した期間によって動脈硬化などさまざまな症状の進行が変わっていくので、早い段階からコントロールして進行を抑制できるよう、医師に相談してみてください。
最後に読者へのメッセージをお願いします。
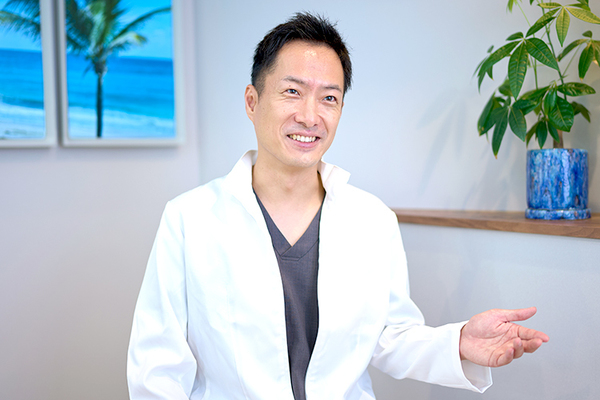
発熱や腹痛などの急性疾患や糖尿病・高血圧・高コレステロール血症など生活習慣病の治療に限らず、通院する患者さんを生活面や福祉の面からサポートしていきます。慢性疾患については、患者さんが無理なく、自分らしく生活できるような治療法を考えていきます。スタッフと協力し、医師だけでなくクリニック全体で幅広い世代の方の健康を維持できる体制をつくっていきますので、お気軽に足をお運びください。






