肝臓疾患は専門の医師に相談
エコー検査で脂肪肝も迅速に診断
ぎょうとく内科・内視鏡クリニック
(台東区/浅草橋駅)
最終更新日:2025/11/21


自覚できる症状が出にくいために、気づきにくい肝臓疾患。しばしば話題になる脂肪肝だけでなく、ウイルス性の肝炎を発症する人も多く、そのほかにも肝臓の疾患はさまざまな種類がある。また、脂肪肝は放置すれば肝硬変や肝臓がんといった、さらに重篤な疾患を引き起こすこともあり、早期に発見してケアすることが重要だ。「ぎょうとく内科・内視鏡クリニック」の行徳芳則院長は、「肝臓の疾患が進行すると、元の状態に戻すことは困難。だからこそ、病状が進行してしまう前に早期発見するための対応策が大切です」と話す。肝臓疾患の専門家である行徳院長に、肝臓疾患の種類や検査方法、治療法などについて、詳しく話を聞いた。
(取材日2025年3月14日)
目次
脂肪肝を放置すると肝硬変や肝臓がんのリスク増大。血液検査と画像検査で状態を把握して適切なケアを
- Q肝臓の病気にはどのようなものがありますか?
-
A

▲日本肝臓学会肝臓専門医である院長。穏やかで優しい人柄が魅力
現在、日本で最も多いのはB型肝炎やC型肝炎といったウイルス性肝炎とされています。また、肝細胞に過剰に脂肪が蓄積した脂肪肝も増えていますね。脂肪肝には基本的に症状はありませんが、脂肪の過剰蓄積は炎症を引き起こし、放置すると肝硬変や肝臓がんにつながる恐れが。脂肪肝による疾患はNAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)とNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)に分類され、脂肪が蓄積しているだけのNAFLDに対して、NASHはひどい炎症が起きているものを指します。NASHは肝臓がんのリスクがさらに高くなるため注意が必要。他の肝臓疾患としては自己免疫性肝炎や薬剤性肝障害、アルコール性の肝障害などがあります。
- Q健康診断の数値や日々の症状で、気をつけることはありますか?
-
A

▲手製の資料を用いてわかりやすく説明している
血液検査を受けられる場合は、肝臓の機能を調べるALTという数値に着目します。ALTの数値が高くなっていると指摘を受けた方は、一度クリニックを受診して、原因を調べてもらいましょう。肝臓の疾患は、初期の段階だと症状がないことが多いため、自覚することは難しいのですが、何か兆候があるとすれば浮腫(むくみ)の症状がおなかや足などに見られた場合、肝臓の疾患が関わっている可能性があります。それらの症状が現れていて、まだ受診されたことがない方は、肝臓を調べてみていただければと思います。
- Q肝臓の検査はどのように行うのでしょうか?
-
A

▲エコー検査で肝臓の脂肪量をチェックできる
大きく分けると、血液検査と画像検査です。ウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎などは、血液検査によってある程度、診断がつけられることが多いです。一方、脂肪肝などは画像検査で診断できることが多いため、エコー検査を行って肝臓の状態を見ます。エコー検査では肝臓の脂肪量も同時に計測し、より重症度が高い方に対してはこまめなフォローを心がけています。エコー検査のみで情報量が足りない場合は、MRIやCT検査といった画像検査を組み合わせることもありますが、検査の手軽さや侵襲性の低さの点でも、まずはエコー検査が行われることが多いですね。また当院では、先進の機器を用いて肝硬度測定を行う場合もあります。
- Qこちらで対応している肝硬度測定について教えてください。
-
A

▲先進の機器を導入し肝硬度測定を行う
肝硬度測定とは、体表から振動と超音波を送り、その伝わり方から肝臓の硬さと脂肪量を測定するものです。初期段階の肝硬変の発見をはじめ、脂肪肝や慢性肝炎の発症の可能性を調べることができ、早期発見にとても役立っています。この測定では結果が具体的な数値で表示されるので、他の症例データと併せることで、より適切な病態の評価につなげられるんですよ。また、短時間・低侵襲である点も特徴の一つです。肝生検のように、入院が必要となる検査をしなければわからなかった情報の取得を、肝硬度測定により日帰りで図れるようになりました。
- Q肝臓疾患の治療法や対策について教えてください。
-
A
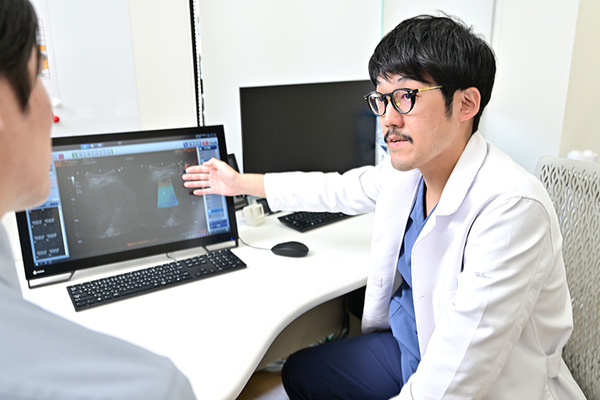
▲患者自身のために定期検査が大切
肝臓は病態が進行すると、元の状態に戻すことは困難です。例えば、生のレバーを焼くと固くなってしまうように、一度固くなった肝臓は、以前のやわらかさにはなかなか戻らないため、いかに現状から悪化させずに維持するかが大切です。そのために、定期的な採血検査や栄養管理を行います。アルコール性の肝障害であれば減酒や禁酒をし、脂肪肝なら体重を落として食事の管理、運動の習慣づけなどを行います。そのほか、B型肝炎やC型肝炎ならば原因となるウイルスの排除、自己免疫性肝炎であればご本人の生活習慣が原因ではありませんので、通院で定期的な経過観察をすることが重要です。






