臼井 靖博 院長、宇野 洋美 先生の独自取材記事
西新宿内科つながりクリニック
(新宿区/西新宿駅)
最終更新日:2025/09/25

開業から1年を迎える「西新宿内科つながりクリニック」は、心臓、肺、脳をそれぞれ専門とする3人の医師が連携して診療している。特徴は、それぞれの疾患を単独で診る「点」の医療ではなく、関係して発症する疾患も包括的に診療する「面:つながり」の医療で、「患者さんを丸く診る」こと。疾患ごとに複数のクリニックを通院している人や、症状の裏にある別の疾患に気づかず過ごしている人にとっては、同院の受診が生活の質を向上させるきっかけになるだろう。「疾患のつながり」に着目する診療の特徴と、つながりの医療にかける思いについて、臼井靖博院長と宇野洋美先生に話を聞いた。
(取材日2025年5月9日)
心臓・肺・脳の専門家が連携し、包括的な医療を実践
まずはクリニックの特徴を教えてください。

【臼井院長】当院は、脳神経内科の宇野洋美先生、循環器内科の田中宏和先生、循環器内科・呼吸器内科・睡眠時無呼吸症が専門の私がそれぞれの診療科を担当しつつ、互いに連携して包括的な医療を実践しています。高血圧症、糖尿病などの生活習慣病、狭心症、心不全などの循環器疾患、喘息、COPDなどの呼吸器疾患、脳梗塞、パーキンソン病、認知症、片頭痛などの脳神経疾患、そしてこれらに深く関係する睡眠時無呼吸症の専門的な治療を行っています。加えて、睡眠時無呼吸症と心不全、喘息と片頭痛のように科をまたいで関連する疾患の包括的な治療にも取り組んでいます。開業から1年がたち少しずつコンセプトが浸透し、こうした患者さんを「丸く診る」つながりの医療に期待を寄せて、近隣オフィスで働く方やお住まいの方だけではなく、遠方から受診される方も増えています。
無関係に見える疾患同士が、実はつながっているということは多いのですか?
【臼井院長】はい。特に心臓、肺、脳には深い関連性があることがわかっています。たとえば睡眠時無呼吸症と喘息の合併で、相互の重症化に影響します。また、睡眠時無呼吸症は高血圧や心不全、狭心症、心房細動、脳梗塞、認知症とも相互関係があります。肺の病気であるCOPDには不整脈や狭心症が多く、意外なところで喘息と片頭痛の合併もよく見られます。
【宇野先生】私たちはこれまでの診療経験から「心臓、肺、脳は密接につながっており、包括的な診療が大切」という共通認識を持っています。そのため咳の症状で受診した患者さんでも、診察で「頭痛はありませんか?」と尋ねます。それによって片頭痛の発見につながるケースがあるからです。多くの方は「まさか別の臓器の病気が関連しているなんて」と驚かれるかもしれませんが、一つのクリニックであらゆる側面から診ることで、患者さんの不調を解決したいと考えています。
つながりに気づいた際、どのように連携されていますか?

【宇野先生】その場ですぐに声をかけ合います。信頼関係がありますから、そのあたりはスムーズですね。診察室も隣り合わせで物理的にも声をかけやすい体制になっています。これまで症状ごとにクリニックや病院を受診していた方には喜んでいただけると思います。
【臼井院長】例えば喘息患者さんのお話の中で、片頭痛で悩んでいることがわかり、お互いの疾患のつながりや併せて治療することの大切さをお話しし、すぐ宇野先生に声をかけて診察をお願いします。
適切な診断と包括的治療で、患者とともに歩む医療を
それぞれのご専門分野について伺います。臼井先生は循環器と呼吸器がご専門ですね。

【臼井院長】聖路加国際病院で臨床研修後、武蔵野赤十字病院で呼吸器疾患全般を学び、東京医科大学では循環器疾患の研鑽を積みました。当時は睡眠時無呼吸症と循環器疾患の関係性が注目され始めた頃で、実際、夜の病棟には、大きないびきをかき一時的に呼吸が止まっている患者さんが多くいらっしゃいました。そこで循環器内科、耳鼻咽喉科、口腔外科のチームによる睡眠時無呼吸症の外来、検査、治療体制を立ち上げました。その後、地域の医院に勤務してからは、呼吸器疾患の患者さんにも睡眠時無呼吸症の合併が多いことを経験しました。このような経緯から、当院では睡眠時無呼吸症の検査が行える体制を整備し、検査結果に基づき、CPAP、連携する歯科でのマウスピース作製などの治療方針を提案しています。併せて、併存する生活習慣病や循環器、呼吸器、脳神経疾患の治療も同時に行うことで、患者さんのお悩みに幅広く応えられるよう努めています。
宇野先生がご専門の脳神経内科で、最近目立つ疾患や気になる症状はありますか?
【宇野先生】「頭痛」と「震え」ですね。頭痛の多くは片頭痛で、私自身も重度の片頭痛患者で、痛みを我慢して過ごしておられる患者さんのつらさはよくわかります。生活習慣の見直しや片頭痛治療薬の処方、抗CGRP抗体製剤の導入などにより、「頭痛を考えない毎日」をめざし、患者さんとともに歩む姿勢で診療しています。震えに関しては、若い方ですと「本態性振戦」が多く、内服薬で症状軽減を図ります。一方、中高年の方はパーキンソン病などの変性疾患の恐れがあるため、画像診断や近隣病院での検査を追加し、慎重に鑑別診断を進めます。パーキンソン病と診断された場合は、長期的視野を大切に、生活の質の維持をめざして薬物療法と運動療法のアドバイスを行います。認知症も増えており、ご家族の心配事やお悩みを伺い、患者さんが住み慣れた場所で安心して暮らせるよう、生活環境の整備も含め地域ぐるみで見守っていきたいと考えています。
スタッフの皆さんも非常に献身的だと伺いました。

【臼井院長】当院のスタッフは皆、自身の職種のエキスパートとして、当院の理念にあるとおり「誠実に、謙虚に、互いを尊重して」、患者さんのために切磋琢磨しています。初診患者さんや気になる患者さんへの声かけ、問診、各種検査やCPAP導入後のフォローや指導など、役割は多岐にわたり、私もスタッフから多くのことを学んでいます。
【宇野先生】当院で導入している片頭痛発作を予防する抗CGRP抗体製剤の注射療法は、状態を見極めた後、自己注射に変更するのですが、自己注射の導入説明や指導、導入後のフォローには看護師の役割がとても大きく、片頭痛診療はまさにチーム医療ということができます。このような看護師による取り組みの輪を広げるため、講演活動も始めています。
他の医療機関との連携を強化し「つながりの医療」を
内装にもこだわりがあるそうですね。

【宇野先生】ホスピタルアーティストの方の作品を待合室に飾っています。ホスピタルアートは、患者さんはもちろん、医療従事者の心を癒やすもので、欧米では20年以上前から実践されている取り組みです。当院では、臼井院長の発案で、春夏秋冬の季節に合わせた作品を展示してもらうことにしました。それぞれ作品の中にかわいらしい動物が隠れているので、待ち時間に見つけてみてください。また、片頭痛患者さんは強い光で頭痛を起こしてしまうことがあるので、調光機能で待合室の光をやわらかなものにしています。
診療における心がけを教えてください。
【臼井院長】日本で行われたラグビーの世界大会を見て、ノーサイドの精神をはじめとした紳士的な振る舞いに感銘を受け、「誠実に」「謙虚に」「常に冷静に」「互いを尊重し」「すべてに感謝して」の5つの言葉をクリニックの理念としました。医療従事者としてはもちろん、人間として大切にすべきこれらの言葉に忠実な医療の実践に努めています。また、宇野先生の片頭痛同様、私自身が喘息患者なので、咳や息切れのつらさは身にしみています。喘息患者さんが「咳や息切れを考えない毎日」を過ごせるよう、ともに歩んでいきたいです。
最後に、今後の展望をお聞きします。
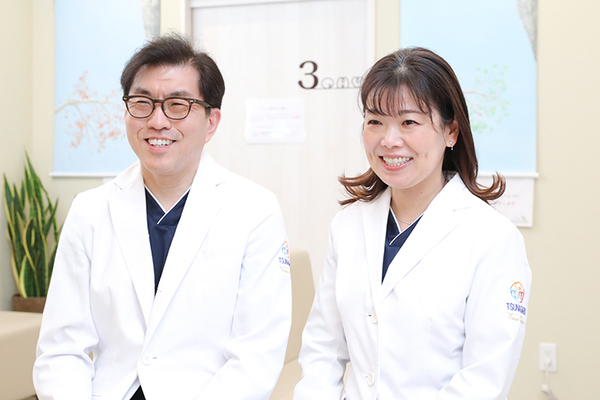
【宇野先生】当院で解決できない疾患のつながりは、他領域の先生のお力も積極的に借りて、患者さんの症状や心配事が改善する最善の道を考えています。お互いの顔が見え、信頼できる先生方と「つながりの輪」を広げていきたいですね。
【臼井院長】今、呼吸器疾患の治療では「Treatable Traits Approach:治療可能な臨床特性に対するアプローチ」が注目されています。これは呼吸器疾患だけでなく、関係する他の領域の疾患や環境も含めて包括的に治療することが、より良い結果につながるという考え方です。私はこの考え方を呼吸器疾患に限ったものではなく、すべての患者さんを丸く診る「つながりの医療」そのものと捉えています。私たち3人の専門性、スタッフのスキルを高めながら、他領域の先生方との連携を深め、つながりの医療を続けていく所存です。






