望月 直樹 院長の独自取材記事
かまた眼科クリニック
(大田区/蒲田駅)
最終更新日:2025/11/20

蒲田駅直結の商業施設で、週7日とも19時まで診療する「かまた眼科クリニック」は、誰もが通いやすい医院にしたいという望月直樹院長の思いから生まれた。「見えることの喜びに満ちた患者さんの姿を見たくて眼科を専門に選びました」と語る望月院長は、緑内障のように自覚症状がほとんどなく進む病気の早期発見・早期治療のほか、学校の健診では見つかりにくい小児の見えづらさにも積極的にアプローチする。「ここ数年で眼科で検診を受けていない方は、ぜひ受診してください」。優しい笑顔の望月院長に眼科検診の大切さ、新型コロナウイルス感染症の流行で在宅勤務などが増えて以降多くなった目の病気、治療法などを聞いた。
(取材日2024年8月20日/再取材日2025年9月12日)
気づきにくい子どもの「見えにくさ」。弱視の原因にも
週7日とも診療されていますが、そのほかのクリニックの特徴や診療方針について教えてください。

患者さんのご都合に合わせて受診していただけるよう、当院がある商業施設の休館日以外はすべて診療日とし、19時まで診療しています。開業にあたって蒲田駅に直結する商業施設のクリニックモールを選んだのも、どなたでも通いやすい場所で患者さんを診たかったからなんです。患者さんの年齢層は幅広く、平日の昼間は高齢の方が多く、17時を過ぎるとお勤め帰りの方が増え、土日は結膜炎やものもらいなどのお子さんをご家族が連れておみえになります。診療の際は、患者さんが自分の家族だったらどの治療を提案するだろうかと考え、ご本人とご家族の気持ちに寄り添うよう心がけています。実際に治療法を選ぶ時は患者さんと十分にお話しして、ご本人が納得される方法で進め、病気や治療法についてわからないこと、疑問に感じることなどがあれば、その場で丁寧にご説明しています。
最近、目の病気の訴えなどで気づかれたことはありますか?
在宅勤務などのせいか、軽度の視力低下や視野の中心が暗くなる中心性漿液性脈絡網膜症が目立ちました。自然治癒も多いのですが、長引くと治っても見えづらさが残ることもあるので、内服薬による早めに治療をお勧めします。また、お子さんの近視、特に仮性近視が増えている印象です。室内で近くばかりを見ていると近視傾向が強くなります。お子さんの場合、自分で遠視か乱視か気づくことはできませんが、その状態が続くと視力が未発達のまま成長して弱視が定着し、成長後の改善が望めないこともあります。絵本を読んでも集中力が続かない場合などは、目のピントが合わずうまく見えていないのかもしれませんから、一度検査をお勧めします。新たな検査機器により、2歳以下でも簡易的な視力検査が可能です。詳しい検査が必要ならば、連携先の大学病院もご紹介できます。また、最近では近視を抑制する点眼薬も登場しており、注目しているところです。
どのタイミングで受診すると良いのですか?
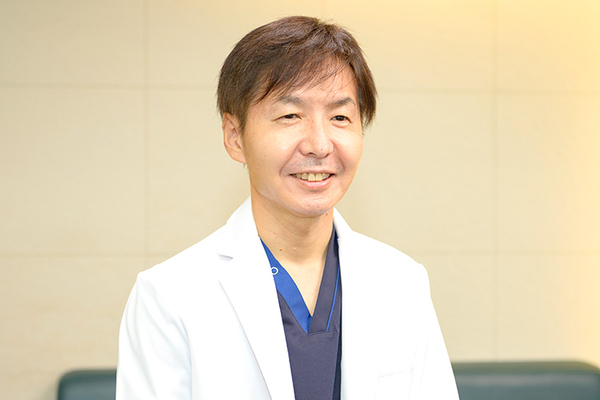
目の病気や障害の中には自分では気づきにくいものがあり、気づいても「しばらくすれば元に戻るだろう」と様子見をしている間に重症化することも起こり得ます。何か気になったりおかしいと感じたりしたら、お勤め帰りでも土日でも気軽に受診いただければと思いますね。当院は当日直接来ていただいても受診できますが、あまり待ちたくない方はインターネットで24時間予約も可能です。それに商業施設の中にあるので、受診の前後にはお買い物もしていただけますし、便利ですよ。
自覚症状に乏しい緑内障の早期発見と治療に努める
緑内障の検査や治療に力を入れているのはなぜでしょうか?

開業して感じたのは緑内障の患者さんが予想以上に多かったことです。緑内障は進行すると失明の可能性もある病気ながら、自覚症状がほとんどなく、見え方が変だと感じて受診された時には失明の一歩手前、ということもあります。以前は高齢の方の病気、眼圧が高い方の病気とされていましたが、実際には40代で発症する方も多く、20代、30代でもその予備軍が見つかり、眼圧が高くなくても発症することがあるとわかってきました。この病気は視神経が傷ついて視野の周辺部が欠け、それが視野全体に広がるのですが、片目の視野が一部欠けた程度だと気づきにくいのです。ただ、網膜の神経線維の厚みが変化するなどの特徴があり、OCTによる網膜断層解析をはじめ専門的な検査により早期発見もめざせます。当院ではOCTでの検査を含む定期検診を行っています。コンタクトレンズ用の視力検査などで緑内障が疑われた場合も、OCTによる検査をお勧めしています。
治療の際に心がけていることを教えてください。
早期なら目薬で進行の抑制を図りますが、病気の進行度やタイプによっては飲み薬、レーザー手術などの治療が必要な場合もあります。ただ、いずれの治療でも失った視野や視力は元に戻らないため、やはり早期発見が何よりです。当院で行う治療の大半は目薬によるもので、ずっと続けていただくには患者さんの協力が不可欠ですが、残念ながら治療を自己判断で中止され、何年か後に緑内障が悪化して再受診される方もいらっしゃいます。そこで緑内障とはどんな病気か、症状がなくても治療を続けるのはなぜかなどを映像やリーフレットも使って説明を徹底し、続ける大切さをご理解いただけるよう努めています。
そのほか多い病気や治療法などはありますか?
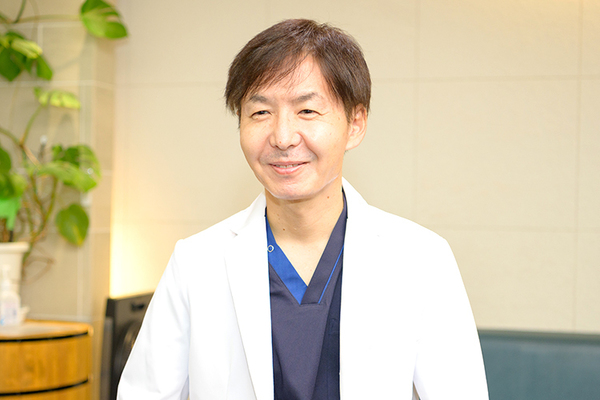
目が乾く、光がまぶしい、コンタクトレンズをつけると痛いなどの症状を伴うドライアイに対しては、目を温めたり運動したりといった血行の改善や栄養バランスのアドバイスも行います。治療としては、点眼薬で涙の状態を安定させることをめざす治療法や、保険適用の涙点プラグで涙を保持しやすくすることを図る治療法もご案内しています。また、目の中に炎症が起きるぶどう膜炎は、失明や視神経損傷による視力低下が起きる可能性もあるため検査・治療に力を入れています。症状はかすみ目、虫が飛んでいるように見える飛蚊症、目の痛みなどで、疲れや年齢のせいと諦めて受診が遅れる方も多いのです。治療は点眼が中心ですが、病気が進むと治療は長くかかるので、早めの受診が大切です。
ドライアイの悪化につながる生活の改善までアドバイス
先生がこちらで診療されるまでの経緯をお聞かせください。

私は子どもの頃から体調を崩すことが多く、同じ悩みを持つ人の気持ちに応えたくて医師をめざしました。その後、親しい先輩医師に誘われ、茅ヶ崎市の病院に移ってからは眼科を専門に診療してきました。診断から治療まで一通りできるようになった頃、自分で医院を持ちたいと考えるようになり、当院の開業に至ります。その先輩医師には蒲田駅近くの大学病院を連携先として紹介していただくなど、本当にお世話になりました。
眼科を受診する際のアドバイスをお願いします。
眼鏡やコンタクトレンズを作らなければ、眼科はあまり縁がないと思われるかもしれません。ただ、軽い遠視や乱視は無理をして見ているので眼精疲労を起こしやすく、緑内障のような病気も初期段階では気づけません。できれば30代になったら一度眼科で検査を受けていただければと思います。特に緑内障は早めに適切な治療を行えば失明のリスクは大幅に軽減することが見込めます。また、糖尿病の患者さんは網膜障害が起きやすいことはよく知られており、眼科の受診も一般的ですが、その一方で、全身性エリテマトーデスや関節リウマチなどの膠原病が、ぶどう膜炎のような目の病気のリスクが高いことはあまり知られていません。睡眠薬や抗不安薬は眼圧を高めて急性緑内障発作を起こす可能性もあるなど、他科の病気や治療が目のトラブルにつながるケースにも注意してください。
最後に、地域の方々にメッセージをお願いします。

眼科検診を受けずに何年も過ごされている方も多いのではないでしょうか。視力や見え方は年齢によって変化し、使っていた眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなることもしばしば。自覚しにくい病気の早期発見のためにも定期的な検査をお勧めします。また、遠視のお子さんは頑張って見ている間は2.0くらいの視力が出ることも多く、学校の視力検査では気づかれにくいのが難点です。しかし頑張りは長く続きません。普段は遠くも近くもピントがうまく合わず、黒板や教科書がよく見えなくて勉強嫌いになる子も。お子さんの視力も一度眼科で検査を受けていただければと思います。視力や見え方は生活にも大きく影響します。眼科の診療を通じて、自分らしい生活を長く続けていただくお手伝いをめざしていますので、どうぞ気軽にご相談ください。






