樺島 重憲 院長の独自取材記事
えがおの森こどもアレルギークリニック
(川崎市高津区/高津駅)
最終更新日:2025/06/13

子どもの病気や健康の問題を相談できる小児科医は、子育てにおける大切なパートナー。早めに信頼できるかかりつけ医を見つければ、育児の不安や悩みを分かち合い、安心して成長を見守ることができるだろう。東急田園都市線・高津駅からすぐの場所に位置する「えがおの森こどもアレルギークリニック」は、小児の一般診療や予防接種、乳幼児健診、さらには樺島重憲院長の専門であるアレルギーの診断・治療も受けることができる。優しく包み込むような温厚さの中にユーモアを秘めた樺島院長の人柄も相まって、セカンドオピニオンで受診する患者も多い。知りたいことを適切かつ丁寧に、理解しやすい言葉で話してくれる樺島院長に、アレルギー診療の前線や同院の診療方針などについて尋ねた。
(取材日2025年5月13日)
一般的な小児疾患に加え、アレルギー診療にも注力
一般診療に加えて、先生のご専門であるアレルギー診療も積極的に行っているそうですね。

はい。私はもともと人工衛星の開発をしていた会社員だったのですが、医師に転身してからはアレルギーの研究と診断・治療に取り組んできました。立川相互病院でアレルギー専門の外来の立ち上げを担ったほか、国内のアレルギー診療の拠点である国立成育医療研究センターで診療と研究、後進の育成に携わった後に当院を開業しています。アレルギー症状の寛解をめざし、生活の質を維持するためには、早期に適切な治療を開始する必要があります。場合によっては、発症の予防もめざせます。病院より気軽に相談できるクリニックの特性を生かして新しい知見に基づいた検査や治療を行い、一人でも多くの患者さんのつらさを軽減したいと思っています。
どのような主訴での受診が多いですか?
最も多いのは、咳・鼻水、発熱、腹痛といった日常的な症状を訴えるお子さんですね。こうした症状は、細菌感染、またはウイルス感染のいずれかが原因であることが多く、細菌感染であれば適切な服薬、ウイルス感染であれば対症療法で回復を待ちます。ただ、ウイルス感染では発熱などの症状が長引くことがあり、本人はもちろん看病する親御さんも「いつまで続くんだろう?」「このまま様子を見ていて良いの?」と不安に駆られることが少なくありません。そこで、15種類の病原体を15分ほどで特定できるPCR検査を導入しました。これまでは、熱が7日以上続いたら大きな病院をご紹介して専門的な検査をするのが一般的でしたが、院内で速やかに診断をつけられるようになり、親御さんともども安心してお子さんを見守ることができています。
アレルギーの患者さんは、どの年代の方が多いですか?また、どのようなきっかけで来院されるのでしょう?

アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、喘息などのアレルギー疾患をご相談いただくのは、小学生くらいまでの年齢のお子さんが中心です。専門的な検査や治療ができるクリニックを探して、少し遠くから来られる方も増えてきました。受診のきっかけは、アトピー性皮膚炎で通院しているけれどなかなか良くならない子、咳が長引くので親御さんがアレルギーを懸念して相談に来る子などさまざまです。長引く咳で受診してみたら喘息が疑われる、ということもあります。
治療法も進歩、アトピー性皮膚炎の寛解をめざす
アレルギーは、いつ、どんなタイミングで受診するのが望ましいですか?

当院では、乳幼児健診や予防接種の際、気がかりな症状が見られるお子さんには検査や治療をお勧めしています。というのも、近年、乳児期に湿疹のある子は食物アレルギーを発症する確率が高いことがわかってきたからです。以前は離乳食が進んでアレルギー症状が出てから専門の医療機関を受診するのが一般的でしたが、早期にリスクを把握できれば離乳食前に肌の症状を治療をし、その後のアレルギー発症を抑えるために予防的な対応をするということも可能です。大規模病院では難しい先回り治療が実践できるのは、成長著しく体の変化も大きい乳児期から子育てに伴走できるクリニックならではの強みだといえるでしょう。
アレルギーの検査や治療は、著しく進化していると聞きました。
おっしゃるとおりです。例えば「食物アレルギーは、原因となる食物を避けるべき」というのは既に過去の考え方なんですよ。今は、対象の食物、いわゆるアレルゲンを少しずつ口にして経過を観察する食物経口負荷試験で適切な量を見極め、症状が出ない量のアレルゲンを継続的に食べていく方針が主流です。当院では、モニターつきの個室を2室用意し、アレルギーに精通した専門の看護師のもとで、安心して食物経口負荷試験を受けていただくことができます。最近では卵黄を食べると嘔吐する消化管アレルギーが増えている印象ですが、これは血液検査ではわからず、症状で診断します。1~2年で自然に治ることが多いので、原因食品を除去して食べられるようになるのを待ちます。消化管アレルギーに一般的な食物アレルギーが合併している場合もあり、その場合は対応が変わってきますので、なるべく早めにご相談ください。
治療が難しいとされてきたアトピー性皮膚炎にも、さまざまな治療法が登場しているそうですね。
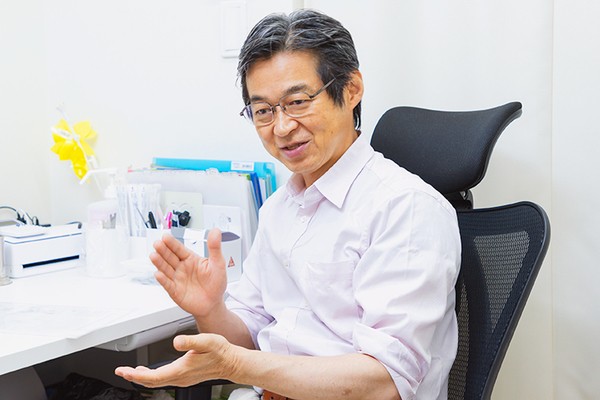
近年のアトピー性皮膚炎の治療は、速やかに炎症のない状態をつくるためステロイド外用薬などを用い、皮膚の状態を見ながら肌の保湿を強化し、継続的に湿疹がでにくい状態をめざしていくプロアクティブ療法が推奨されています。これに加えて、大きく3つの新しい治療法が登場しました。1つ目は、3種類の塗り薬。塗り続けていても副作用が出にくいのが特徴です。比較的アトピー性皮膚炎が軽度な方であれば、この塗り薬を用いるのが良いと思います。ただ費用が高めなので、体が小さい3歳くらいまでの方に多く使っています。2つ目はJAK阻害薬という飲み薬で、外用薬と併用して重度の方の治療にも用います。3つ目は注射で、これも重症の方にお勧めの治療法です。
子どもの成長を見守るサポーターとして、子育てに伴走
お子さんが通いやすいよう、工夫している点があれば教えてください。

院内でアニメーションを流したり、壁紙を部屋によって変えたりして、少しでも楽しい気持ちになってもらえるようにしています。注射を怖がる子には、痛みを軽減するため麻酔シールを貼ることも。また、アレルギー検査の際の採血は、指先から1、2滴の血液を採取することでアレルギー検査が行える機器を導入しました。検査結果の解釈は難度が高く専門的な知識が必要な機器なのですが、痛みの少ない上に最短30分で結果が出ますから、お子さんの負担を軽減するためにはやはり導入して良かったなと思っています。治療や検査を頑張った子に回してもらっているカプセルトイも人気ですよ。
院名のとおり、お子さんを笑顔にするアイデアがたくさん隠れているのですね。
困っている人、悩んでいる人に喜んでもらえる仕事がしたいと思って医師をめざし、研修医時代に唯一笑い声が日常的に聞こえてきた小児科の雰囲気に惹かれて小児科医の道に進みました。ですから、当院を受診したお子さんにも、お父さんとお母さんにも、最後は笑顔になって帰ってほしいと思っているんです。会社員時代に習得した、わかりにくい話をわかりやすく説明する力も活用しながら、「ここへ来て良かった」「助かった」と思ってもらえる場所にしていきたいと思っています。
ありがとうございました。最後に、今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

開業当初から、エビデンスのある新たな治療法やケアを提供すること、正確な情報を伝えることを心がけてきました。特にアレルギーの治療については、正しい治療を一定期間継続しなければなりません。ある程度の年齢のお子さんの場合、自主性、主体性はとても大事ですが、それだけではなかなか続きませんから、大人が治療の目的やゴールを理解し、「一緒に頑張ろう」「皆で治そう」という雰囲気を醸成することがとても大切です。今後も変わらぬスタンスで、ご家族とチームを組んで子どもたちの成長を見守っていきたいですね。






