森岡 新 院長の独自取材記事
森岡小児科医院
(大田区/雑色駅)
最終更新日:2025/11/12
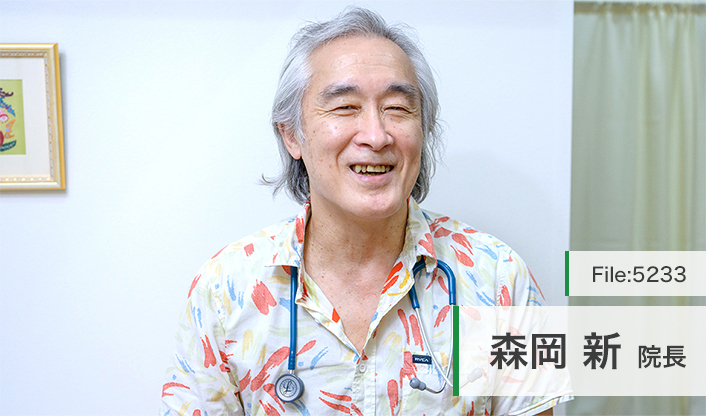
「子どもがにこにこ元気に育っているかどうかを見極めること。それが一番大切」。そう語る森岡新(あらた)先生は、50年以上にわたり地域に根づく「森岡小児科医院」の院長として、子ども一人ひとりと向き合い、また家族の話をじっくり聞くことで地域の健康を支えてきた。大学病院では二分脊椎症の外来を担当。下肢のまひや排泄障害を伴う重篤な疾患の診療に携わっていることから、子どもの成長や障害のある場合の生活ケアなどにも詳しい。子ども時代は町工場や多摩川の河川敷でわんぱくに遊んでいたという森岡院長。診察の際は白衣ではなくカジュアルなシャツスタイルで親しみやすく、下町育ちらしいテンポの良い本音トークも楽しい。患者家族に親しまれていることが納得できる、優しさと頼もしさを兼ね備えたドクターに迫っていく。
(取材日2025年8月26日)
子どもが元気に成長できることを第一に考える診療
初めに、先生の診療方針についてお聞かせください。

子どもにとって最良の治療や方向性を選ぶことを大切にしています。その際、ご家族の様子にも目を配り、家族中心の視点で診療するよう心がけています。親御さんと話すことで子どものことがよくわかるため、できるだけ時間を取り、疑問や相談に応じています。そして何より、子どもが元気ににこにこ育っているかを見極めることを重視しています。診察の最後には必ず「ほかに何かありませんか」とお尋ねするようにしています。言いづらいことを言葉にできずにいる方も少なくないからです。子どもも一人ひとりに個性があり、小さいうちはつらいのに我慢する子や大暴れする子もいますが、時間とともに少しずつ落ち着き、成長していくものです。後になって「よく泣いてたよね」と昔話をすると、照れくさそうにする姿がかわいらしいですね。
クリニックの特徴を教えてください。
当院の特徴は、小児外科を専門とする医師が小児科診療を行っている点です。現在も母校である順天堂大学医学部附属順天堂医院で、二分脊椎症が専門の外来を担当しています。二分脊椎症は下肢のまひや排泄障害を伴う先天的な病気で、脳神経外科、泌尿器科、整形外科、リハビリテーション科、時には眼科や皮膚科、内科まで含めた総合的なケアが必要になります。その全体を調整するのが小児外科の役割であり、ご家族のあらゆる相談に対応しています。体のこと以上に、生活面での悩みや相談が多いのも特徴です。普段の診療では外傷や消化器・泌尿器系の疾患などに、小児外科の経験が役立っています。小児外科を専門的に診る医師が少ない現状もあり、例えば保育園で遊んでいる時に頭を切ってしまった患者さんが、受け入れ先が見つからずに当院で手当てを行ったこともあります。
どのようなご相談が多いのでしょうか?
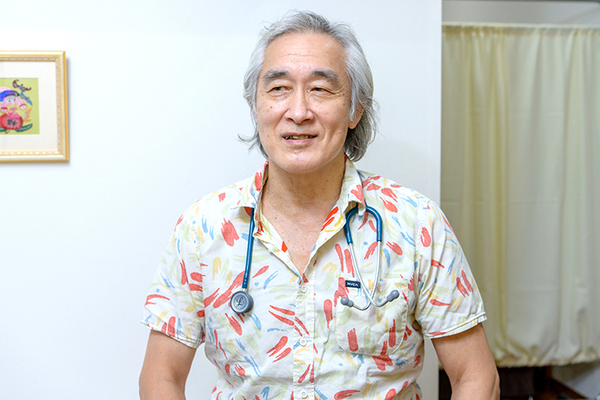
当院では一般的な小児科診療のほか、小児外科的な外傷や肘の脱臼などの外科的処置にも対応しています。手術は行っていませんが、簡単な処置であれば可能です。長年診療を続けているため、古くから通院されている子どもが成長して、親として自分の子どもを連れて来院されることもあります。また、患者さんのご家族など大人の診療にも、可能な範囲で対応しています。最近では、便秘で悩む子どもが増加しているんです。背景には、屋外で遊ぶ機会が減り、室内で過ごす時間が増えていることが挙げられます。便秘は食事、運動量、水分摂取量と密接に関係しており、特に運動不足は大きな要因です。子どもの腹痛や発熱、吐き気などに対応しますし、親御さんには、水分をこまめに、しっかり取るようアドバイスしています。
感染症拡大時に見えた、世代をつなぐための小児科診療
医師をめざしたきっかけや開業までの経緯を教えてください。

両親が医師で、私は4歳の頃、母が自身の実家・西六郷で開業した医院で育ちました。忙しい母の姿にふれるたび、少し寂しい気持ちを抱きながらも、次第に「面白そうだ」と感じるようになり、医師をめざすことにしたのです。医学部では勉強よりラグビーに夢中になり(笑)、小児科に入局して4年後、ラグビー部の監督が小児外科の教授に就任したことを機に、私も小児外科に進む決心をしました。大学病院や地方病院で研鑽を積む傍ら、母の診療も手伝い、1997年に当院を引き継ぎました。2018年には築50年の旧医院の向かいに新築移転。老朽化が進み、修繕では対応しきれないと判断したためです。診察台や待合室の椅子は以前のものをそのまま使用しています。
新型コロナウイルス感染症が流行していた頃はどのような状況だったのでしょうか?
ワクチン接種が始まった当初、近隣の先生方がなかなか対応できない状況もあり、当院では「できることはやろう」と思い、可能な限りお受けしました。そこから広がりが生まれ、ご縁のなかった地域の方々にも認知していただけるようになりました。健康や生活に関するちょっとしたご相談も増え、気軽に立ち寄っていただける雰囲気ができたように思います。
感染症の流行を経て、何か変化はありましたか?
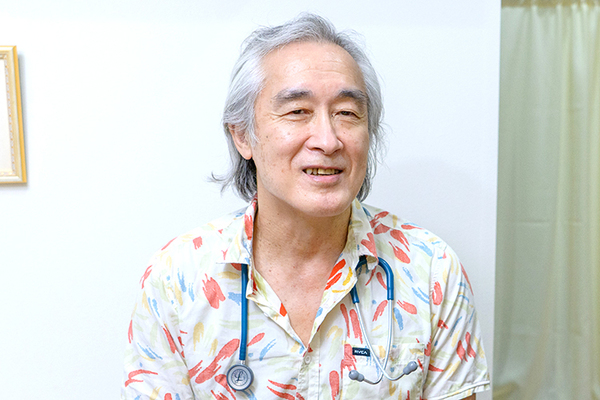
感染拡大をきっかけに、当院では症状や体質などに合わせて漢方を処方するケースが増えています。私自身が四十肩になった際、漢方に詳しい先生から教えていただき、それ以来、学びを深めてきました。現在では、子どもの過敏性腸症候群、食欲不振、夜泣き、お母さんの冷え性などに、個人差を踏まえながら積極的に取り入れています。子どもは成長に伴って体質も変化するため、その点に注意して処方しています。ワクチンに抵抗を感じる親御さんもいることから、希望される方が増え、私自身も勧めるようになりました。
親子の生活や思いを理解し、適切な診断と治療を
この地域の特徴を教えてください。

この辺りはもともと京浜工業地帯で、工場の煤煙や車の排気ガスの影響で喘息が多い地域でした。現在は環境も改善され、また古くからの住民に加え、新しいファミリー層やマンションも増え、活気ある街になっています。「医療の町」として院外処方など新しい取り組みも積極的に行われ、医療環境も充実しています。小児科では、医師会診療所で土曜夜・日曜の外来、平日夜は東邦大学医療センターで「大田区子ども平日夜間救急室」を開設しており、私たちも当番で診療に携わっています。蒲田だけでなく大森や田園調布からも患者さんが訪れ、地域ごとの流行や病気の状況を把握でき、とても勉強になります。
地域に対する想いをお聞かせください。
地域には子どもを診る医師が少ないという現状があります。声をかけていただければ、少しでもお役に立ちたいと思い、現在は10園ほどの園医を務めています。診療では子どもだけでなく、親御さんとの対話を特に大切にしています。電話では伝えにくいことも、写真を添えて相談していただくことで、不安を少しでも和らげられればと考えています。小児科は子どもの体を診るだけでなく、ご家庭の生活や親御さんの思いを理解することが欠かせません。そのため、子どもが嫌がらずに来院でき、親御さんも安心して相談できる場であることを心がけています。さらに数年前には乳幼児用の視力検査機器を導入し、弱視や斜視を早期に発見できるようにしました。地域の子どもたちが健やかに成長できるよう、これからもできる限り力を尽くしていきたいです。
最後に読者へのメッセージをお願いします。

子どもは一人ひとり違いますので、いろいろな人の話を聞くことが大切です。身近に気軽に相談できる大人がいなければ、遠慮せず小児科を利用してください。また、スマートフォンやテレビなどの強い視覚刺激は脳の発達に影響し、「キレやすい」「集中力がない」「無関心」などの問題につながることがあります。子どもがバランス良く脳を発達させられるよう、よく話しかけ、一緒に遊んであげてください。家族が心身ともに健康であれば、子どもも元気に育ちやすいです。仕事や家事で忙しく、子どもに向き合えないと感じることもあるでしょうが、親が一生懸命取り組む姿を子どもは見ています。お母さんお父さんも無理をせず、ご自身の健康に気をつけながら子育てしてくださいね。






