手や腕、肘の痛みやしびれの治療は
手の外科が専門の医師に相談を
芦花公園整形外科
(世田谷区/芦花公園駅)
最終更新日:2022/05/09


- 保険診療
整形外科の中でも、特に肘関節から指の先までを専門とする「手の外科」と呼ばれる分野があるのを知っているだろうか。そして、整形外科が専門の医師の中でも特に少ないとされる手の外科を専門とするのが、「芦花公園整形外科」の南野光彦院長だ。南野院長はこれまで大学病院で、体のほかの部位よりも機能的や美容的にも要求度が高く、繊細な治療を必要とする手の病気やけがに対し、手術を含めさまざまな治療を行ってきたという。そこで、手の外科のことや、手や腕、肘などの病気やけが、それらに対する治療などについて、南野院長に詳しく教えてもらった。
(取材日2022年4月12日)
目次
繊細な治療が必要となる手の病気やけがは、それらを専門とする医師を見つけることが適切な治療につながる鍵
- Q手や腕、肘の痛みやしびれは何科に相談すれば良いのでしょうか?
-
A

▲手の外科を専門とする医師である南野院長
手や腕、肘の痛みについては、基本的に整形外科への受診で間違いではありません。しかし、手の治療というのは機能的、美容的にも要求度が高く、診断も比較的難しく、繊細な治療を要するなど、非常に特別なセクションと言えます。整形外科の中には、特に肘関節から指先までを専門とする手の外科という分野がありますので、それを専門とする医師を探して受診するのがお勧めです。しかし、整形外科を専門とする医師の中でも、手の外科を専門とする医師は特に少ないのが現状です。私は、その手の外科を専門としていますので、手や肘の痛みやしびれの際には、ぜひ当院をご利用いただきたいと思います。
- Q手のしびれや痛み、つるなどの場合に考えられる疾患は?
-
A

▲手の痛みやしびれの原因はさまざま
手に多い具体的な症状としては、指や手首、腕の痛みやしびれ、動きが悪い、感覚が弱いなどがあります。痛みやしびれの場合に疾患で多いのは、指や手首の腱鞘炎、神経の圧迫から起こる手根管症候群、加齢の影響から起こるへバーデン結節、親指の付け根の関節が腫れる母指CM関節症などがあります。ほかに、骨折や切り傷、神経や血管、腱の切断などの外傷もあります。また、手の痛みやしびれなどの原因がその場所に限らず、少し離れた頸椎椎間板ヘルニアや頸椎症など首や、鎖骨の部分の神経の圧迫からくる胸郭出口症候群、さらには糖尿病が関係することもあります。そのため、手に加えて首や内科的なことまで診ることが大切になります。
- Q肘の内側や外側に痛みがあり、特に骨を押すと痛いという場合は?
-
A

▲理学療法士が常勤している同院
肘の内側や外側の痛みはいわゆるテニス肘やゴルフ肘が考えられます。正式な病名は、外側なら上腕骨外側上顆炎、内側なら上腕骨内側上顆炎。その名前のとおり上腕骨の外側、あるいは内側に炎症が生じている状態です。骨を押すと痛いのは、骨そのものの痛みというより、腱や筋肉が付着している肘の骨の部分の炎症による痛みのことがほとんどです。また、テニスやゴルフをしていなくても、パソコン操作や日常生活動作が原因となることも。治療は、手術が必要になることはまれで、原因となる日常生活動作を制限し、スポーツをペースダウンし、痛み止めの内服薬や湿布薬、注射薬などに加え、ストレッチなどの理学療法で痛みの軽減を図るのが基本です。
- Q手や肘のけがや病気を放置することのリスクを教えてください。
-
A

▲対応が遅れると手術が必要になる可能性も
治療は早いほうが選択肢は多く、一方症状が進んでしまうと選択肢が限られる可能性があります。例えば、骨折なら骨のずれがなければギブスで固定するだけで済みますが、対応が遅れると手術が必要になることもあります。また、手の病気は痛みをとることや骨をつけることだけでなく、機能の回復も求められます。治療が遅れると指や手首が硬くなり、機能回復のためのリハビリテーションにも時間がかかります。傷が残りにくいようにするためにも対処は早いほうが良いと言えます。遅れたからといって治療ができなくなるわけではありませんが、早いほうがメリットが多いので、症状がある場合は早めの受診をお勧めします。
- Q治療後に気をつけたほうが良いことはありますか?
-
A
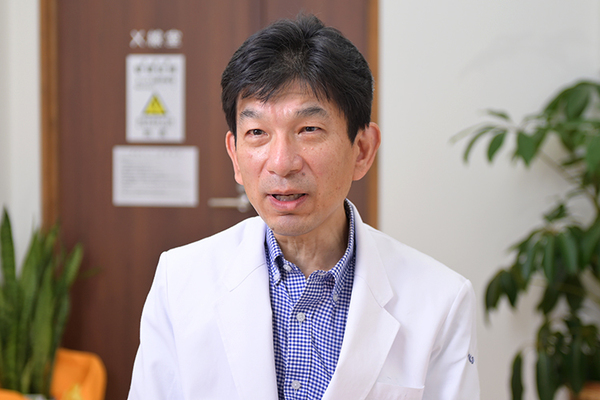
▲患者に合わせたアドバイスやストレッチなどを行っている
治療をしても、スポーツなどを再開するとまた痛くなってしまうことも少なくありません。そのようなことがないように、リハビリテーションをしっかり行うことが大切です。当院では、患者さんとよく話し合い、スポーツ復帰や社会復帰に向けてできる限りストレスの少ない治療のプログラムづくりを心がけています。特に、リハビリテーションについては、理学療法士とともに、患者さん一人ひとりに合わせ、これ以上けがをしないための予防として、日常生活動作での注意点や自宅で行えるストレッチなどの指導も行っています。そして、皆さんには、それぞれの生活の中で工夫をしながら再発や予防に努めていただきたいと思います。






