岡田 和子 院長の独自取材記事
岡田小児科クリニック
(新宿区/東新宿駅)
最終更新日:2025/08/26

東新宿駅から徒歩5分。静かな住宅街にある「岡田小児科クリニック」は、1999年の開院以来、地域に住む新生児からティーンエイジャーの子どもたちのかかりつけ医として健康を守っている。院長の岡田和子先生は、容態の急変の兆しを見逃さないよう、悪化の恐れのある子どもには夜間でも両親へ電話をかけて確認するというくらい熱い想いを持つ小児科専門の医師だ。専門分野は消化器。特に子どもの便秘に関しては診療ガイドラインの作成にも携わり、遠方からの受診者も少なくない。「慢性便秘では、親御さんにお子さんのつらい症状をしっかりと知っていただくために、病状をよく説明し、最後に不安に思っていらっしゃることを伺うようにしています」と語る岡田院長に、さらに詳しい話を聞いた。
(取材日2022年11月10日/情報更新日2024年12月19日)
親子関係や事情を熟慮した診療を心がける
ここ大久保で開業されたのはなぜですか?

実はこの地には、戦前から岡田家がありまして、戦争で焼け野原になった地域だそうです。私は9歳から暮らしているんです。かつては木造の一戸建てでしたが、40年ほど前に現在のビルに建て直しました。最初に木造の時に開業したのは、産婦人科の医師だった母です。その後少しブランクがありましたが、継承するようなかたちで、1999年に小児科を開業しました。それまでは卒業した東京女子医科大学第二病院小児科で、19年間勤務医としてさまざまな経験を積ませていただきましたね。開業当時、大久保地域で小児科が専門のクリニックは他に見当たりませんでしたが、ここ2年で2軒ほど増えたんです。前より忙しくなくなりましたが、逆にゆとりをもって丁寧な診療ができることはいいことだと思っていますね。
どんな患者さんがいらっしゃいますか?
近所に住んでいる新生児からティーンエージャーのお子さんが中心です。最近は外国のお子さんの来院も増えましたね。予防接種や健診は午前午後ともに予約時間で行います。発熱の患者さんは、予約枠も設定していますが突然いらしたりします。午前中早い時間や夕方の保育園帰りが多いです。2020年新型コロナウイルス感染症の出現で小児科も診療の仕方が大きく変わり、発熱患者診察用ブースを屋外に設けて診察していましたが、2023年5月からは、発熱者はクリニック内で隔離して診察しています。
クリニックの診療方針を教えてください。

親御さんとのコミュニケーションをしっかり取る、ということです。特に親御さんは、お子さんにとっては最も身近な存在ですからね。診察の前に、親御さんにお子さんの症状をしっかり伝えていただけると、診察時に診断の助けとなります。そして診察後は病状の説明をしてから、親御さんが不安に思っていることについてきちんと伺うようにしています。そして治療について説明する際は、親子関係や親御さんの性格など、それぞれに抱える事情を考慮してお話しします。例えば、心配性の親御さんには病気についてわかりやすく話して「何かあった時はすぐ連絡してください」とお伝えしますし、逆におおらかな方に対しては、時に厳しく言うこともありますね。また場所柄、外国の方も多いので、その場合はわかりやすい言葉で簡潔に説明しています。
容態急変の兆しを見逃さない真摯な診察を重要視
治療の際に心がけているのはどんなことですか?

お子さんの場合は特に、診断や薬の処方について多くの注意を払わなければなりません。診察時にはまず顔色や活気を確認しますね。容態急変の兆しを決して見逃さないように、悪化の恐れがあるお子さんには、救急科の外来にかかれるように診療情報提供書を渡しておくか、私から夜間に親御さんに電話をかけて確認をとることもあります。また人見知りの時期の1~2歳のお子さんは診察時に泣くので、重要な点はしっかり診ながらもなるべく短時間で診察を済ませるように心がけています。7~8歳になるとコミュニケーションも取りやすくなりますから、雑談をしながら診察することもありますね。親御さんの中には看護師や受付スタッフに相談される方もいらっしゃり、そうした場合は私にその内容を伝えてもらい、診察に反映しなければなりません。ですからスタッフとのコミュニケーションも重視していますね。
先生は子どもの便秘治療が得意と伺いました。
私は小児消化器が専門で、約2年間アメリカで当時、先進の研究にも携わってきました。母校の東京女子医科大学では、非常勤講師として子どもの嘔吐や下痢・便秘などの消化器病をテーマに研究もしていたんです。2023年まで乳糖不耐症の治療について若い医師らの指導をしていました。小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインの作成にも携わっていて、再びその改定作業を行っています。乳児期の便秘には先天性の病気が絡んでいる場合もありますが、3歳前後から始めるトイレットトレーニング時期に起こる例が多いですね。親御さんがトレーニングを厳しくしすぎてストレスで便秘になるお子さんもいます。便秘になる誘因やうんちがおなかの中でどのようにできるかのお話などもきちんとさせていただいています。治療は便秘になってからの期間にもよりますが、少なくとも半年はかかります。治療中は心配なことがあればいつでも電話で相談を受けるようにしています。
小児医療の観点から感染症についてどう見られていますか?

新型コロナウイルス感染症はインフルエンザ並みの感染症分類になりましたが、インフルエンザと同じように、人によっては脳症や肺炎など重症化することのある感染症です。また、子どもは発熱を伴う感染症がほかにもたくさんあります。消毒やマスク着用など生活様式の変化の影響も考えられますが、しばらく出ていなかった、手足口病やヘルパンギーナも流行したり、今後、未知の新しい感染症が出現する可能性もあります。当院では安心して来院してもらえるよう、引き続き感染防止対策を行い、発熱児は隔離して診療を行っていきます。また、発熱がない場合でも、咳、鼻汁、下痢、嘔吐などの症状の多くはウイルス性感染症であり、お互いに別の感染症をうつしあう可能性があるため、受診マナーとして、待合室では騒がず静かにお待ちいただきたいと思います。スタッフは常時マスクを着用しておりますが、患者さんもご心配ならマスク着用をお勧めします。
医療も子育ても子どもの個性に合わせて考える
先生はなぜ医師をめざされたのですか?

実はグラフィックデザイナーになりたくて、最初は武蔵野美術大学に通っていたんです。しかし就職活動をするうちに企業で働くのは自分には向かないように感じました。一方で、当時医学部に通っていた姉から、「人間の体」の仕組みについて聞くことがあり、そこに芸術性を感じて興味を持つようになっていました。そこで武蔵野美術大学を卒業後に1年間受験勉強し、東京女子医科大学に入り直したんです。遠回りしましたが、美大に通ったことは無駄ではなかったと思います。実は院内のレイアウトは学んだ知識を生かし、使いやすいように私がデザインしました。それが楽しくて仕方なかったのを今でもよく覚えています。
近年の子育てについて感じられていることはありますか?
今はインターネットやスマホにあらゆる情報があふれている時代ですが、その中で自分にとって都合の良い情報だけを取り入れようとする親御さんが目立つように感じています。その情報が正確かどうか情報源がどこなのかをよく調べずに心配になるようで、誤った知識で質問されても、医師としての意見はお伝えするようにしていますが、コミュニケーションの取り方が昔とはかなり異なってきたので難しい面もありますね。一つ言えるのは、お子さんは一人ひとり異なる体質や個性を持っているということです。ですから、インターネットに書いてあった情報があてはまるとは限りません。そうした意味も含めて、診察では親御さんが安心するような説明を心がけています。ご自身の五感を駆使してお子さんの成長を感じとっていただけたらなと切に願っています。
最後にメッセージをお願いします。
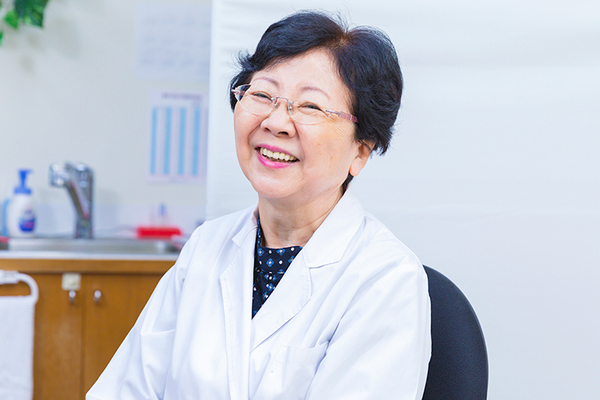
今は2歳児でもスマホやタブレットを操作し、親御さんもお子さんを見ずにスマホを見ているという光景をよく目にします。しかしそれでは子どもがなぜ泣いているのか、どんな時に具合が悪くなるのかといったことを見抜く目が鈍ってしまうと思うのです。こうした現象は問題視されていて、言葉の発達やコミュニケーション能力の発達への影響が危惧されています。ですから、親子間では、もっと「目と目を合わせるコミュニケーション」を大事にしていただきたいと思っています。






