宮尾 益道 院長の独自取材記事
宮尾耳鼻咽喉科クリニック
(新潟市中央区/新潟駅)
最終更新日:2025/10/29

新潟バイパス女池ICから車で約5分、住宅街の一角に立つ「宮尾耳鼻咽喉科クリニック」。モノトーンのスタイリッシュな外観が印象的なクリニックだ。2016年の開院以来、幅広い世代の患者に寄り添う診療を続けてきた。院長の宮尾益道(みやお・ますみち)先生は、東京医科大学を卒業後、アメリカでの研究留学や大学病院での臨床・研究経験を重ねてきた耳鼻咽喉科のエキスパート。日本専門医機構耳鼻咽喉科専門医として、耳・鼻・喉・頸部などの一般的な疾患に加え、めまい、いびき、顔面神経麻痺といった症状にも対応している。「どなたでも気持ち良く利用でき、明るい気持ちになれるクリニックをめざしています」と語る宮尾先生に、診療への思いや今後の展望について聞いた。
(取材日2025年9月24日)
気持ち良く、明るい気分になれるクリニックをめざして
医師を志されたきっかけや、これまでのご経歴を教えてください。

父が医師だったこともあり、幼い頃から医療が身近な存在でした。その影響もあって自然とこの道を志すようになり、大学は地元・新潟を離れて東京へ。卒業後は再び新潟に戻り、大学病院やその関連施設で研鑽を積んできました。大学医局在籍中は研究にも取り組み、さらには海外留学を通して、学術的な知識や国際的な視野も得ることができました。こうした経験は、現在の診療にも大いに生かされています。開業地である女池上山エリアは、いろいろな候補地がある中で地域の発展性にも惹かれました。地域に根差した医療を実現する場として理想的だと感じ、この地で開業してから10年がたちます。頼りにして来てくださる方も少しずつ増えてきました。これからも学びを重ね、より良い医療を提供し続けていきたいと考えています。
内装や設備のこだわりについてお聞かせください。
患者さんが気持ち良く利用できることを第一に、外観や内装を設計しました。医療機関にありがちな無機質さを避け、明るく清潔感のある空間をめざして温かみのある色調を採用しています。靴のまま入れる設計にしたことで、スリッパへの履き替えが難しいご高齢の方や小さなお子さん連れの保護者の方にも負担をかけません。キッズスペースを設けており、お子さんが遊びながら待てるようにしています。また、私自身の子育て経験をもとに、子育て世代の視点にも立った設備づくりを意識しています。例えば、おむつ交換台は女性用だけでなく男性用トイレにも設置しており、育児中のお父さま・お母さまのどちらにとっても使いやすい環境を整えました。来院されるすべての方にとって、居心地の良い場所となるよう心がけています。
患者さんの通いやすさを追求されているのですね。
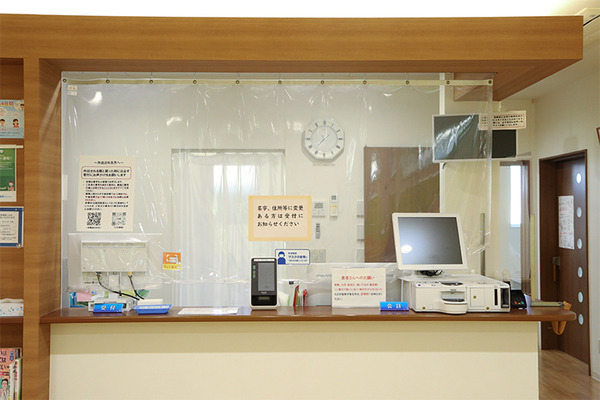
病院って、進んで行きたい場所じゃないですよね。だからこそ、患者さんが少しでもリラックスできるよう、院内の環境に配慮し、居心地の良い空間を提供することを大切にしました。インテリアや動線、清潔感など、細部まで気を配っています。患者さんにとっての通いやすさとは、ハード面の整備だけでなく、対応や説明の仕方、コミュニケーションといったソフト面も重要です。だからこそ、より良い医療を実現するために、ソフト面・ハード面ともに丁寧に整えることを意識しています。来た時よりも明るい気持ちで帰っていただけるとうれしいです。
「見てわかる」診療で、納得できる医療の提供を
患者さんの層や、主訴について教えてください。

当院には、0歳の赤ちゃんから100歳を超えるご高齢の方まで、実に幅広い年齢層の方が来院されています。小さなお子さんには風邪や中耳炎、思春期から若い世代にかけてはアレルギー性鼻炎や花粉症などの相談が目立ちます。一方で、働き盛りの世代から中高年層になると、めまい、耳鳴り、難聴といった症状が増えてくる傾向にあります。最近では、ストレスや生活習慣の影響で若年層のめまいも珍しくなくなってきました。受診される方の多くは近隣の方ですが、大学病院時代に担当していた患者さんが遠方からわざわざ足を運んでくださることもあります。長年にわたり頼っていただけるのは、医師としてありがたく、大きな励みにもなっています。
こちらではどのような診療を受けられるのでしょうか。
耳・鼻・喉を中心に、脳と目以外の「首から上」の領域全般を幅広く診ています。風邪や花粉症、めまい、耳の違和感、喉の痛みといった身近な不調により踏み込んでアプローチできるのが強みです。例えば耳に痛みがある場合、耳鏡や内視鏡などの専門機器を用いて耳の奥まで直接観察し、炎症の有無や鼓膜の状態を詳細に確認できます。また鼻や喉の奥など、自分では見えない部分の状態を、画像やモニターを使って患者さん自身にも「見える化」して説明できるのも特徴です。目に見えることで、漠然とした不安が安心に変わったり、治療に前向きになれたりする方も多いと考えています。専門的な診療と視覚的な説明を組み合わせることで、患者さんの納得や安心につなげられる診療をめざしています。
地域における役割について、どのようにお考えですか?

私たちは、地域における一次医療の窓口、いわゆる「ゲートキーパー」としての役割を大切にしています。どのような症状でも、まずは気軽に相談していただき、初期対応を行った上で、必要に応じて専門的な医療機関へつなげることを重視しています。特殊な機器を備えているわけではありませんが、地域のクリニックとして求められる基本的な検査には対応可能です。その上で「このまま当院で診ていけるか」「さらに詳しい検査が必要か」を適切に判断し、最適な医療の流れを築くことをめざすのが私たちの重要な役割だと考えています。どんな小さなことでも構いませんので、気になることがあれば、遠慮なくご相談ください。
これからも地域の健康を支えていきたい
患者さんと接する際に大切にしていることは何ですか?

患者さんに納得していただくことを何より大切にしています。限られた時間の中でも、患者さんが「来て良かった」と思えるように、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。例えば、めまいのように原因が多岐にわたる症状では、必ずしも明確な診断がつかないこともありますが、しっかりと検査を行った上で症状と向き合い、現状や今後の見通しをできるだけ言語化してお伝えすることが、安心感につながると考えています。また、必要以上にお待たせしないことも重要なポイントです。一人ひとりとしっかり向き合いたいという思いと、できる限りスムーズな診療を両立させるために、スタッフとの連携や動線の工夫に取り組みながら、診療体制のバランスを整えています。
スタッフとの連携について教えてください。
スタッフにはとても恵まれていると感じています。長年一緒に働いているメンバーも多く、接遇や業務の分担についても、言葉にしなくても自然と動ける関係性ができていることは、大きな強みだと思います。診療後の補足説明などはスタッフがスムーズに引き継いでくれる場面が多く、その分、私は診療に集中できる体制が整っています。おかげさまで開業当初は4人ほどだったスタッフも、今では倍以上の人数となり、より多くの患者さんに対応できるようになりました。それに伴い、スタッフ間の連携や情報共有の重要性もさらに高まり、チームとしての一体感がより求められるようになっています。これからもそれぞれの強みを生かし、連携を取りながら、患者さんが受診しやすい環境づくりに努めたいと考えています。
最後に、今後の展望や地域医療への思いをお聞かせください。

これまで多くの患者さんと関わる中で、一人ひとりと丁寧に向き合いたいという思いが年々強くなっています。日々の診療はどうしても慌ただしくなりがちですが、患者さんの表情の変化や声のトーンに気づけるような診療を意識し、少しずつでも理想に近づけるよう努めています。耳鼻咽喉科は「耳・鼻・喉」という、日常生活の質に大きく関わる部位を専門としており、自分では見えない箇所の状態を画像で確認しながら説明できる点が大きな特徴です。こうした耳鼻咽喉科ならではの強みを生かし、他の診療科ではカバーしにくい領域を支えることで、地域医療に専門的な立場から貢献していきたいと考えています。地域の皆さんに気軽に足を運んでいただけるような、身近で安心できるクリニックをめざしたいですね。






