岡本 日出数 院長の独自取材記事
益子腎臓内科透析クリニック
(川口市/川口駅)
最終更新日:2025/08/04

JR京浜東北線・川口駅から徒歩8分の場所にある「益子腎臓内科透析クリニック」は、診察室の他に、2フロア各30床という大規模な透析室を設置している。院長を務める岡本日出数先生は、東京慈恵会医科大学で講師を務め、日本腎臓学会腎臓専門医や日本内科学会総合内科専門医として豊富な経験を積んだ腎臓内科のスペシャリスト。岡本院長はまた、腎臓病を早期発見・治療するための啓発活動にも積極的に携わり、地域医療への貢献をめざしている。そんな岡本院長にクリニックの特徴や強み、診療におけるモットーなどをじっくりと聞いた。
(取材日2025年6月4日)
腎臓病をトータルで診療していくという強い使命
岡本先生のこれまでのご経歴についてお伺いします。

大学卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院の第二内科に入局し、医局が臓器別に再編されたことに伴い、腎臓・高血圧内科に所属しました。その後、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院(現・康心会汐見台病院)に2年半勤務し、2001年からは医療法人健仁会の益子病院に派遣され、川口市で初めて腹膜透析を導入しました。その後、大学での診療に携わった後、神奈川リハビリテーション病院で内科副部長を務め、再び益子病院に戻りました。2013年からは益子腎臓内科透析クリニックの院長を務めています。
長年にわたり腎臓の診療に携わってきて、特に注力されていることはどんなことでしょうか?
腎臓内科医には、2つの重要な役割があると考えています。一つは、腎臓病を早期に発見し、適切な治療を進めることで、透析導入を防ぐことです。実際に、かなり進行してからご紹介を受け、「もっと早く診て差し上げられていれば……」と悔しい思いをしたことも少なくありません。もう一つは、透析が必要になった患者さんに対し、できる限り元気に、健やかな日常を長く送っていただけるよう、最善の治療を提供することです。以前、ある透析患者さんから「先生、私、頑張るからね」と声をかけていただいたとき、その言葉に私自身も大きく励まされました。そうした患者さんの思いに応えられるよう、日々、最善の透析医療を届けることを心がけています。
新たな国民病といわれる慢性腎臓病(CKD)とはどのような疾患なのでしょうか?

現在、成人の5人に1人が慢性腎臓病(CKD)といわれています。一般には、CKDはやがて透析が必要になる病気というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。心疾患や脳卒中などの重大な病気を引き起こすリスクが高いことも、CKDの大きな特徴です。腎臓は血管の固まりのような臓器で、「腎臓が悪くなる=全身の血管も悪くなる」と考えていただくとわかりやすいと思います。ある大学の腎臓内科の先生は「尿タンパクは腎臓が流している涙」と表現されていました。尿タンパクが出ているというのは、それだけ腎臓が傷つき、つらい状態にあるということです。腎臓を守ることは、心臓や脳血管を守ることにもつながります。健康診断を欠かさず受け、血液検査や尿検査で腎機能異常や尿異常が指摘された場合には、ぜひ速やかに腎臓内科を受診してください。
腎臓内科だからこそできるきめ細かいフォロー
具体的には、どのタイミングで腎臓内科を受診すれば良いのでしょうか?

尿検査で尿タンパクが(+)や(±)と出た場合は、「様子を見る」のではなく、必ず腎臓内科を受診してください。血清クレアチニン値が高い場合や、推算糸球体ろ過量(eGFR)が60mL/min/1.73m2未満の時も、放置せず早めに受診することが大切です。「eGFRって何?」と思われるかもしれませんが、eGFRの単位をパーセンテージに置き換えて考えると、腎臓の働きがイメージしやすくなります。例えばeGFRが50mL/min/1.73m2なら、腎機能が50%程度という感覚です。腎臓病はかなり進むまで症状が出にくく、eGFRが30mL/min/1.73m2を下回る頃に貧血や高カリウム血症などが現れますが、その時点では病態が進行しています。だからこそ健康診断などで早期に異常を見つけ、対応することが重要です。最近はSGLT2阻害薬といった新しい治療薬も登場し、早期からの治療が期待されています。
貴院の強みはどんなところにあるとお考えですか?
当院では受診時に必ず尿検査を実施し、「一日尿タンパク量」や「推定一日食塩摂取量」を提示して、腎機能への影響を丁寧にご説明しています。川口市立医療センター、埼玉県済生会川口総合病院などの地域の基幹病院や、慈恵医大などの大学病院と密に連携しており、腎生検など入院が必要な検査にも迅速に対応できます。また、超音波検査に習熟した臨床検査技師が常駐しており、腹部臓器や心疾患の評価も即日対応が可能です。透析患者さんでは、腎細胞がんや虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈、心不全などの心疾患を合併しやすいため、超音波検査を中心とした画像検査で異常の早期発見に努め、所見があった場合には速やかに専門医療機関へ紹介し、適切な治療へと確実につなげられる体制を整えています。
慢性腎臓病の治療では食事制限が厳しいイメージがあります。

確かに慢性腎臓病の治療では、塩分・タンパク質・カリウムなどの摂取制限が必要になります。当院では管理栄養士が、「塩分は1日6g未満に」「タンパク質は40g未満を目安に」といった数値を示しつつ、日常の食生活に即した指導を行っています。無理なく続けるには、気負いすぎずに、できる範囲で取り組むことが大切です。時々、制限を厳密に守ろうとするあまり、かえって身動きがとれなくなる方もいらっしゃいます。「何も食べられない」と感じてしまっては本末転倒です。ときには自分へのご褒美で好きなものを楽しんだり、薬剤で数値の調整を図ったり、「うまくいかないのですが……」と医師や栄養士に相談することも、食事療法を続ける上で大切です。
長い治療期間を乗り越えるために大切な信頼関係の構築
患者さんとのコミュニケーション面で心がけていることは、どんなことでしょうか?

患者さんやご家族にご説明する際には、できるだけ専門用語を使わないよう心がけています。専門用語に頼った説明では、患者さんが「わかったつもり」になってしまうことがあり、実際には正確に理解されていないケースもあります。そのため、言葉をできるだけかみ砕いてお伝えし、「今お話しした内容はご理解いただけましたか?」と確認を重ねながら、相互理解を深めるよう努めています。また、食事管理に関するアドバイスでは、「塩分が梅干し1個分ほど多かったですね」など、イメージしやすく前向きに取り組んでいただけるような言葉がけを意識しています。治療を長く続けていく上で、医師と患者さんとの信頼関係を築くことは、たいへん重要だと考えます。
岡本先生の診療におけるモットーを教えてください。
「医学はサイエンスに支えられたアートである」という言葉は、ウィリアム・オスラー先生の名言ですが、私もこの教えを大切にしています。患者さんの症状に対して、その原因や病態を追求して診断する「サイエンス」とともに、患者さんと深くコミュニケーションをとり、最善の治療を行う「アート」が重要だと考えています。また、より良い治療を提供するためには、常に新しい知識やエビデンスを学び続けることが欠かせません。医師が「もうこれでいいかな」と諦めてしまうと、患者さんの生きる希望が失われてしまいます。わずかでも良くなる可能性があれば、その可能性を追求して最善を尽くすことが大切だと思っています。透析を避けるために最善を尽くすのはもちろん、透析が必要になった場合でも、元気に過ごせるよう最良と思われる透析医療を提供し、腎移植を選ばれた際には全力でサポートします。
読者へのメッセージをお願いします。
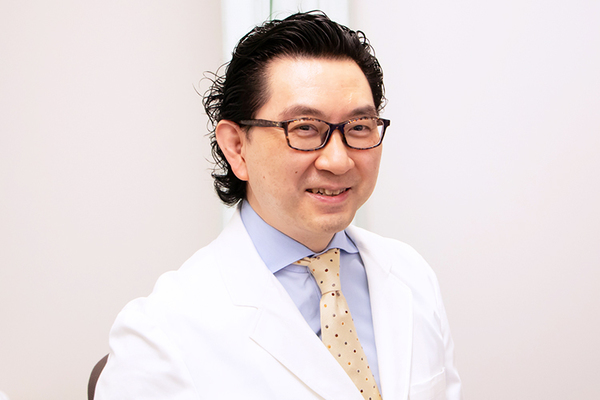
腎臓内科は受診のハードルが高く感じられるかもしれませんが、当院ではそのようなハードルを感じることなく、気になることがあれば、「ちょっと立ち寄ってみようかな」と気軽に立ち寄れるクリニックをめざしています。また、大規模病院で治療を受け、症状が落ち着いた患者さんが、引き続き安心して当院で治療を受けられる環境づくりにも力を入れています。透析が必要になった場合でも、「やっと通院に慣れたのに転院しなければ……」といった思いをせずに済むのも、透析施設を完備している当院ならではのメリットです。腎臓を守ることは全身を守ることにつながりますので、まずは健康診断を受けていただき、腎機能や尿に異常が見つかった場合にはお気軽にご相談ください。






