川上 猛敬 院長の独自取材記事
まちだ耳鼻咽喉科
(町田市/古淵駅)
最終更新日:2025/09/05
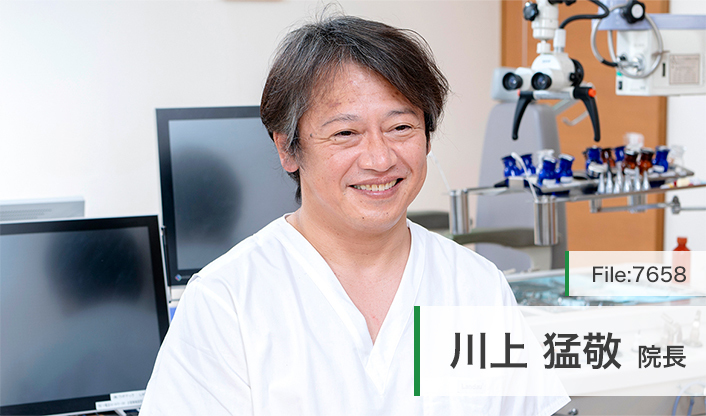
里山の風景が残るのどかなエリアにたたずむ医療モールに「まちだ耳鼻咽喉科」はある。町田駅から車で約15分、駐車場完備なので車での通院も便利だ。院長の川上猛敬(たけのり)先生は社会人入学で医学の道に進んだ異色の経歴の持ち主。もともとの専門である工学で培った論理的思考力をベースに、すべての疾患に対して根本原因に迫る。中耳炎や副鼻腔炎などのよくある耳鼻咽喉科疾患は自然と治ることも多い。しかし、だからこそ万が一の重症化を見逃さないよう、細部まで目を光らせる。患者の言葉にやわらかな姿勢で耳を傾け、何げない一言にも心からの笑顔を見せてくれる川上院長。「この先生になら何でも話せそう」と慕う患者も多いだろう。広々としたスペースに診察デスクを配置したユニークな空間で、詳しく話を聞いた。
(取材日2025年7月19日)
中耳炎から風邪症状までしっかりと診るかかりつけ医
今年で開業10周年ですが、これまでを振り返っていかがでしょうか?

足を運んでくれた患者さんをしっかりと治療し、気持ち良く帰っていただけるよう、開業当初からスタッフ一同力を合わせできる限りのことをしてきました。スタッフは当時より倍の人数になりましたが、今でもそれは変わりませんね。また、10年たって幼稚園生だった患者さんが高校生になって来院し「ずいぶん大きくなったね」といった会話が増えているのはうれしいですね。他にも来院するたびに俳句を添えた絵画作品を持ってきてくださった患者さんがいらっしゃったのですが、今でも季節ごとに作品を取り替えて飾っているんですよ。そして、耳鼻咽喉科というのは季節ごとに多くなる訴えがだいたい決まっているという特色があります。春先のめまいと花粉症、夏の風邪と感染症、秋の体調不良、冬の風邪と感染症、と繰り返しつつ、患者さんとともに過ごしたあっという間の10年でしたね。
風邪症状も耳鼻咽喉科に相談できるのですね。
風邪はもちろん、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の検査と治療なども行っています。咳、鼻水、喉の痛みなどのつらい症状を高い専門性でより早く快方に導くことをめざすのも耳鼻咽喉科が重視しているところです。また、鼻水、喉の痛みは放置していると扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎などの疾患を発症してしまうリスクもあります。風邪と思っていたらアレルギーだったというケースもあるので、自己判断せず早めに受診するようにしてください。当院では小児の風邪にも力を入れていて、まだうまく鼻をかめないお子さんへの鼻水の吸引の他、喉の局所処置、ネブライザー療法などもできるようにしています。風邪から中耳炎を起こしているときにも、すぐに治療を開始できるのも耳鼻咽喉科だからこそのメリットといえるでしょう。
子どもの中耳炎を放置するリスクを教えてください。
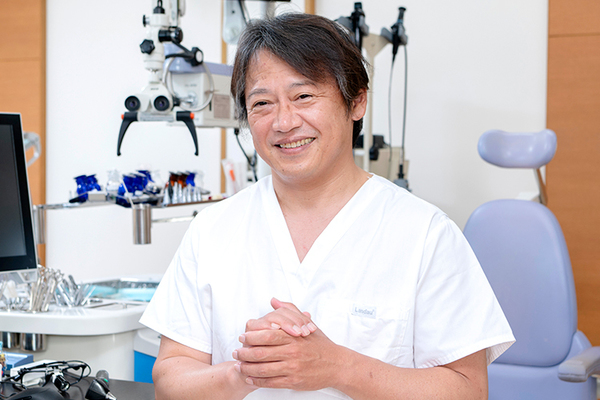
お子さんに多い滲出性中耳炎は自然に治ることも多い病気です。しかし、何度も繰り返しているうちに真珠腫性中耳炎になり難聴になる可能性もゼロではありません。もし小学生の頃に通院が途絶えてしまった場合、大学生くらいの年齢でコレステリン肉芽腫などの手術が必要な疾患になることもあり得ます。中耳炎の治療では処方された薬を途中でやめずに必ず飲みきることが大事です。それでも再発するようならば、大きな病気に発展しないよう予防するため、院内での鼓膜切開や、提携先の病院で鼓膜に換気用の小さなチューブを挿入する手術などを行います。中耳炎は生後6ヵ月から3歳までが比較的多いのですが、発熱しているときに耳をよく触るといった場合は、気兼ねなくご相談ください。
完全予約制の小手術や補聴器専門の外来で相談に対応
診療室の造りで工夫されている点がありますね。

あえて処置室と診察室に分けず、広々とした空間の中心に私の診察デスクを配置しています。診察中でも、点滴やネブライザーをしている患者さんにも私の目が届くようにしておきたいからです。処置そのものは熟練のスタッフたちが担当してくれていますが、誰でも薬剤へのアレルギー反応を引き起こす可能性はあります。万が一のときに、迅速に対応できるようにしているのも開業当初からのこだわりです。
新たに検査機器も導入されたとお聞きしました。
副鼻腔炎の診断を院内で迅速に行いたかったのが主な理由で頭頸部CTを導入しました。副鼻腔炎も中耳炎同様によくある病気でそのままにしていても治る例も多いとはいえ、決して油断はできません。副鼻腔炎は鼻炎や風邪などが原因の鼻性だけではなく、虫歯や歯周病が招く歯性もあります。まれに鼻の中にできた腫瘍によって引き起こされている例もあり精査が必要です。風邪が治って1〜2週間しても鼻詰まり、異臭、後鼻漏、顔面痛などがあるときは、一度受診してください。
花粉症については同院ではどのように診療されていますか?

花粉症シーズン最盛期は鼻詰まりなどへの対症療法が中心になり、院内もどうしても混み合います。一方、オフシーズンは予防的な治療を始める絶好の機会とも言えるでしょう。舌下免疫療法を開始したり、トリクロロ酢酸で鼻の粘膜を焼いたりといった治療ができる時期は限られています。来シーズンの症状を抑えることが期待できますので、早めに取り組んでみてはいかはでしょうか。
木曜の専門の外来では補聴器の相談などもできるのですね。
基本的に木曜日は完全予約制の専門の外来のみとして、時間が必要な診療をじっくりと行う日としています。例えば、中耳炎や花粉症などの小手術は専門の外来で実施。また、高齢の方からの補聴器の相談が増えているので、聞こえの検査の後に院内ですぐに業者に相談できる体制も整えました。本当に耳が悪くなってからでは補聴器のサポートがあっても脳が音を認識しなくなってしまうので、気になるようならぜひご活用ください。その他、睡眠時無呼吸症候群の診察も行う日としています。場合によっては自宅でできる簡易検査や精密検査に進み、CPAP治療にも対応可能です。
全身との関係も重視。小さな悩みでも頼れる相談窓口
診療において何を大切にしていますか。

何よりも患者さんのお話をしっかり聞くことです。鼻、耳、喉は接近していて患者さん自身説明が難しいことも多いからこそ、話しやすい雰囲気づくりを心がけています。また、どの疾患に対しても全身との関係をおろそかにしないことも大事にしています。鼻水に逆流性食道炎、喉の痛みに心筋梗塞が隠れている場合もありますので、「健診結果を見てほしい」といった依頼も歓迎しています。採血データの小さな違和感から、がんの発見につながる場合もあるかもしれません。健康全般に関する相談窓口として、気兼ねなく利用してほしいと思っています。
そのような診療ポリシーを持つに至ったご経歴を教えていただけますか。
大学の工学部を卒業して7年間、情報機器メーカーに勤務しました。ある時、病院で「人体は機械と違って換えが利かない」という医師の一言を聞き、医学に興味を持つようになったんです。そして、社会人入試で合格した大学では一回りも年下でしたが、それでも毎日同級生たちと切磋琢磨していましたね。大学卒業後は病院で小児科や救急医療をはじめさまざまな診療科を経験し、全身を診る土台を培いました。耳鼻咽喉科を選んだのは診断から外科的処置までを1人で担当できるので、患者さんの「ずっと同じ先生に診てほしい」という願いをかなえられると考えたからです。振り返ってみると、工学部時代の勉強も、常に病気の根本原因を論理的に突き詰めていくのに役立っていますね。
最後に今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

将来的には専門の外来で嚥下機能評価もしていきたいと思っています。嚥下内視鏡検査を行い、そこからさらに踏み込んでフレイル問題にも取り組めたらいいですね。高齢者のめまいは耳または下肢の問題による平衡感覚の衰えから引き起こされることが多いと考えられているため、整形外科の先生との連携などもできればと考えています。また、めまいに関しては若い方も増えていて、約80%が良性発作性頭位めまい症とされているため再発防止のための理学療法にも注力したいです。中枢神経由来が疑われるなら迅速に脳神経外科を紹介していますが、今後とも診診連携、病診連携を推進していきたいですね。その他、最近は大人の中耳炎が増えているのも気になっています。帯状疱疹も顔面に沿って出たときは耳鼻咽喉科にご相談ください。どんな小さなお悩みでも「とりあえず、まちだに行ってみよう」と頼りにしていただければ幸いです。






