丹羽 直樹 理事長の独自取材記事
横浜脳神経内科
(横浜市神奈川区/横浜駅)
最終更新日:2025/06/11
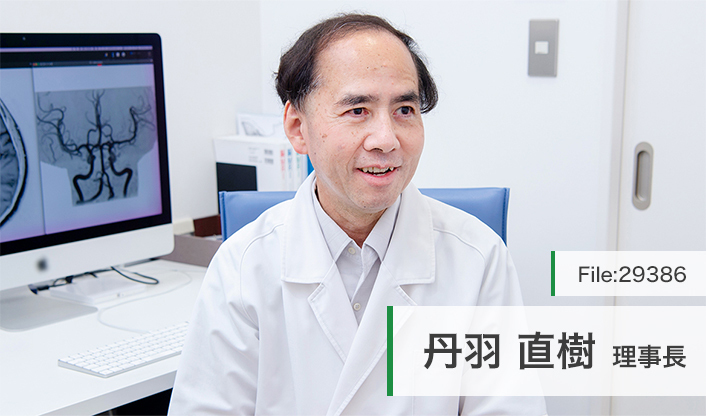
「横浜脳神経内科」の丹羽直樹理事長は、基幹病院の救急医療やリハビリテーション病院で、脳卒中後のリハビリテーションなど豊富な経験を積んできた。頭痛を中心に、身近な所で適切な検査や治療を提供したいという思いから、開業の道を選んだという。横浜駅近くにある同院には、近隣はもとより市外・県外からも、頭痛やめまいといった症状に悩む人が訪れる。頭痛やパーキンソン病については、薬物治療に頼りすぎず、食生活や運動、生活習慣を見直して症状改善に取り組むのが特徴だ。患者への説明やホームページではできるだけ専門用語を使わず、患者が理解し安心できる診療をめざす。頭痛に悩む多くの患者から信頼される丹羽理事長に、同院の診療の特徴や頭痛診療、パーキンソン病診療などについて聞いた。
(取材日2025年4月14日)
生活習慣のアドバイスも取り入れた、包括的な頭痛診療
こちらでは、どのような症状や病気の診療を行っているのですか。

当院は、頭痛診療を中心とする脳神経内科クリニックで、頭痛のほかは、めまい、手足のしびれ、手足のふるえ、まぶたのけいれんなど、さまざまな症状の患者さんが受診されます。また、さまざまな神経内科の病気、パーキンソン病など神経難病も幅広く診ています。私も、院長の石川達也先生も、頭痛や脳卒中、神経内科疾患などの診療を専門とする医師です。頭痛診療に関しては、薬物療法だけでなく、栄養相談や、ヨガなどの運動、睡眠などの生活習慣の改善に関するアドバイスなども取り入れているのが特徴です。
どうして栄養相談や運動に関するアドバイスを取り入れているのですか。
頭痛診療では、薬も必要ではありますが、薬物療法だけでは解決しないことが多いのです。一方で、患者さん自身の生活習慣を少し変えることで改善が期待できることもあるので、栄養相談や運動に関するアドバイスを取り入れています。栄養相談は、管理栄養士や専門的に学んだスタッフが対応し、最初は対面で行いますが、その後はオンラインでも行っています。特に、片頭痛の方は食物アレルギーがある人も少なくなく、原因となる食物を控え、食生活を変えることで、片頭痛の緩和をめざすこともあります。また運動ですが、リラクゼーション効果が期待できるヨガを紹介しています。現代人はストレスが多いため、自律神経系統が緊張に偏りがち。それが片頭痛に影響していることもありますので、ヨガなどで緊張をほぐすことを心がけてもらっています。また、睡眠も頭痛に関係しますから、睡眠も含めた生活習慣を見直すこともアドバイスしています。
どのような患者さんが来られますか。
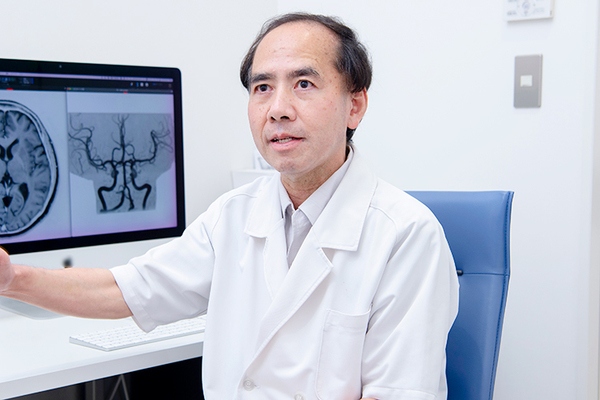
患者さんのうち7割から8割が、なんらかの頭痛を訴えています。そのうち女性の患者さんが8割程度ですね。症状として一番多いのは、片頭痛をはじめとした慢性頭痛ですが、くも膜下出血の方が自分では気づかず、普通に歩いてこられることもあります。また、MRI検査を行ったら、急を要する疾患が疑われ、救急車で専門医療機関に搬送することになったという例も少なくありません。ただの頭痛だと思って受診したのに、命に関わるような病気と診断されてショックを受けられる方もいるでしょう。脳出血以外にも急を要する患者さんは、意外にいらっしゃるのですよ。頭痛は軽症から重症まで幅広く、頭が痛いという一つのキーワードで医療機関にたどり着かれるので、急を要する頭痛かどうかを見極めるのが、私たちに課せられた一番大きな仕事ですね。
高齢化の中で増えるパーキンソン病の診療にも取り組む
パーキンソン病診療にも力を入れているそうですね。

パーキンソン病は高齢化でじわじわ増えてきており、世間にも知られてきていますが、薬物治療がうまくいかず、副作用で苦しまれている患者さんも少なくないのが現状です。当院では薬は最小限にして、早いうちから訪問リハビリテーションを導入しているのが特徴です。というのも、デイサービスなどで集団で受けるリハビリテーションでは、個々の患者さんの症状や生活習慣に合わせることが難しいのです。訪問診療であれば、その方の症状はもちろん生活環境や生活習慣に合わせて、生活に実際に役立つリハビリテーションが行えると考えています。数は少ないのですが私が訪問診療に伺うこともあります。高齢化社会の中で増える病気ですから、今後も力を入れていきたいと考えています。
ところで先生は、どうして脳神経内科に進まれたのですか。
実は紆余(うよ)曲折あって、理系が好きだったので最初はなんとなく理工学部に進んだのですが、もともと生命に興味があって、結局、医学部に入り直しました。医学部で学び、次第に脳に関心を持つようになり、脳神経外科に進もうかと考えたのですが、脳神経外科は、当然手術が主になります。私は脳の構造そのものに興味が移ってきたので、脳の病気を内科的な面から診ていきたいと脳神経内科を選び、千葉大学の医局に入局しました。その後は、大学の関連病院である松戸市立病院(現・松戸市立総合医療センター)の救急部門に勤務し、次に神奈川県にあったAOI七沢リハビリテーション病院に勤務して、主に脳卒中のリハビリテーションを学びました。また、今でいうエコノミークラス症候群に早くから注目して治療や予防を行ってきました。
では、こちらで開業された経緯を教えてください。
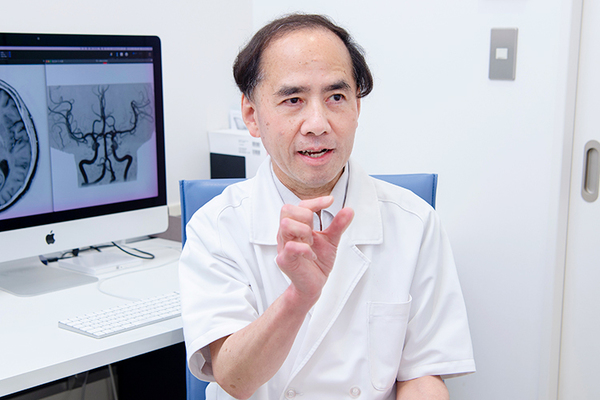
約20年、勤務医を続ける中で、やはり自分で思うような診療を行いたいという思いが高まり、開業を考えるようになり、2002年に八王子で長池脳神経内科を開設しました。その分院として2012年に開設したのが当院です。ただ、八王子と横浜を行き来するのは体力的に負担が大きいこともあり、2022年にこちらを本院として一本化しました。この場所を選んだのは、やはり横浜駅は多くの路線が集まる交通の中心だからですね。ここは駅にも近くわかりやすいですし、通院していただきやすいと思っています。患者さんは横浜の方が中心ですが、藤沢や鎌倉、川崎、都内などからも来てくださいます。
頭痛の悩みに真摯に寄り添い、情報発信にも注力
患者さんと接する際、どのような点を大切にされていますか。

医療関係者は、専門用語を何げなく使ってしまいがちです。例えば「予後」という言葉も、医療現場では日常的に使われていますが、一般の方には少しわかりづらく感じられることもあるかもしれません。そこで、患者さんへの説明や、ホームページの解説もできるだけ専門用語は避けて、一般的な言葉を使うことを心がけています。医師として患者さんに接する中で、いつのまにか身についた習慣ですね。スタッフは信頼できるメンバーがそろっているので、患者さんへの対応はそれぞれの個性に任せています。受付スタッフは航空業界出身で言葉遣いや接遇も行き届き、急患への対応にも慣れているので安心です。勘が良いというか、よく気がついてくれるので助かっています。
頭痛診療で、重視されているのはどのような点ですか。
最初のうちは薬による治療が中心ですが、様子を確認しながら食事や睡眠などの生活習慣などを見直し、薬をだんだん減らしていくことを心がけています。片頭痛の場合、薬も通院もやめられるのがベストです。また、患者さんの悩みやつらさをよく聞くことも大切にしています。例えば、頭痛の経験がない人が上司や同僚だと、頭痛のつらさや痛みを理解してもらいにくいですよね。「頭痛ぐらいで仕事を休むな」とか「頭痛なんか我慢できるだろう」などと言われて職場にいづらくなり、仕事を辞めざるを得ない人もいるのです。そんな悩みもよく聞いて、頭痛をコントロールできるよう治療して、生活の質を上げられるようにと心がけています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
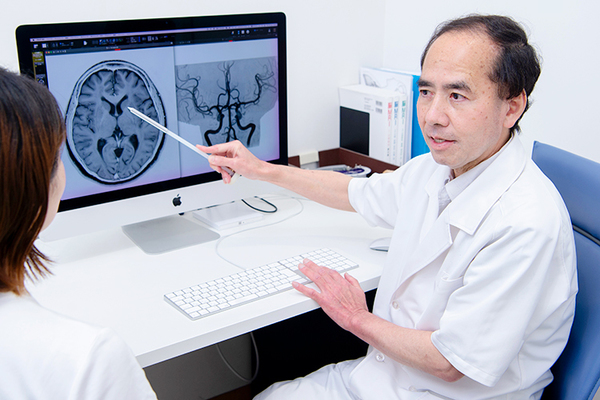
頭痛を我慢したり市販薬に頼ったりしている方に、当院を知っていただきたいと思っています。頭痛は、軽いものから重いものまで幅広く、命に関わることもあります。ぜひ受診していただきたいのは、今まで経験したことのない頭痛を感じる時と、頭痛が1週間以上続いている時です。今までないような痛みがあり、ただごとではないと感じたら、頭の中で重大なことが起きている場合もあります。また片頭痛など慢性頭痛は命には関わりませんが、患者さん本人にとっては生活の質に関わるとても大きな悩みとなります。当院では、薬物治療だけでなく、栄養相談や運動に関するアドバイス、生活指導などを取り入れ、生活全般を見直して頭痛をコントロールできるように取り組んでいます。また、ホームページ上での正しい情報発信にも努めています。頭痛で悩まれている方はぜひ参考にしてください。






